インタビュー 33
このページでは、当研究所教員へのインタビューを通じて、当研究所における研究への取り組みをご紹介しています。
第33回となる今回は、新世代アジア研究部門所属の佐藤 仁 准教授へのインタビューをお届けします。
佐藤 仁 (SATO Jin , Associate Professor / 新世代アジア研究部門 准教授)

―― 先生はもともと、東南アジアがご専門だったのですか?
いや、僕の場合は地域ありきではなく、問題ありきなんです。貧困や開発といったことにもともと関心がありまして。途上国の開発問題のための勉強をしにアメリカに留学している時、夏休みに世界銀行でインターンをしていたのですが、上司だったインド人の森林専門家に、「もし、途上国の貧しい人について研究したいのであれば、彼らが日常的に依存している資源が、どのように使われているのかを詳しく見るのが良い」と助言されました。それまで僕は、開発・援助というと、先進国が、進んだものを遅れた国に持っていく、みたいな発想を持っていました。でもその上司のアドバイスはそうではなくて、そこにあるものがどう活用されているかという視点をまず真ん中に置けというものだったんですね。まさに、資源つまり「そこにあるもの」の潜在的な力をどう表に出していくかというアプローチで、これは当時の僕にとってはすごく新鮮だったのです。このことが今の研究のきっかけになりました。
―― では、現在の研究について教えてください。
僕の今の中心的な関心は、「国家権力による天然資源や環境の管理が、人間の支配にどう転化するか」ということです。例えば日本の場合だと、資源や環境を国家が管理の対象としていくのは明治以降ですよね。明治になってはじめて、それぞれの藩が管理していた森林や鉱山が、明治政府によって中央集権的に管理されていきます。ただ、例えば森林を管理するという時には、森林それ自体を管理するというよりも、森林を管理する労働者を編成し動員し規律化するわけですよね。そういった形で、資源の管理をするためにはその手段として人間社会の再編成をしなければならない。こういったことが、例えば東南アジアの国々でどういった形で現れていたかを研究しようとしています。
―― 「資源」という視点から国家統治を描写するって、おもしろい発想ですね!
資源に注目した統治体制の研究のどこがおもしろいかというと、天然資源って、多くの場合奥地にあるんですよ。奥地というのは、東南アジアだと少数民族の居住地だったりして、政治的な外縁部なんですね。そこにある天然資源を中央集権的に統治するとは、つまり、外縁にいる人々を国家に取り込んでいく過程そのものなんです。今、東南アジアにおいて天然資源の管理に関する行政機関が19世紀末当時どう建設されていったかをまとめているところですが、その機関は内務省という警察・治安を扱う部署の中に入っていました。それはやはり、国家統治に密接に関係していたからだと思います。
―― ちらっと思ったことなんですが・・先生が今研究されているようなことは、戦時中に非常に考えられていたことなのではないかと。つまり、資源を国が管理して、国家総動員的にもっていくという発想ですが。
僕の近著『「持たざる国」の資源論』はまさに、国家総動員に向かっていった日本で、資源という概念がどういった意味を持ったのかが書いてあります。川は川、森は森と呼べばいいものを、なぜ「資源」と呼ばなければならなくなったのか、それがポイントの一つだと思います。様々な資源を使っている生活者の視点から見ると、資源という言葉はいりません。森は森、土地は土地、水は水と呼べばいいわけですから。それを「資源」としてまとめていくのは、統括する上からの視点なんです。日本の歴史の中で、資源という言葉をさかんに使おうとしたのは、まず陸軍でした。陸軍はとにかく、戦争に役立つ諸々のものがどのぐらい日本にあって、どのぐらい民間の手の中にあるのか、そしてそれをどうすれば動員できるのかについて、第一次大戦後以降、真剣に研究するようになりました。ヨーロッパの戦争を見て、これからの戦争は、前線での戦闘力だけではなく、そこにコンスタントに物資を流す、物流の力で勝ち負けが決まると考えたわけです。それで、「資源」という言葉が、「諸々の役に立つもの」の総称としてちょうどいいと陸軍が使い始めました。まさに、「資源」という言葉と、国家権力は非常に密接な関係を持っているといえるでしょう。
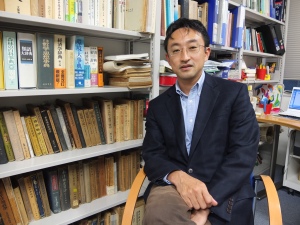
ここまで歴史的な話をしましたが、時代が経つにつれ、土壌、水、大気、生物多様性、そして気候に至るまで、国家の支配する領域がどんどん広がっているといったことも見過ごせません。大気の質について国家が基準を作って・・放射能の話なんてまさにそうですよね。食べ物の安全基準も国が作っているでしょう?我々を取り巻いている環境への国家権力の介入というのは、ずっと拡張してきました。それに対して社会の側の抵抗もあるわけですが、そういった国家と社会のせめぎあいを、アジアのいろいろな国で、そして様々な資源・環境を通じて考えたいと思っています。
―― ちなみに、「資源」という側面から国家統治を考えていくというような先生のご研究に近いことをやるのであれば、何学からのアプローチが可能なのでしょうか?
僕がやっている資源の研究は、「モノと人との関係」なんです。文系理系という日本的な分け方でいうと理系はモノを、文系は人を扱うでしょう?その「関係」をやるところがないんです。例えば工学ではある程度関係も考えるけれど、工学の場合、何かを作ることありきだから、まず歴史に関心がないでしょう?支配・被支配といった政治的なことに関心のある自然科学者はいませんし、天然資源に関心のある政治学者もほとんどいません。結局、自然と人間の関係が経てきた「政治性」みたいなものを正面から取り上げる分野は、ないといっていいと思いますね。
「資源」という言葉に引き付けられた大きな理由というのは、それがバラバラなものを統合してくれるヒントになると思ったからです。タイのフィールドで見たのは、森を管理する森林局、土地を管理する農地改革局、といった具合に断片化した状況でした。学問も同じように断片化しています。森は林学の研究者が、人々の暮らしは文化人類学の専門家が、そして水は水文学の人が、という具合に。でも、そこに暮らす生活者の視点からすると、それらはすべて一体的な資源です。それなのに、その観察者や、現場の外で政策を作る人は、一体的に見る視点を失っています。一体性を失うことが、「専門家」であるということになってしまっています。僕には、「資源」という言葉を通じて、学問の一体性を回復したいという野心があります。資源とは、人間が自然の中に見出す有用性です。物的なものと人的知的なものとが組み合わさって資源はできているので、まさに関係を表現するいい概念なんです。
―― もともとのご関心は、貧困や開発にあったということでしたが、今は、国家による資源の管理が、国家による人間の統治にどう転化するか、ですよね。貧困や開発といったテーマは、もうやられていないのでしょうか?
いや、結局、資源や環境に大きく依存している人たちとは、農村では貧困層なんです。天然資源が豊かなところは奥地だと言いましたが、奥地の土地なし農民は自分の畑を持っていないゆえに、森に入ってきのこを、川に行って魚をと、まさに身の回りの自然環境に依存して生活をしています。ですから、天然資源の支配を論じることは、すなわち、私有財産に乏しい人たちの生活を論じることになります。だから僕の中では、資源の統治は貧困と直結した話で、違うトピックでは全くないんです。
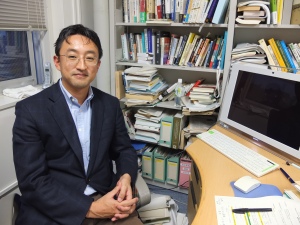
―― なるほど、全部つながっているんですね!先生のご研究も全てつながっているし、それは、現場が全てつながっているからなんですね。
はい、そのように思っています。
―― 学問の中で様々なことを連動させながら、というお話をしていただきましたが、さらに実践の現場でもいろいろとやられていますよね?行政機関のアドバイザーとか。先生のご研究のゴールはどのようなものでしょうかというのが最後の質問です。学問の中で完結するのではなく、実践の現場も視野に入っているのでしょうか?
そうですね・・実践といっても様々なレベルがありますが。少数の専門家しか読まない論文を書くのも大事ですが、僕は、時と場所に応じた「議論の喚起」というのが、社会科学の役割だと思っています。そう考えると、一般の人々に分かるような問題提起をすることが、非常に重要な「実践活動」になります。まださほどできてはいないのですが、一般向けの本を書くとか、新聞記事を書く。あるいは公開講座のようなものをまじめにやることを通じて、問題意識の裾野を広げるというのは重要なゴールになります。そうした他流時代の場では、自分が研究していることが、専門外の人々にとって意味をもつかどうか、厳しくテストされますね。
もちろん、政府のアドバイザー的な仕事、たとえばJICAの専門家になって現地に行くといったこともやります。これは、どんなことが現場で求められているかを知る上でとても重要な機会になっています。国別援助委員会という、一つの現場を考えてみましょう。そこは、例えば、タイに対してどんな援助をしようかを話し合う会議です。経済、教育、環境といった分野の専門家たちが呼ばれて集まります。それぞれの専門の立場から様々な意見が出てきますが、例えば、教育と環境の専門家が話し合って、どちらがどれくらい重要かについての結論は出ません。そういう場面を何度か見たときに、やっぱり、それぞれの「専門」の視点をくみ上げようとしても、物事は統合的には見られないという気がしました。統合は一人一人の頭のなかで、できていないと為されないのです。そして、いろんな見方を統合するというのは、学問の世界よりもむしろ実践の場で必要とされていることが分かってきました。統合という作業は、従来、官僚や政治家に任せていればいいという考え方がありましたが、官僚や政治家は時間や予算、組織的な利害の制約が非常に大きい中で判断する人々です。そうした制約から比較的自由な研究者が、自ら進んで具体的な課題解決のために総合の仕事を担う、全体を見渡せるような絵を描いて見せる、というのは細かな専門的知見を提供する以上に必要だと思うのです。もちろん、社会問題に最終的な答えはありませんから、「違ったあり方」を見せながら、議論を喚起する。このように、社会科学は現場でこそ、求められているのです。
インタビュー後記
今回の佐藤先生のインタビューでは、ご研究の内容ももちろん興味深いものでしたが、研究の姿勢や方向性といったことを非常に勉強させていただきました。現場は一体であるというお話のところで、学問は「分ける」ことが基本にあるような気がしていると私がお伝えした際の、「人間は複雑なものを複雑なまま理解できないからね」というお言葉が印象に残っています。学問は複雑なものを理解するためのものであって、それをより複雑にしてはならないなと改めて思いました。非常におもしろかったです。ありがとうございました。(虫賀)
佐藤 仁 プロフィール
略歴
- 1968.4.
- 生
- 1992.3.
- 東京大学教養学部教養学科卒
- 1994.6.
- ハーバード大学ケネディ行政学大学院修士課程修了(公共政策)
- 1995.3.
- 東京大学大学院総合文化研究科国際関係論専攻修士課程修了
- 1995.8.
- Regional Community Forestry Training Center (タイ・カセサート大学内)客員研究員
- 1998.3.
- 同博士課程修了、博士(学術)
- 1998.4.
- 日本学術振興会特別研究員(PD)
- 1998.9.
- イエール大学Agrarian Studies Program フェロー
- 1999.5.
- 東京大学大学院新領域創成科学研究科環境学専攻助手
- 2000.4.
- 同 助教授。
- 2004.10.
- タイ国天然資源環境省政策アドバイザー(JICA専門家)
- 2007.4.
- 東京大学大学院新領域創成科学研究科准教授
- 2009.4.
- 東京大学東洋文化研究所汎アジア部門准教授
- 2010.8.
- プリンストン大学 Democracy and Development Fellow
- 2011.9.
- 東京大学東洋文化研究所新世代アジア研究部門准教授

