インタビュー 30
このページでは、当研究所教員へのインタビューを通じて、当研究所における研究への取り組みをご紹介しています。
第30回となる今回は、西アジア研究部門所属の長澤 榮治 教授へのインタビューをお届けします。
長澤 榮治 (NAGASAWA Eiji , Professor /西アジア研究部門 教授)

―― 現在の研究テーマについて教えてください。
ここのところ取り組んできたのは、1940年代から50年代のエジプト、最終的に1952年の7月革命を導くころの時代、当時は様々な活動家たちがいたわけですが、その中の共産主義運動に参加した、エジプト人ユダヤ教徒の二人の知識人の個人史を描くということです。同時代の運動の状況、特に1947年の国連のパレスチナ分割決議案とそれをめぐる大きな論争など、そのあたりを中心に考察を進めてきました。これはここ10年近くやってきたテーマですが、だいたい原稿が書きあがろうかというときに、今年の1月からの革命がはじまって、今はその分析もしています。現在にある体制をつくりだしたプロセス、つまり歴史をふりかえりながら、現在の問題を考えるのに何か貢献ができればというのが、最近やってきたテーマです。
それは個人史を描くための背景となる全体状況が必要だからということですが、またこれらの動きの大きな流れや全体像を「個人」と運動との関わりを通じて捉えようということでもあります。先ほど言及しました二人の知識人とは、アハマド・サーディク・サアドとヘンリ・クリエルですが、彼らはともにカイロのユダヤ教徒の家庭に生まれ、それぞれ共産主義運動の組織のリーダーになりました。当時エジプトにはユダヤ教徒は10万人ほどいたのですが、56年の戦争で、イスラエルが、フランス・イギリスと共にエジプトに攻めてきたときに、国内にいたユダヤ教徒に対する迫害が起こりました。それで大半のユダヤ教徒はエジプトを去りましたが、サアドは国内に留まって、イスラーム教に改宗しました。彼はそのあと弾圧されて拘置所で暮らし、釈放されても監視状態に置かれながら電気会社の技師として働きましたが、定年になった頃から著作活動を本格的に開始して、晩年にかなり多くの著作を残した人です。一方クリエルは、自身が指導していた組織から排除されたあと、パリに拠点を移し、アルジェリアなどの第三世界の解放運動に対する資金提供などをして、最後は暗殺されてしまうという運命を辿りました。この二人を対照的に、パレスチナ問題などとからめながら分析してみようというのがメインの研究です。
また最近は、早稲田に本部があるNIHUイスラーム地域研究プロジェクトに関わっています。拠点の一つが東大にあり、いろいろな研究のサポートをしています。その中に若手中心のパレスチナ研究班があるのですが、こうした研究の一環として、研究者仲間で「パレスチナ学生基金」という組織を立ち上げまして、ガザ難民のために奨学金を送る活動もしています。関心のある方はご支援いただければと思います(http://palestinescholarship.web.fc2.com)。

―― 先生の研究の向かうところというか、個々の研究の背後にある大きな問題関心とはどのようなものでしょうか?
私の基本的な問いは、「近代とは何か」です。アラブとかエジプトにとっての近代とは何かというところです。
以前にエジプトの「資本主義論争」を取り上げたことがありました。資本主義論争というのは、日本でもやられましたし、特に非ヨーロッパ世界にとっての近代とは何かということです。たとえば、ユダヤ教徒出身の知識人サアドは、ヨーロッパ近代を背負いながらいわゆる「東洋」に向きあうという知的人生を送りました。私がそもそも彼に最初に関心をもったのは、「エジプト資本主義論争」の中でアジア的生産様式という、マルクス主義的なオリエンタリズムというべき、東洋社会論を展開していた点です。「近代」というものを非西洋の知識人がどう認識したか。そしてそれによって、自分の社会をどう分析しようとしたかというのが、私の一番の関心です。今の研究に区切りがついたら、家族関係とか、エジプト社会論のようなものをやりたいと思っているのですが、これはつまり、エジプトの知識人は「家族」や「伝統社会」をどのように捉えたかということです。これからやりたいと考えているのは、革命やらナショナリズムの話というよりむしろこちらの方ですかね。知識人たちが、ヨーロッパの近代社会科学を勉強して、自分たちの社会をどのような枠組みで分析しようとしたか。そこで新しい方法論をどのように出してきているか。一番関心を持っているのはそこですね。
―― なるほど・・。先生の著作や論文の題名を拝見すると、非ヨーロッパ世界、その中でも特に「エジプト」に軸があるように見受けられたのですが・・。
そうですね、エジプトは研究の蓄積もありますし、面白いテーマがたくさんあります、なんでみんなエジプトをやらないのかなと思うぐらいです(笑)。
ただ、私の場合は「地域研究」をしていますが、これは地域の特殊性、異文化を研究すればいいというだけではなくて、人文社会科学のあり方、あるいは近代の知のあり方を問い直すということに、大きな存在意義があるのではないかと思います。「経済学や政治学をある特殊な地域に適用しました、そしたらこういう概念ができました」、というものではなく、近代の人文社会科学の枠組みそのものを捉え直すようなこと、それが地域研究の私ができる、学問的な貢献の一つではないかと思います。特殊な地域の特殊な知識をただ供給するということも、需要としてはあるのでしょうが。
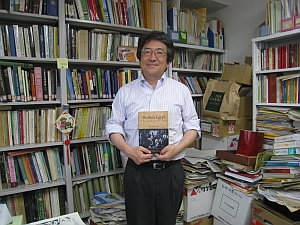
さきほどエジプトの知識人が「家族」や「伝統社会」をどのように捉えたかということに興味があると言いましたが、そうした試みは、日本の場合でしたら、柳田国男とかと比較できるのではないでしょうか。彼らは、近代西洋の学問をよく勉強しているんだけれど、単純にそれを適用しようとするのではなくて、独自の学問を作ろうとしているんですよね。輸入学問の翻訳だけで済ましてきた人も多かったけれど、そうではなくて、自分が西洋を勉強して得た方法や概念を、苦闘して何とか改変しようとしてきたわけで、そこがなかなか面白いなと。これは地域研究の重要な研究領域の一つではないかと思います。
地域研究は実証的にデータを出すことが重要だという意見がある一方、ディシプリンとしての地域研究の枠組みを出すべきだという人たちもいるのですが、私はそのいずれでもない感じです。理論的な関心を保ちつつ、実証的なところでも、一つ一つひねり出して、作品を作っていくというところではないでしょうか。「ここに素晴らしい理論がある、さあこれを適用しよう」というような研究は、やっていけないとは思わないけど、地域研究者であるならば、その地域固有の概念や考え方と、近代的な社会科学概念とをお互い響き合わせるような研究をすべきではないかと思います。理論適用や理論の切磋琢磨といったことは、社会学者なり経済学者がやればいいことで。我々がやっているのはもう少し違うことなんじゃないかと思います。
「現地の知的世界」を捉えるといっても、例えばアフリカのような、非文字社会の場合は全く違うかもしれない。ただしアラブの場合でも私が注目している知識人たちが関心をもっていたのは、「民衆的知識」で、民衆の文字化されていない社会とどう接近するかというテーマでやっていたわけです。こういう社会学者の人たちは、民衆的な思想・知的伝統というのか、物言わぬ人たちの声を聞くというような本を書いていて、それは落書きの研究だったりするんだけど(笑)。彼らは、十分近代的な知識をわきまえていながら、自分たちの固有な文化に接近しようとする。私はそういう人たちを紹介したい。面倒だから自分でそういうことをやればいいじゃないかと言われるかもしれないけれど、それは文化人類学者がやればいいことで。私はそうではなくて地域研究者なので、知識人というワンクッションを置きながら、知識人研究を通して民衆文化研究をするというやり方をとっているといえます。
インタビュー後記
今回の長沢先生のインタビューでは、前半は現在の研究テーマを伺ったあと、私の個人的な興味から、ナショナリズムという概念、近代国家・民族・宗教的区分・言語といった枠組みのそれぞれの関係性について質問させていただきました。そのご回答も非常に興味深かったのですが、インタビュー後半の、「非西洋世界における西洋近代」や「地域研究とは」というお話がとても面白かったため、そちらを中心に記事にさせていただきました。本当に勉強になりました。ありがとうございました。(虫賀)
長澤 榮治 プロフィール
略歴
- 1976.3
- 東京大学経済学部経済学科卒業
- 1976.4
- 特殊法人アジア経済研究所入所
- 1981.2
- エジプト・カイロ大学文学部大学院にて海外派遣として在外研究に従事(-1983.6)
- 1983.6
- 帰国、同研究所調査研究部に配属
- 1992.2
- 地域研究部副主任調査研究員
- 1995.4
- 東京大学東洋文化研究所助教授(西アジア研究部門)
- 1998.4
- 日本学術振興会カイロ研究連絡センター長(-1999.3)
- 1998.4
- 東京大学東洋文化研究所教授(西アジア研究部門)
- 2002.4
- 東京大学東洋文化研究所附属東洋学研究情報センター主任(-2005.3)
- 2008.4
- 東京大学東洋文化研究所副所長(-2009.3)

