インタビュー 29
このページでは、当研究所教員へのインタビューを通じて、当研究所における研究への取り組みをご紹介しています。
第29回となる今回は、東アジア第一研究部門所属の小寺 敦 准教授へのインタビューをお届けします。
小寺 敦 (KOTERA Atsushi, Associate Professor /東アジア第一研究部門 准教授)
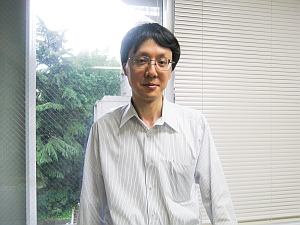
―― 先秦時代の家族を研究テーマにされたきっかけを教えてください。
大学に入った頃は、法律家になりたいと思っていました。でも、法律の本よりも歴史の本を読む方が好きなことに気づいて、一生の仕事にするなら・・と歴史を選びました。さかのぼって考えてみると、私が生まれ育った環境の影響もあると思います。私は滋賀県の大津に生まれまして、三井寺、比叡山が近くにありました。家のそばには、源義仲と松尾芭蕉の墓があるという、義仲寺もありましたし。そのあと奈良に引っ越しましたが、ご存知の通り、あそこは寺と神社と古墳とが日常風景なので(笑)。歴史、特に古代史に親しむと言う意味では、非常に良い環境にあったと思います。
中国史を選んだのは、私の場合、歴史学をやると決めたのが先で、中国を研究したいからではありませんでした。前近代であれば、日本でも欧州でも構いませんでした。ただ中学高校の頃、岩波文庫の青本に入っている漢文の訳注を読んで、それは好きでした。大学に入ると西嶋定生先生の『中国古代の社会と経済』を読んで、その理路整然とした内容に感銘を受け、中国古代史の研究に興味を持ちだしました。でもまあ、気がついたら、私は東洋史を専攻して中国古代史をやっていたというのが、一番事実に近いかもしれません。
あとはやはり、人文学をやるという人は大体そうだと思うのですが、人間、人類社会に対する興味があるということでしょう。人間がどこから来て、どこへ行くのかということに対して、もちろん漠然とですが、関心がありましたね。
古代中国をどこから研究していこうかというときに、もちろん切り口はたくさんあるわけです。そこで「家族」は、社会のいわば基本的な構成単位ですよね。ここでは「家族」を血縁集団として漠然と考えておきます。この家族について、中国の文献ではいろいろなところで説明がなされています。しかしながらそれらの記述を総合しても、私にはよく分かりませんでした。非常にごちゃごちゃしているんです。その錯綜しているところに興味を持ったというか、そこから何かつかめないかなと、学部生の頃に漠然と思ったのがはじまりです。
そして先秦時代のいわゆる家族制度は、後世に与える影響が非常に大きいのです。宗法や宗族といわれるものですが、後代の中国の家族、族制、人間集団のあり方を根底のところで規定していきます。もちろん中国だけでなく、儒教経典などの文献が朝鮮半島や日本に伝わることによって、周辺諸地域にも影響を与え続けてきました。家族制に目を付けたのは、そういう側面もありました。
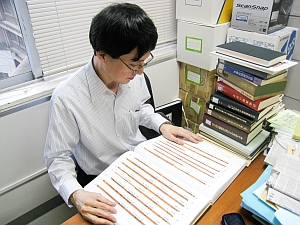
―― 方法論に関して、出発点は歴史学ということでしたが、現在でもそうでしょうか?
そうですね、私自身は、歴史学をやっているという認識はありますね。よそからどう見えているのかは分かりませんが(笑)。歴史学は総合的な学問であって、誤解を恐れずに言えば、何をやろうが、どんな方法を使おうが構わないのです。というより、思想史や考古学など、様々な隣接諸分野の方法論を取り入れて総合的にやらないと、この時代の研究はできないんです。例えば、出土した竹簡を資料として使うとき、古文字学の知識がなければ当然読めないわけです。あと、簡牘(かんとく)学、考古学、内容を解釈するには中国思想や中国文学の知識もいる。なかなか大変なのですが、そういったものを総動員しないと読めませんし研究できません。これを一人でやることは不可能ではないのでしょうが、研究していると他分野の方々との協力が必要になる局面がでてきます。また協力しあうことにより、互いに刺激を与えあって、いろいろとアイデアがでてきます。
私の研究の主軸は、もちろん中国古代の家族史を再構成することにあるのですが、それと平行・関連して、先にお話しした出土資料の研究もやっています。先秦秦漢の出土文献は、通常は発掘調査によって発見されるのですが、盗窟されて香港の骨董市場で売られ、それを博物館や大学が買い戻したものがどんどん増えています。それらは出土地が分からないだけではなく、出土したものでない(=誰かが偽作した)可能性すらあります。そこで理科学的な検査や書かれている内容などを検討することにより、価値ある資料とされるわけです。そういう出土資料は今日存在しない文献を含んでいて、本当に興味深いものです。しかし、やはりこういうものは偽物の可能性が100%ないわけではありません。そのことを頭の片隅に置いておくことは必要だと思います。
―― 先生がやられている「史料的性格に関する検討」とはそういうことですか?
これは研究者としての立ち位置にも関係してくるのですが、史料に書いてあることを、ほとんど無批判にそのまま史実として受け取って、歴史を再構成するという傾向が、最近けっこう強いんです。それはいかがなものかと私は考えます。史料の記述には、必ず一定のバイアスがかかっています。これは私の出身研究室の影響だと思うのですが、中国史を研究する場合に、政治性を無視してはならないと叩き込まれました。今でもそれは間違いではないと思っています。
文献が書かれた背景や、史料自体のもつ性格を考えて研究を進めないと、当時の実態とは全く違ったものを再構成してしまいます。例えば今日の新聞や雑誌といったメディアだって、色眼鏡はいろいろ入っているわけです。そこに書かれていることそのままに現在を再構成したら、今の実社会と違うものができあがるのではないでしょうか。ただ、それら史料の中で、残せる部分と残せない部分とは、工夫すればある程度まで分けられるだろうというのが私の考えです。そういった史料が、どのようにして作られたかを調べることで、ひいては当時の人々のあり方も分かるのでは、というかそれをやらないと先に進めないと思っています。
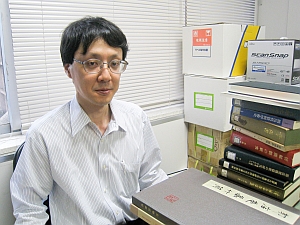
―― 史料も莫大にあって、次々に新しい出土資料が出てきて、本物かどうかも分からないし、そして史料から何かを読み取ろうとするのであれば、「余計なもの」をいかに排除するかを考えなければならない・・なんだか大変そうだなと思ってしまったのですが、研究の面白さとはどんなところですか?
とにかく、文献を読んであれこれ考えているときが一番楽しいです。
―― 古代に思いを馳せるというか、想像したりですか?
いや、ロマンはないですね。どちらかといえばロマンを破壊する方ですから(笑)。ロマンではなく、学問的な事実がどうだったかに興味があります。今手元にある材料を、どう料理して過去をどう再構成していくかというところ、それがこの研究の醍醐味です。
お話しした出土文献もそうですが、遺跡など、考古資料の実物を見に行くのは楽しいことです。誰かが言っていましたが、我々が外で見るものって、大概は土を掘ったものか積み上げたものかどっちかだと・・それは間違いないですね(笑)。でも、見ていて飽きません。これらは、古い時代の人々がどう生活していたか、どう生きていたかを知るための、ほんのわずかな手がかりですから。
インタビュー後記
今回小寺先生のお話を伺い、とにかく文献を読むのが楽しく、好きなのだということと、何とかして過去の本来の姿に迫りたいという先生の情熱的な思いが心に残りました。先生はロマンはないとおっしゃっていましたが、遠い遠い昔のことをいかにして再構成するかというお話、次々と出てくる出土資料の共同での整理など、好奇心が刺激されるお話ばかりでした。ありがとうございました。(虫賀)
小寺 敦 プロフィール
略歴
- 1969.10
- 生。
- 1996
- 東大・文・東洋史卒。
- 1998
- 修士(文学・東大)
- 2000
- 遼寧大学歴史系高級進修生(2002まで)
- 2003
- 日本学術振興会特別研究員(PD,2006まで)
- 2003
- 博士(文学・東大)
- 2004
- 北京大学考古文博学院訪問学者(2005まで)
- 2006
- 東文研助教授
- 2006
- 海外研修(復旦大学文物与博物館学系訪問学者)
- 2007
- 帰国

