インタビュー 26
このページでは、当研究所教員へのインタビューを通じて、当研究所における研究への取り組みをご紹介しています。
第26回となる今回は、汎アジア研究部門所属の名和 克郎 准教授へのインタビューをお届けします。
名和 克郎 (NAWA Katsuo, Associate Professor /汎アジア研究部門 准教授)
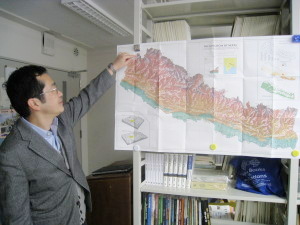
―― 研究において、学問的には文化人類学、地域的にはネパール、特に極西部に位置するビャンス地域を選んだきっかけを教えてください。
高校生や浪人だった頃にNHKの市民大学という番組で、山口昌男先生や岩田慶治先生など、今考えると錚々たる先生方が授業をされていました。それを見ていて、人々の間に住み込んでそこからある世界を描いていくというやり方に惹かれたのが、文化人類学に興味を持った一つのきっかけです。
ネパールを選んだのは偶然ですが、ビャンスに決めたのには少し理由があります。修士の時、当時ネパールで最も有名な人類学者だったドル・バハドゥル・ビスタ先生にお会いする機会がありました。西洋の著名なネパール研究者の研究についてお話をうかがっているうちに、「西洋人の人類学者の多くは、観光地化されていたりして楽に調査できるところばかりやってけしからん」という話になったのですが、一緒に行った友人が極西部ネパール出身だったからでしょう、先生は続けて、「彼の故郷には交易をやっているビャンシーという人たちがいるが、自分も含めて誰もまだ本格的に研究していない。海外の研究者はなかなかきついところに行かないが、お前がそこへ行ったらどうか」と仰って。これが、ビャンスの研究を始めたきっかけです
きついと言うのは・・今考えると、ビャンスはとにかく遠いんですよ。首都のカトマンドゥからだと、最初に行った当時で、カトマンドゥからバスを乗り継いでまる二日、その後一日半歩いて郡庁所在地に着き、そこから更に二日半歩いてやっとビャンスの村に到着でした。今は郡庁所在地まで乾季ならバスで行けるようになりましたが。しかしビャンスを選んだのは私にとっては大正解でした。交易をしている人が多くて外来者を歓待する習慣があり、自分達の社会や文化について正しく書いて外部に伝えて欲しいと考えている人が多くいるところでしたので。私はバリバリと誰に対しても簡単に話を聞けるタイプの人間ではなく、実はフィールドワークは大変苦手なのですが、本当にビャンスの人々に助けていただいてきています。これは強調しておきたいです。なんでこんな素晴らしいところに誰も調査に来ないのだろうと思っていたのですが、就職して理由が分かりました。ネパールの雨季は6月から9月なので、極西部の道路事情を考えると夏休みを利用して調査に行くことがほとんど出来ないのです。大学院生の頃はそんなものだろうと思っていたのですが、最近は本当に遠いなあと思います。
―― そのビャンスでのフィールドワークを中心に、具体的には現在何を研究されていますか?
東文研のサイトを見ていただくと、研究テーマはいろいろと書いてありますが・・今、主にこれをやっていますというのはなかなか難しいです。というのも私は前もって研究テーマをはっきり決めて調査をするというより調査を通じて問題意識自体を作っていくことが多いのですが、現在いろいろな方向にそれが展開しつつあって、その全体を、あまり抽象度を上げずにまとめてお話するのが難しくなっておりまして。
今までやってきた主題としては、社会範疇の構成、儀礼の変容過程、言語使用が一応の三本柱です。まず社会範疇とは、「我々は~である」とか「あの人たちは~である」というような、カテゴリー化の問題です。「実体としての民族は存在しない」と昔書きましたが、個々人や集団がそれぞれに「~民族」を定義することはできるけれども、それを越えて民族が実体として存在すると考えずに、社会範疇に関わる様々な過程を見ていこうというような話です。

儀礼関係の研究も延々やっております。ビャンスでは20世紀後半以降、様々な儀礼が変化してきているのですが、葬送儀礼が一番分かりやすいと思うので、少し具体例をお話ししましょう。葬送儀礼といっても、最後に祖先の地に魂を送る儀礼についてです。昔は、「グォン」という儀礼がありました。遺骨を載せられたヤク(動物)が各家を回り、人々はそれに酒や食べ物を与えます。その後ヤクは、死んだ人の家に連れて行かれ、遺骨は家の中に入れられます。その遺骨は、死んだ人の服を着せた人形に結びつけられます。人形の両側におじさんが座って、だいたい一昼夜かかる「セーヤーモ」という口頭伝承を語ります。セーヤーモの最後のところで、死者の魂を、交易で用いている道を通って北へ北へと送って、チベットの北の方にあるとされている祖先の地まで送ります。
しかし20世紀の後半から、動物使用の問題や、時間がかかりすぎることを理由に、人々はこの儀礼を変えていきます。違う動物を用いるようにしたり、動物をやめて人形だけにするなどという動きがありました。さらにはセーヤーモをやめて、ヒンドゥーの『ガルダ・プラーナ』を読むという新しい形態も出てきました。僕が主に住んでいた村は、『ガルダ・プラーナ』を読むようになってもう40年程経っていました。これはヒンドゥー化しようということから出てきたことだったのですが、その後チベットから逃げてきた仏教の僧侶の一部がビャンスに住んだことから、僧侶にチベット語の経典を読んで貰うことも選択肢の一つとなりました。ここまでは1998年に提出した博論に書いたのですが、それ以後に状況はまた変わったのです。セーヤーモを、自分たちの言語をデーヴァナーガリー文字(ネパール語、ヒンディー語などを書く文字)で書いたものと、ヒンディー語訳との対訳という形で出版した人がいて、この本が民族団体によって村々に配られたのです。そうなると、セーヤーモをやめていた村々でも、自分たちの本があるのだから『ガルダ・プラーナ』ではなくこれを読もうということになりました。ただ、昔のグォンに戻ったわけではなくて、儀礼自体は新しいやり方のままで、読む本が、『ガルダ・プラーナ』からセーヤーモに戻った、しかもセーヤーモそのものでなくヒンディー語訳を読み上げている、ということです。こういった変化がなぜ起こったのか、そして、儀礼はある意図を持って変えることが出来るけれども、意図通りに何かが変わるとは限らない訳ですが、実際の変容の過程と意図とのずれ、またそこで生じた逆説的な事態をどう捉えるか、といったことを考えています。
例えば、これは言語使用の問題ともかかわりますが、セーヤーモを動詞の形態まで溯って細かく分析すると、そこには、朗誦することがそのまま魂を送ることであるような言語的な仕掛けがなされているように見えます。ところが、ヒンディー語訳を見ると、その仕掛けをうまく翻訳することは出来ていないように見える。また、セーヤーモはその場にいる男性達の誰もが朗誦に加わることが出来たのに対して、ヒンディー語訳の読み上げは、『ガルダ・プラーナ』やチベット語の仏典と同様、とりあえず魂に対して道を指し示すテクストとして、その場での理解をあまり考えずに正しく淡々と読んでいる感じです。もちろんヒンディー語をじっくり読めば意味は判るのですが、それは基本的に儀礼の場の外で行われることになっています。そのようなことで、自分たちの伝承を取り戻す為に行われたがはずのセーヤーモの対訳の出版が、実は同時に儀礼と伝承のある種の抽象化をさらに進めているのではないかと、現在のところ考えています。

―― 特定の事例の描写で終わるのではないところが、勝手な印象ですが、人類学っぽいというか・・。
うーん、確かに、私は地域研究者である以上に(文化)人類学者でありたいと思っています。ただ、「人類学」と言う以上、特定の地域についてこれが分かりましたというだけではなく、それが人類全体についての何らかに繋がっていないといけないと思うのです。それが、なかなか形にならないというか(笑)。 私は今のところ、長期の住み込み型フィールドワークという人類学の慣習的な調査法に開き直って仕事をしているのですが、特定の理論を前提として事例を斬って終わりという仕事は、基本的にはやりたくありません。ある理論に沿って観察される事象を斬るだけであれば、現地の人々に色々な迷惑をかけてまで長期のフィールドワークを行う意義は、多くの場合見出せないのではないでしょうか。人類学者に「あなたの理論は何ですか」と聞かれると、唖然としてしまいます。もちろん、それは理論を学ばないということでは全くないし、フィールドに行けば何かがわかるというナイーブな経験主義で押し通せる程の才覚が自分にないことも判っています。また、偉大な地域研究者が一生をかけて行う、特定地域に関する知識や情報を膨大に積み上げることによって何かが見えてくるという類の研究が、自分に出来ないことも確実です。もちろん、地域に関する研究蓄積からは学ばなければならないことが常に山のようにあることは確かですが。ちなみに私は現在、東文研付属の東洋学研究情報センターにも所属していて、そこでは日本ネパール協会から御寄贈いただいた1950年代、60年代の貴重な文献の整理を進めております。例えばこれは19世紀半ばに最初に出された、カースト的な違いにより様々に異なった条項が定められた法典で、先ほどお話しした社会範疇の問題に関わるものです。
フィールドワークで分かることは、ある限られた期間のある限られた人々について、「私が」見聞したことなので、「私が書いたある人たちに関する記録」は、ある人たちの営為自体ではありません。しかしそうであっても、ある人々について、誤りではない新たな知見を明らかにするようなものを常に書きたいと思っています。同時に、それが先ほど言った意味で人類学的な射程を持っていることが理想です。実際に、人々・・僕だったら主にビャンスという地域の人々とお付き合いをしながら、そこから出てくることを、様々な理論との関係で書くのだけれども、できればそれが、その地域なり人々なりに関する何らかの知見を新たにもたらすとともに、参照した理論に対しても何らか返せるものでありたい、と思っています。
インタビュー後記
失礼ながら、「理論ありき」というのが、これまで私が人類学に対して抱いていた勝手なイメージでした。しかし今回のインタビューで、名和先生のフィールドワークの意義についての考えや、「ビャンスの人々のお陰」という意識、そしてインタビューの最後に語って下さった、「自分が当たり前であると考えていたことがひっくり返ることをできる限り発見したいし、それが楽しい」というお言葉から、そうではないのだということが分かりました。ただ名和先生には、ネパールから帰国された翌日にインタビューを受けていただきまして、人類学者はタフであるというイメージは、そのまま残ることとなりました。ありがとうございました。(虫賀)
名和 克郎 プロフィール
略歴
- 1966. 11
- 生。
- 1990.3
- 東京大学教養学部教養学科卒
- 1992.3
- 東京大学大学院総合文化研究科文化人類学専攻修士課程修了
- 1999.3
- 東京大学大学院総合文化研究科超域文化科学専攻博士課程修了,博士 (学術)
- 1992.11
- Research Scholar, Centre for Nepal and Asian Studies, Tribhuvan University, Nepal (-1995.3)
- 1996.4
- 日本学術振興会特別研究員 (DC2, -1998.3)
- 2000.1
- 日本学術振興会特別研究員 (PD, -2000.3)
- 2000.4
- 東文研助教授
- 2002.9
- Visiting Fellow, Clare Hall, University of Cambridge (-2003.8)
- 2007.4
- 東文研准教授

