書籍紹介
馬場 紀寿 著『仏教の正統と異端――パーリ・コスモポリスの成立』(東京大学出版会)
著者による紹介
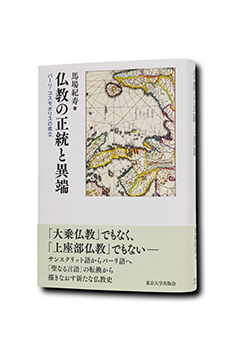 高校「世界史」の教科書で「仏教」にかんするページを開けば、「大乗仏教」と「上座部仏教」という二種類の仏教が存在したことが説明されています。教科書だけではありません。仏教学の研究書でも同様の説明がしばしばされています。しかし、近代以前の文献に、「大乗仏教」(Mahāyāna Buddhism)と「上座部仏教」(Theravāda Buddhism)という概念はまったく存在しませんでした。あたかもこの二種類の仏教が歴史上に存在し、両者が脈々と存続してきたかのような言説は、近代に生まれたものなのです。
高校「世界史」の教科書で「仏教」にかんするページを開けば、「大乗仏教」と「上座部仏教」という二種類の仏教が存在したことが説明されています。教科書だけではありません。仏教学の研究書でも同様の説明がしばしばされています。しかし、近代以前の文献に、「大乗仏教」(Mahāyāna Buddhism)と「上座部仏教」(Theravāda Buddhism)という概念はまったく存在しませんでした。あたかもこの二種類の仏教が歴史上に存在し、両者が脈々と存続してきたかのような言説は、近代に生まれたものなのです。
それでは、「大乗仏教」や「上座部仏教」という近代製の分類概念を用いずに、南アジアと東南アジアの仏教史全体を捉え直すには、どうすればよいのでしょうか。本書は、サンスクリット語からパーリ語への言語の転換に焦点を当てて、スリランカと東南アジアに成立したパーリ語の国際空間――本書で「パーリ・コスモポリス」と命名――を論じたものです。パーリ・コスモポリスの成立にかかわるパーリ仏典の文献学的分析をしつつ、およそ1世紀から20世紀に到る南アジア・東南アジア仏教史を時系列に沿ってまとめました。
ベンガル湾を介して南アジアと東南アジアに広がった、聖なる言語のコスモポリスが、21世紀に到ってなお国民国家の戦争で多数の血を流している現代社会に与える示唆は、小さいものではありません。
目次
| 凡例 |
| 序 章 聖なる言語の国際空間 |
|---|
| 一 世界史の中の南アジアと東南アジア |
| 二 パーリ・コスモポリスはどのように成立したのか――本書の目的 |
| 三 「大乗仏教/上座部仏教」の二分法を超えて――本書の視座 |
| 四 正統と異端をめぐって――本書の構成 |
| I 不在の中心 |
| 第1章 仏教に「正統と異端」はあるのか? |
| 一 丸山眞男の「正統と異端」論 |
| 二 古代インド政体の「正統」 |
| 三 インド仏教の「正統と異端」――出家教団、仏典 |
| 四 結論――宗教多元社会の自律分散型ネットワーク |
| 第2章 インド仏典の多元的伝承――部派と大乗 |
| 一 インド仏教の正典形成? |
| 二 集結仏典(三蔵)のリスト |
| 三 韻文仏典のリスト |
| 四 説一切有部における正典の不在 |
| 五 大衆部の四阿含と「小蔵」 |
| 六 部派仏典の多元性 |
| 七 部派と大乗の共存 |
| 八 結論――複数の正統 |
| 第3章 サンスクリット・コスモポリスの仏教 |
| 一 サンスクリット・コスモポリスの成立 |
| 二 サンスクリット仏教としての説一切有部 |
| 三 大乗のサンスクリット化 |
| 四 「ブッダの言葉」をめぐって |
| 五 サンスクリット・コスモポリスを越える仏教 |
| 六 結論――仏教の中心なき中心 |
| II 中心と周縁 |
| 第4章 スリランカにおける史書の誕生 |
| 一 大寺派の成立 |
| 二 インドの仏教――マヒンダ |
| 三 スリランカの正統――デーヴァーナンビヤ・ティッサ王 |
| 四 スリランカの仏教――聖地としての大寺 |
| 五 『島史』の構造と編纂者の編集作業 |
| 六 結論――大寺の自画像 |
| 第5章 パーリ語原理主義 |
| 一 サンスクリット語に抗して |
| 二 パーリ語原理主義の概要 |
| 三 インド本土由来のアーリヤ語論――説一切有部との共通要素 |
| 四 注釈文献の編纂――仏典言語論(Ⅰ) |
| 五 正典の確定――仏典言語論(Ⅱ) |
| 六 結論――「ブッダの言葉」の伝承方法 |
| 第6章 ブッダゴーサが示す仏教の未来 |
| 一 ブッダゴーサの三宝論 |
| 二 インド仏教の正法論 |
| 三 ブッダゴーサが用いた先行資料の言説 |
| 四 正法存続の基準 |
| 五 正法存続の年数 |
| 六 結論――正法「五千年」存続可能論の仏教史的位置 |
| III 周縁の正統 |
| 第7章 正史の王権論――「教え」と「異端」 |
| 一 『大史』が継承した三つの特徴 |
| 二 編集作業に見る『大史』の構造 |
| 三 「教え」と「異端」の構図 |
| 四 『小史』が継承した三つの特徴 |
| 五 仏教と王権の関係 |
| 六 正史モデル |
| 七 結論――パーリ・コスモポリスの参照点 |
| 第8章 パーリ・コスモポリスの形成 |
| 一 パーリ・コスモポリスとは何か? |
| 二 聖なる言語の闘争――五―一〇世紀 |
| 三 パーリ語の勝利――一一―一二世紀 |
| 四 パーリ・コスモポリスの時代――一三―一八世紀 |
| 五 パーリ・コスモポリス後の近代――一九―二〇世紀 |
| 六 結論――正史モデルの再演 |
| 第9章 近代における「大乗仏教」と「上座部仏教」の創造 |
| 一 西欧仏教学の近代版パーリ語原理主義 |
| 二 釈宗演の近代版パーリ語原理主義 |
| 三 仏教の新たな二分法 |
| 四 「唯一仏教」という理念 |
| 五 「仏法西漸」の確信による英語発信 |
| 六 「上座部仏教」の成立 |
| 七 結論――パーリ語原理主義が生んだ仏教の分類概念 |
| 終 章 神々の言葉からブッダの言葉へ |
| 一 中心なき中心としてのインド仏教――一―一〇世紀 |
| 二 周縁のスリランカで成立した大寺派のパーリ文献――四―五世紀 |
| 三 スリランカの上座部における大乗派と大寺派の対立――六――〇世紀 |
| 四 インド仏教の衰退とスリランカ仏教の刷新――一一―一二世紀 |
| 五 パーリ・コスモポリスという国際空間――一三―一八世紀 |
| 六 近代における仏教の分類概念の成立――一九―二〇世紀 |
| 注 |
| あとがき |
| 図版出典一覧 |
| 初出一覧 |
| 略号・参考文献 |
| 索引 |
情報
馬場 紀寿 著 『仏教の正統と異端――パーリ・コスモポリスの成立』
東京大学出版会, 368ページ 2022年2月 ISBN: 978-4-13-016043-8
出版社ホ―ムペ―ジへ
東洋文化研究所教員の著作

