書籍紹介
アンソニー・リード 著,太田 淳・長田紀之 監訳,青山和佳・今村真央・蓮田隆志 訳『世界史のなかの東南アジア(上・下巻)』(名古屋大学出版会)
訳者による紹介
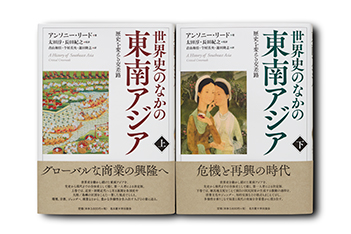 本書はこの数十年間の東南アジア史研究を牽引してきたアンソニー・リードが、東南アジア地域全体の歴史を先史時代から現代まで描き上げた作品であり、現時点でのリードの最新作、かつもっとも包括的な本である。各章は国家や時代にもとづくのではなくテーマごとに立てられており、取り上げる時期は重複し、議論は地域を横断する挑戦的な作品である。
本書はこの数十年間の東南アジア史研究を牽引してきたアンソニー・リードが、東南アジア地域全体の歴史を先史時代から現代まで描き上げた作品であり、現時点でのリードの最新作、かつもっとも包括的な本である。各章は国家や時代にもとづくのではなくテーマごとに立てられており、取り上げる時期は重複し、議論は地域を横断する挑戦的な作品である。
「この地域の10ヵ国の国民国家史については、日本語でも他の言語でも多くの優れた作品があり、いくつかはそうしたネーションの物語を統合しようと努めている。それでも私は、本書が国民国家や時代よりもテーマを強調したことにより、日本の読者が何らかの新しい知見を得る一助となることを願っている。本書は個別の国家や王家の物語の役割を控えめに描き、一般の人びとにもっとも影響を与えた、地殻変動的な深く広い変化に対してより大きな注意を向けている。そうした人びとは、政治的指導者が主張するほど国境によって分断されてはいないのである」(「日本語版への序」)。
本書は教科書としても使えるように作られている。わたしたち訳者はそれを意識して、現在から将来にかけて、日本の文脈に埋め込まれながら東南アジアの歴史を学ぶ学生や一般の読者に理解してもらえるような訳文をめざした。同時に、本書をつらぬく独自のキーワードや、新たな、または既存のものを読み替えた概念が正確に伝わるよう、原資料にあたることはもちろん、リード自身と常に連絡をとり、批評的な視点を忘れないようにしながら最善を尽くしたつもりである。ぜひ本書を多くのかたに手にとっていただけたらと願っている。(青山和佳)
上巻目次
| 日本語版への序 |
| はじめに |
|---|
| 第1章 熱帯湿潤地域の人びと |
| 穏やかな気候、危険な環境 |
| 森と水と人びと |
| 人口が少ないのに多様なのはなぜか? |
| 農業と近代語族 |
| 稲作革命と人口の集中 |
| 国家と社会の農業基盤 |
| 食と衣 |
| 女と男 |
| 中国でもなく、インドでもなく |
| 第2章 風下の地のブッダとシヴァ |
| インド的国家をめぐる論争 |
| 青銅、鉄、土器 |
| 仏教徒世界とサンスクリット化 |
| 「憲章の時代」のシヴァとナガラ 900-1300年 |
| 玄関口としてのヌグリ —— オーストロネシア系の諸港市 |
| 大越と中国との国境 |
| 国家に属さない大多数の人びと |
| 13-14世紀の危機 |
| 第3章 貿易とネットワーク |
| 陸路と海路 |
| 生産の特化 |
| アジア海域市場の統合 |
| オーストロネシア系とインド系の開拓者たち |
| 東アジアの貿易システム 1280-1500年 |
| イスラームのネットワーク |
| ヨーロッパ人の参入 |
| 第4章 都市の発展と世界市場向けの生産 1490-1640年 |
| 東南アジアの「商業の時代」 |
| 世界市場向けの作物 |
| 船と商人 |
| イノベーションの中心としての都市 |
| 貿易、銃、新種の国家 |
| アジアの商業組織 |
| 第5章 宗教革命と近世 1350-1630年 |
| 東南アジア型信仰 |
| 上座部仏教コスモポリスと大陸部の国家形成 |
| イスラームのさまざまな始まり —— 商人と神秘主義者 |
| 最初の世界戦争と分極化の連鎖 1530-1610年 |
| 競合する普遍主義 |
| 多元性、宗教の境界、そして「高地の野蛮人」 |
| 第6章 アジアとヨーロッパの邂逅 1509-1688年 |
| 欧華都市 |
| 文化的媒介者としての女性 |
| 文化的混淆 |
| イスラームの「発見の時代」 |
| 東南アジアの啓蒙主義 —— マカッサルとアユタヤー |
| 近世的形態としての銃砲国家 |
| 第7章 17世紀の危機 |
| 大分岐論争 |
| 長距離貿易の衰退 |
| グローバルな気候変動と局地的危機 |
| 危機の政治的帰結 |
| 第8章 民俗語的アイデンティティ 1660-1820年 |
| 18世紀の文化的凝集 |
| シンクレティズムと現地化 |
| 宮廷・寺院・村落における表演 |
| 歴史・神話・アイデンティティ |
| 凝集とその限界 |
| 第9章 中国語化した世界の拡大 |
| 大越の15世紀革命 |
| ベト人の拡張 —— 南進 |
| 広南国南辺の多元的フロンティア |
| 大国化する阮朝ベトナム |
| 「華人の世紀」と商業の拡大 1740-1840年 |
| 南方の経済フロンティアの中国人たち |
| 第10章 熱帯プランテーションへの道 1780-1900年 |
| 胡椒とコーヒー |
| 必需農産物の商業化 |
| 新たな独占 —— アヘンとタバコ |
| ジャワにおける強制された植民地農業 |
| プランテーションとアシエンダ |
| 大陸部三大デルタの経済圏 —— 米の単一作物生産 |
| 植民地化前後の成長の比較 |
| 第11章 自律性の退潮と最後の抵抗 1820-1910年 |
| シャム ——「文明」化による生き残り |
| コンバウン朝ビルマ —— 悲運の近代化 |
| 阮朝ベトナム —— 儒教原理主義の高揚 |
| 「保護」されるヌグリ |
| スマトラのムスリム —— イスラームという代案0年 |
| バリの黙示録 |
| 東部インドネシアの島々 —— 動き回る「ビッグマン」たち |
| 最後まで国家を逃れる人びと |
| 訳 注 |
下巻目次
| 第12章 国家をつくる 1824-1940年 |
|---|
| ヨーロッパのナショナリズムと領域画定 |
| ヌサンタラの諸政体 —— 多数からふたつへ |
| 極大化するビルマ、生き長らえるシャム |
| ウェストファリアと中華帝国 |
| 国家のインフラストラクチャーを建設する |
| インドシナ —— 国家はいくつあるのか |
| 新たな主権空間における民族構築 |
| 国家の生成、未完のネーション |
| 第13章 農民の非自律化ペザンタイゼーション |
| —— 人口増加と貧困 1830-1940年争 |
| 人口増加 |
| インヴォリューションと農民の非自律化 |
| 二重経済とブルジョワジーの不在 |
| 女性を従属させる |
| 貧困の共有と健康の危機 |
| 第14章 消費する近代 1850-2000年 |
| 危うい環境に適した住居 |
| 食物の進化 |
| 魚、塩、肉 |
| 嗜好品と飲み物 |
| 布と衣服 |
| 近代的服装とアイデンティティ |
| 表演 —— 祭礼から映画へ |
| 第15章 進歩と近代 1900-1940年 |
| 絶望から希望へ |
| 教育と新たなエリート |
| ネーション概念の勝利 —— 1930年代 |
| 男性的近代をめぐる交渉 |
| 第16章 20世紀半ばの危機 1930-1954年 |
| 経済的危機 |
| 日本による占領 |
| 1945年 —— 革命のとき |
| 独立 —— 革命か、交渉か |
| 第17章 軍と王とマルクスと —— 権威主義的転回 1950-1998年 |
| 民主主義の短い春 |
| 銃が革命を継承する |
| フィリピン式独裁 |
| 「保護」された君主制の鋳直し |
| インドシナ諸王の黄昏 |
| タイ —— 正法王の再創造 |
| 共産主義者の権威主義体制 |
| 第18章 商業への回帰 1965年以降 |
| ついに訪れた経済成長 |
| 増える米、減る子ども |
| 指令経済諸国の開放 |
| 得たものと失ったもの |
| 陰鬱なコスト —— 環境破壊と政治腐敗 |
| 第19章 ネーションをつくる、マイノリティをつくる 1945年以降 |
| 高度近代主義の時代 1945-1980年 |
| 教育とナショナル・アイデンティティ |
| ピューリタン・グローバリズム |
| 統合された、しかし多元的なる世界への参入 |
| 第20章 世界のなかの東南アジア地域 |
| 地域の概念 |
| グローバルな比較 |
| 訳者解説 / 訳 注 / 参考文献 / 文献案内 / 索 引 |
情報
アンソニー・リード 著, 太田 淳・長田紀之 監訳, 青山和佳・今村真央・蓮田隆志 訳
『世界史のなかの東南アジア(上・下巻)』
名古屋大学出版会, 398ページ(上巻)/386ページ(下巻), 2021年12月 ISBN: 978-4-8158-1051-1(上巻), 978-4-8158-1052-8(下巻)
東洋文化研究所教員の著作

