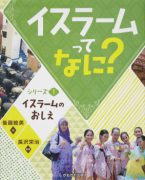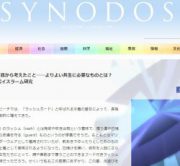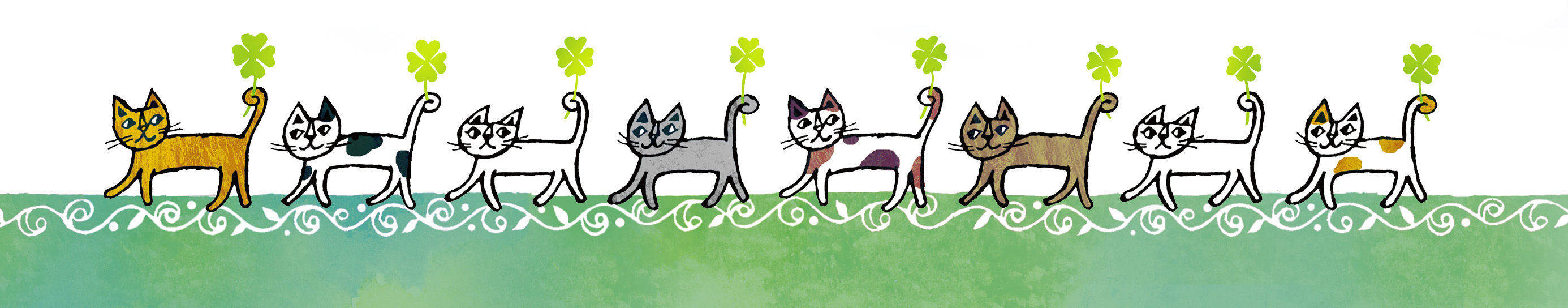イスラーム教ってなに?

私が答えます
後藤 絵美 (学術博士)
Emi Goto, Ph.D
東京大学
日本・アジアに関する教育研究ネットワーク 特任准教授
東洋文化研究所 准教授
研究テーマ:現代におけるイスラームの理解と実践。最近はハラール産業や仏のブルキニ問題を事例に、さまざまな社会での「ムスリム」と「それ以外」という分断の傾向について研究を行っています。
イスラームとは神に身をゆだねること
イスラームとはアラビア語で神に身をゆだねることを意味します。ムスリム(イスラーム教徒、「イスラームをする人」という意味)にとって、神とは世界を創造し支配する唯一で絶対的な存在です。7世紀のアラビア半島で、ムハンマドという名の預言者(神の言葉を預かった人)を介して、神の言葉が人間に伝えられたと信じられています。神の言葉はクルアーン(コーラン)とよばれる書物のかたちで現在まで残されています。
イスラームの意味は一つでも、そのとらえ方は一つではない
神に身をゆだねるとは具体的に何をすることなのでしょうか。世界には十数億のムスリムがいると言われています。さまざまな土地のさまざまな環境の中で、それぞれに異なる生活を営むムスリムの人々ですが、彼らが共通して信じたり、大切に思ったりしていることがあります。神の存在や、預言者の存在、クルアーンが神に由来すること、来世で人は神の裁きを受けることなどです。一方で、文化や社会の違い、個人の考え方の違い、そして、時代によるそれらの変化によって、神が人間に何を命じているのか、何を望んでいるのか、その理解が異なってくる場合もあります。どのような服装がよいのか、何を食べることがよいのか、どんな暮らしをすればよいのかなど、同じくムスリムと呼ばれる人々の間にも、考え方や行動に違いや変化がみられます。
多様な理解や実践も含めてイスラーム教
こうした多様な姿を含めてイスラーム教だということができます。ところが最近、これとは逆の主張が頻繁に聞かれるようになっています。ムスリムのあいだでも、ムスリム以外の人々のあいだでも、「イスラームとはこういうものである」「ムスリムとはこういう人々である」という、規範的なとらえ方が広がりつつあるのです。そしてこの動きは、現代世界にさまざまな摩擦を生み出しています。ここで注目する「ハラール」もまた、こうした流れと関係があると言えそうです。