News
東文研セミナー「パブリック・ヒストリー—多様なる歴史実践から生まれる開かれた歴史—」が開催されました
報告
本セミナーでは、日本の歴史研究では未だほとんど顧みられていないパブリック・ヒストリーや、それにインパクトを与えている歴史叙述の諸転回について論点を整理し、「パブリックな場にある歴史(history in public place)」や「人びと自身が創り出す歴史(people's history)」、そして「歴史する(doing history [保苅 2004]あるいはhistorying [Munslow 2010])」ことの可能性と問題点、そしてその研究/実践の今後の展望について議論された。
まず菅豊教授(東京大学)が「パブリック・ヒストリーとは何か?—歴史実践研究に向けての基本的枠組み—」と題して、本セミナーに関する発題を行ない、続いて岡本充弘名誉教授(東洋大学)による基調講演「パブリックな場にある歴史」が行われた。
以上の発題、講演をふまえ、北條勝貴准教授(上智大学)のコメント後、登壇者及びフロアを交えた活発な議論が交わされた。
当日の様子
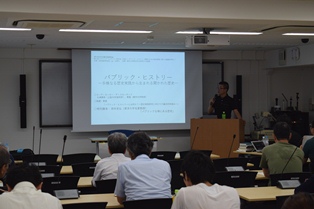 |  |
 |  |
開催情報
日時:2016年9月10日(土)13:00〜
場所:東京大学東洋文化研究所大会議室(3F)
発表者、コーディネーター、ディスカッサント:
○発題:菅豊(東京大学教授)「パブリック・ヒストリーとは何か?—歴史実践研究に向けての基本的枠組み—」
○基調講演:岡本充弘(東洋大学名誉教授)「パブリックな場にある歴史」
○コーディネーター・ディスカッサント:北條勝貴(上智大学准教授)、菅豊
主催/共催:
パブリック・ヒストリー研究会(科研「パブリック・ヒストリー構築のための歴史実践に関する基礎的研究」(研究代表者:菅豊)グループ)、東京大学東洋文化研究所班研究「東アジアにおける「民俗学」の方法的課題」研究会(主任:菅豊)、現代民俗学会
担当:菅
登録種別:研究活動記録
登録日時:WedSep1415:10:072016
登録者 :菅・川野・藤岡
掲載期間:20160910 - 20161210
当日期間:20160910 - 20160910

