News
東文研セミナー「地域文化活動(闘牛)に対する外部影響と、その対応に関する協働的研究―新潟県の国指定重要無形民俗文化財「牛の角突き習俗」をめぐって―第1回(通算6回)勉強会(2017年度 サントリー文化財団「地域文化活動の実践者と研究者によるグループ研究助成」)」が開催されました
報告
2017年11月25日(土)15時より、東文研セミナー「地域文化活動(闘牛)に対する外部影響と、その対応に関する協働的研究—新潟県の国指定重要無形民俗文化財「牛の角突き習俗」をめぐって」第1回(通算6回)勉強会が開催された。本セミナーは、2017年度サントリー文化財団「地域文化活動の実践者と研究者によるグループ研究助成」の主催によるものである。当日は、13名の地域文化活動の実践者(小千谷闘牛振興協議会会員、および北斗会会員)や関係者が集った。本セミナーは、「北斗会「総会」―角突きの未来について「若手」が忌憚なく語り合う」をテーマに進められ、北斗会メンバーによる活発な意見提言が行われた。
当日の様子
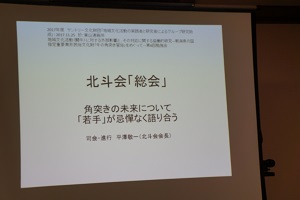 |  |
 |  |
開催情報
日時:2017年11月25日(土)15:00―17:00
会場:小千谷市東山住民センター(東山連絡所)http://www.city.ojiya.niigata.jp/site/shisetsu-map/shisetsu-13.html
勉強会のテーマ:「北斗会「総会」―角突きの未来について「若手」が忌憚なく語り合う」
スケジュール:
15:00―17:00 サントリー文化財団「地域文化活動の実践者と研究者によるグループ研究助成」第1回勉強会(※クローズド形式)
○司会・進行 平沢敬一(北斗会会長)、菅豊(東京大学)
勉強会の趣旨:
いまから20数年前。小千谷の角突きに関わり始めた10~20歳代の若者たちが、これからの越後の角突きを守り、その文化を発展させ、 時代の流れに沿った角突きを目指すために「北斗会」を発足した。ただ、それは「会」としての名称は付けられているが、実際は角突きを愛する同世代が緩やかにつながった仲間の集まりといった方がいいだろう。北斗会は、角突き牛・北斗を共同購入・飼育し、その後、角突きの勢子の主力として活躍している。いまやそのメンバーの存在を抜きにして、小千谷の角突きは成り立たないといっても過言ではない。
北斗会が発足して20数年後。その「会員」たちも、いまでは30~40歳代になった。そして角突きの現在を担う中心として、育った。いま、まさに「北斗会」世代が、小千谷闘牛振興協議会の運営を真剣に、責任をもって考えるべきときが到来したのである。
小さな疑問や意見でもかまわないので、参加者には是非ご準備いただきたい。(文責・平沢敬一、菅豊)
コーディネーター
平澤敬一(北斗会会長)
平沢忠一郎(小千谷闘牛振興協議会実行委員長)
菅豊(東京大学東洋文化研究所教授)
主催
小千谷闘牛振興協議会、「地域文化活動(闘牛)に対する外部影響と、その対応に関する協働的研究―新潟県の国指定重要無形民俗文化財「牛の角突き習俗」をめぐって―」プロジェクト(サントリー文化財団「地域文化活動の実践者と研究者によるグループ研究助成」)、日本学術振興会科学研究費補助金「パブリック・ヒストリー構築のための歴史実践に関する基礎的研究」(研究代表者:菅豊)、東京大学東洋文化研究所班研究「東アジアにおける「民俗学」の方法的課題」研究会(主任:菅豊)
担当:菅
登録種別:研究活動記録
登録日時:Thu Nov 30 09:42:38 2017
登録者 :菅・川野・藤岡
掲載期間:20171125 - 20180225
当日期間:20171125 - 20171125

