News
東文研セミナー「民俗学のデジタル・ヒューマニティーズ的展開」(科研「「野の芸術」論―ヴァナキュラー概念を用いた民俗学的アート研究の視座の構築」(研究代表者:菅豊)第10回研究会)が開催されました
報告
2021年12月19日(日)13時から東文研セミナー「民俗学のデジタル・ヒューマニティーズ的展開」が開催された。本研究会は、菅豊教授(東京大学)を研究代表とする科研プロジェクト「「野の芸術」論―ヴァナキュラー概念を用いた民俗学的アート研究の視座の構築」の第10回研究会である。
研究会では、まず俵木悟教授(成城大学)から本研究会の趣旨説明として、本研究会で議論を進めるデジタル・ヒューマニティーズとは何か、また国内外の民俗学における研究動向が紹介され、問題提起がなされた。
続いて、河瀬彰宏准教授(同志社大学文化情報学部)から「近年のデータサイエンスによる民俗学研究」、日高真吾教授(国立民族学博物館人類基礎理論研究部)から「国立民族学博物館における研究情報の可視化・高度化の取り組み」と題し、自身の研究領域や所属先において自身が手掛けるデジタル・ヒューマニティーズ的取り組みについて発表がなされた。
発表を受け、後藤真准教授(国立歴史民俗博物館研究部)から議論の整理と、両者への質疑応答が行われたのち、全体討論として菅教授や俵木教授、そして約50人の参加者も交えた活発な質疑応答や討論が交わされた。
なお研究会当日は、新型コロナウイルス感染拡大に伴う感染症予防の観点から、オンライン会議アプリケーションであるZoomを活用したリモート会議形式で開催された。
※本講演はJSPS科研基盤B「「野の芸術」論―ヴァナキュラー概念を用いた民俗学的アート研究の視座の構築」(研究課題/領域番号19H01387)の研究成果である。
当日の様子
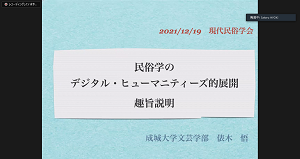 | 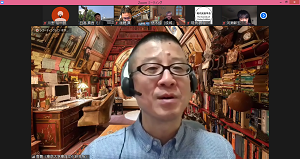 |
 | 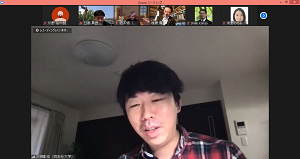 |
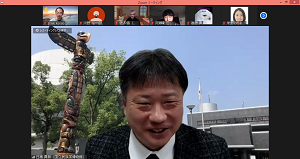 | 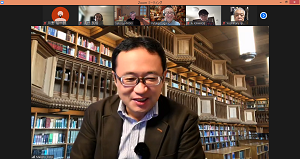 |
開催情報
日時:2021年12月19日(日)13:00~
会場:オンライン開催(オンライン会議システムZoomを使用)
発表者:
河瀬彰宏(同志社大学文化情報学部)「近年のデータサイエンスによる民俗学研究」
日高真吾(国立民族学博物館人類基礎理論研究部)「国立民族学博物館における研究情報の可視化・高度化の取り組み」
コメンテーター:後藤真(国立歴史民俗博物館研究部)
コーディネーター:内山大介(福島県立博物館)、菅豊(東京大学東洋文化研究所)、俵木悟(成城大学文芸学部・趣旨説明)
趣旨:
近年の人文科学において学際的に取り組まれている「デジタル・ヒューマニティーズ」であるが、これまで日本の民俗学においてはその動向が注目されることはほとんどなく、近年はむしろ「乗り遅れ」への危機感が表明されている(e.g. 菊地 2019, 俵木 2019)。しかし民俗学は、文字資料のみならず、人びとの語りや記憶や身体技法、また図像・映像・音声・物質といった多様な形態をとる資料を取り扱い、それらを地理的・歴史的な比較や体系化等によって分析・考察することを旨としてきた。またそうして得られた研究の成果を、専門家のみならず、広く一般の人びとまで含めて共有し、活用することで、自らの生活文化を省みて理解する視点を提供することを目指してきた。このような学問としての性格は、データサイエンスやデジタルテクノロジー、デジタルメディアと親和性を有し、その発展の恩恵を大いに受けるものであるはずだ。この研究会では、研究の手法とその成果の活用の両面から、民俗学のデジタル・ヒューマニティーズ的展開の可能性を探りたい。
菊地暁 2019「文化資源:オープンであること/デジタルになること」『日本民俗学』300
俵木悟 2019「民俗学とデジタル・ヒューマニティーズ」『日本民俗学』299
■共催:「野の芸術」論研究会(科研「「野の芸術」論―ヴァナキュラー概念を用いた民俗学的アート研究の視座の構築」グループ(研究代表者:菅豊))、現代民俗学会
担当:菅
登録種別:研究活動記録
登録日時:ThuDec2310:13:462021
登録者 :菅・田川
掲載期間:20211224 - 20220224
当日期間:20211219 - 20211219

