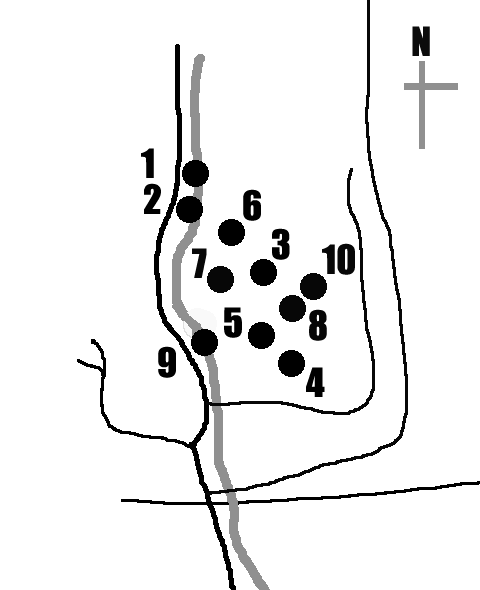 |
1.BARA SONA
MASJID (1526) 2.DAKHIL DARWAZA (16世紀前半) 3.CHAMKATTI MASJID (15世紀後半−16世紀前半) 4.LATTAN MASJID (1475?) 5.TANTIPARA MASJID (c.1480) 6.FIRUZ MINAR (1486?) 7.LUKOCHOLI DARWAZA (16世紀中頃) 8.CHIKA BUILDING (15世紀後半-16世紀前半) 9.GUMPTI DARWAZA (1512?) 10.QADAM RASUL (1513) 11.KOTWALI DARWAZA 12.旧城壁 |












