「ファトフアリー・ハーンの母、妻、嫁:19世紀イランの地方有力者の『家』と女性」
第16回東文研・ASNET共催セミナーが10月21日(木)に開催されました。
以下、報告させていただきます。
日時:10月21日(木)午後5時~6時
場所:東京大学東洋文化研究所 ロビー
テーマ:「ファトフアリー・ハーンの母、妻、嫁:19世紀イランの地方有力者の『家』と女性」
報告者:阿部尚史(東京大学グローバルCOE)
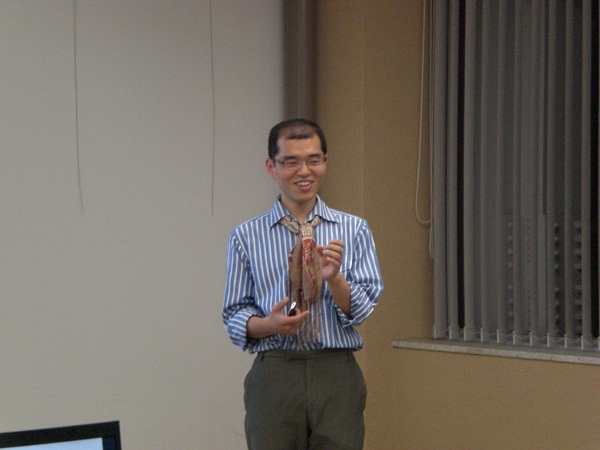
発表要旨
本報告では、被相続人の死に際してのムスリムの女性による財産請求が、家産の維持や後継者との関係を考慮した上でなされた、
という仮説を検討することを目的とした。具体的には、19世紀イランの地方有力者であったファトフアリー・ハーン・ドンボリー死後の
相続を取り上げ、彼の遺産目録に見られる女性の取り分(婚資や相続分)の受領にかかわる問題を検討した。
特に注目したのは、婚資mahrである。被相続人の母、妻、嫁の婚資が遺産目録には債務として計上され、
その割合は全債務35%ほどであった。他の取り分も含めると、全遺産に占める女性の割合は約半分に達することを指摘した。
イスラームの聖典クルアーンでも明記されている、婚資の支払いは、果たしてどの時点で行われるべきなのか、
アラブ圏での研究成果や19世紀の法学学説、社会慣行も含めて紹介し、婚資の支払いは婚姻契約成立時に限らなかった点を指摘した。
そのうえで、再度、ファトフアリー・ハーンの事例に戻り、特に母の婚資が残存している点を説明した。
また、被相続人の祖父の遺産相続にも、女性の財産請求権が残存していたことを述べた。
そして、最終的に、今回取り上げたケースでは、後継者と血縁関係にある女性は、家産の維持を意識して財産請求を行ったと結論づけた。
質疑においては、婚資の役割が曖昧であるため、その社会的意義をより詳しく見る必要がある点や、
本研究で取り上げた有力者層と庶民層を区別して考えるべきではないか、という指摘をはじめ、
家産という中東にはなじみのない術語を使うことの妥当性などにも議論は及んだ。
婚資の説明を丁寧にすべきであったこと、また財産の移動経路や請求権の残存など複雑な内容を含んでいたため、
図を効果的に利用するなど視覚からご理解いただけるような工夫を凝らすべきであったと反省している。
こうした点を今後の報告に生かしたい。最後に、ご多忙中にもかかわらずご参加くださった方々に謝意を申し上げたい。
[阿部尚史]


次回の第17回東文研・ASNET共催セミナーは10月28日(木)午後5時より、東文研1階ロビーにて開催されます。
http://www.asnet.u-tokyo.ac.jp/node/6986
多くの皆様のご参加をお待ち申し上げております。

