「イランにおける「新天文学」の受容:19世紀ペルシア語天文書『形象学訳稿Tarjome-ye Hei’at』を中心に」
第34回東文研・ASNET共催セミナーが2011年9月1日(木)に開催されました。
以下、報告させていただきます。
※英語版レポート
http://www.asnet.u-tokyo.ac.jp/node/7190
日時:2011年9月1日(木)17:00-18:00
場所:東京大学東洋文化研究所 1階ロビー
テーマ:「イランにおける「新天文学」の受容:19世紀ペルシア語天文書『形象学訳稿Tarjome-ye Hei’at』を中心に」
報告者:諫早庸一(日本学術振興会特別研究員PD)
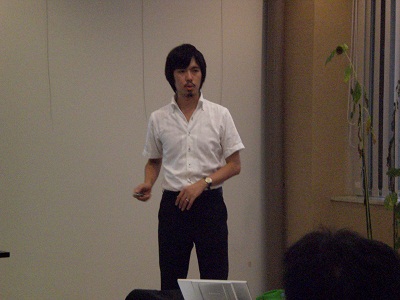

【報告要旨】
本報告においては、新出史料であるペルシア語天文訳書『形象学訳稿』の内容を紹介しながら、イランにおける「新天文学」受容の一側面を見ていきました。ここでいう「新天文学」とはケプラー(1571-1630年)以降の時代における、西欧発信の天文学のことです。
当該テーマについては、これまでほとんど研究されていません。こうした状況のなか、現在留学中のイランにおいて、あるペルシア語天文訳書の一写本に出会うことが出来ました。それがミールザー・マスウード(1791-1849年)の手になる『形象学訳稿』です。この訳稿は新天文学のペルシア語訳書としては知られる限り最も早期のもので、その序文によれば原書はフランス語です。
今のところ原書の正体を突き止めることは出来ていませんが、著者についてはそれなりに情報があります。著者ミールザー・マスウードは晩年には外務大臣も務めた人物で、自らの語学の才でもって身を立てた人物でした。時のロシア皇帝は使節として来訪したミールザー・マスウードのフランス語力に驚いたというエピソードも残っています。
この訳稿のなかには、古代ゾロアスター教占星術に遡ることのできるタームが用いられるなど、著者が古い用語で新しい概念を説明しようとしている部分があります。その一方で、イスラム教普及地域で西端子午線が通る場所として地理学上有名であったカナリア諸島はアラビア・ペルシア語の名称ではなく、フランス語転写で表記されており、著者は必ずしも地域古来の科学に配慮してはいません。新しい知を既存の知を用いて訳すケースもあれば、既存知によらずに新語を導入するケースもあり、その場その場で著者の取る態度は様々です。
ミールザー・マスウードは特にキャリアの初期においては翻訳家と表現し得る人物であり、必ずしも天文学の専門家ではありませんでした。科学文献がまずは翻訳家の手によって訳され、その後に専門家による翻訳が続いていくという流れは、イランに特徴的なわけではなく、西隣のオスマン帝国や日本においても共通して見られる事象です。
質疑においては、同書がペルシア語で記された新天文学の書としては最初のものだとしても、ペルシア語以外に例えば欧語で直接、もしくはオスマン帝国を経てトルコ語やアラビア語で間接的に新天文学がイランに入っていた可能性は無いのか、さらに今回紹介した訳稿がどの程度人々に読まれ、後世に影響を与えたのか、といった今後考えていかねばならない諸点について的確なご指摘をいただきました。御礼申し上げます。
[諫早 庸一]



