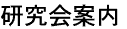
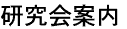
岸本美緒「所有についてのノート-比較史研究会をふりかえって」
関本照夫「市場と商業についてのノート-比較史研究会を振り返って」
三浦 徹「契約についての小括」
岸本美緒
「比較史」をめぐる近年の動向を考えてみると、研究のタコツボ化を打破して国際的ないし地域横断的な比較の視野をもつことの必要性が強調される一方で、比較史の方法については、かつてのような楽天的態度をとることが難しくなっているように思われる。その理由の一つは、比較に際しての「近代化」或いは「世界史の基本法則」といった普遍的(かつ一定の価値付けを帯びた)座標軸が力を失っていることである。それでは、それぞれの文化の固有の性格を強調し、諸類型の共約不可能性を論ずればよいかというと、それも直ちに「文化本質主義」という批判を蒙るであろう。
上記座標軸の有無をX軸、本質論的傾向の有無をY軸にとってみるならば、(X+、Y+)の組み合わせは「アジア的停滞論」のごとき「ねじれた二分法」(小谷汪之の評言)に陥り、(X+、Y-)の組み合わせは自文化中心的な啓蒙的進歩主義に陥り、(X-、Y+)の組み合わせは、対話なき相対主義に陥ってしまうということになろう。残るは(X-、Y-)の組み合わせだけだが、座標軸も文化的固有性の議論もないところで「比較」をしようというのは難しい。その結果、「面白いトピック持ちより」式の表面的な「比較」に終わってしまうか、そうでなければ、従来の比較の方法を批判することに主要な存在意義を見出すような消極的な「比較」に終わってしまいがちである。しかし、実際に我々が「中国は」「福建は」などと語る際には、暗黙のうちに何らかの比較枠組の設定と類型化を行っているのであって、「いったい我々は何をしているのか」を自覚的に考えてみる必要があろう。そうした観点から、「比較の方法」を積極的に考えてみたいというのが、私がこの研究会に参加させていただいた動機であった。
「所有」という語が、現代日本語において一義的な意味をもつのか、また他の文化圏において正確な対応語をもつのか、といえばそうした保証は全くないので、そもそもそれをどうやったら比較できるかというのは難しい問題である。例えば杉島敬志のように、土地の「所有」という概念を明確なロック的意味(それ自体論争のあるところであろうが、杉島は、自己所有の観念にもとづく労働所有説とする)に限定し、それ以外の人間と土地との関係行為を別の語(「土地制度」など)で表現しようとする方向もあるだろう(杉島敬志 1999)。しかしそうした峻別は、ロック的な所有観念を世界史上の類似の観念群のなかに位置付けるというよりは、却って孤立させてしまう恐れもあるように思われる。近代ヨーロッパにおける非ロック的所有権論はもとより、前近代の中国やイスラーム世界におけるそれなりに「私的所有」的な現象も、「所有」という枠組みのなかでロック的なそれと比較してみる価値の十分あるものであろう。
ここでは、「所有」という語をロック的意味に限定することなく、この語自体を拡張・柔軟化する方向、即ち「所有」という語で近似的にくくれる共通の課題が多くの人間社会に存在すると考える方向で話を進めたい。その課題とは、大略以下のようなものとして考えたい。
人間が全く孤独で暮らしている場合、或いは全く紛争のない社会で暮らしている場合には、所有ということは問題にならないであろうが、多くの人間が競合する社会で秩序を保つためには、ある人間ないし人間集団が自己・他者・万物について意志のままに動かし得る範囲につき、何らかの考え方がある程度相互の間で共有されることが必要である。即ち、「誰が」と「何を」の双方において何らかの線引き(分節化)が行われ、「誰が」「何を」「どのように」好きなようにできる、という対応関係が共通認識として成立していることが求められる。これは、この認識について対立や紛争が存在しないということではなくて、対立があるときに議論ができるような枠組みが存在するということである。さらにそうした考え方は、必ずしも「誰か人間が何か物を所有する」という形で表現されるとは限らない。「無所有」或いは「神霊など超自然物による天地・人間の所有」といった逆説的な形で、彼らの言わんとすることが表現される場合もあるだろう。
そのような「所有」の観念は時期により地域によって千差万別であろうが、そうしたバラエティがどのような広がりをもって存在するのか、我々の知る「所有」観念がそのなかでどのような位置付けをもつのか、全体的な眺望を可能にするような地図を素描することができるだろうか。
私の考えている方法は、可能な限りニュートラルな共通の軸を設定し、我々の知る「所有」の諸相を、有る意味では非歴史的にそのなかに位置付けて鳥瞰してみたいということである。(「非歴史的」アプローチについては森村進1997など)。「所有」のあり方はむろん、歴史的文脈のなかで極めて複雑な様相を呈するが、それをいくつかの単純な側面へと分解してみれば、興味深い比較の可能性が見出せるのではないか。例えば、焼畑農業社会や遊牧社会における所有権の発生と近代の無体財産権の発生を比較して論じる加藤雅信の著書(2001)などはその例である。この研究会の関連でも、例えば、中国やイスラーム社会で国家的土地所有説が経済において持っていた意義と、近代の土地公有説との比較(後述)などは、興味深い論点になるように思われる。
歴史的文脈を捨象した「比較」などは、歴史研究者にとっては興味索然たるものかも知れないが、従来の比較史の問題点は、むしろ、過度に歴史的文脈(ヨーロッパの)をもった内容過剰な座標軸が設定されていたことである。その結果、「時代区分」をめぐる不必要な紛糾が、ヨーロッパ以外の歴史学において引き起こされたのである。ここでは、「所有」をめぐる人間の有意識的無意識的な工夫には、いくつかの有限なパターンがあるのではないかという見通しのもと、それらを「およそ人間の考えうる所有論の広がり」の地図のなかに位置付けてみる、そうした例を示したい。そういうレベルでは、ある程度ニュートラルな比較ができると思う。そうした「部品」がさまざまな文化的・歴史的文脈のなかで組み合わされて独特の個性ある社会を形作るわけだが、「部品」そのものは、時代を超え、文化圏を超えてある程度利用可能な面があると思うのである。
いきなり全体的眺望を得ることはできないので、私が比較的なじんでいる中国の例を中心に、主として土地所有を例に話を進めよう。前近代の中国の「所有」のあり方は、土地売買の盛行を始めとして一見近代的所有権に類似するものであり、裁判などにおいても、そうした所有権は当然のこととして一応保護されていたといえる。そのような意味で、例えば清代中国の民事的裁判において私的所有権の保護が目指されていたと主張することは正しいであろう(P.C.C.Huang1996)。ただ、その所有の正当性の「語り方」を見ると、法律上、そうした私法的な権利がポジティブな形で規定されることは少なく(むしろ何々をしてはならないというネガティブな形。それはHuangも認めている)、訴えにおいても悪者によって「冤抑」を受けているという形で主張される(寺田浩明1997)。裁判のみならず、経世的な議論のなかでの土地所有論をみても、「土地は民の有するところ」或いは「土地は君主の有するところ」といった語句はしばしば登場するが、それは民や君主が土地を思いのままに利用処分できる権利を積極的に主張するものというよりは、「土地は民の有するところであるから君主の思うままにはできない」「土地は君主の有するところであるから豪民のほしいままにはできない」といった否定的な文脈で現れる(岸本美緒1986)。すなわち、社会のなかで皆が調和的に暮らしている状況を理想状況とした上で、それを乱す者に対する批判の裏返しとして「所有」が問題となる。「所有」の語り方のこのようなパターンを「全体調和優先型」(以下「全体型」)として、「個別権利優先型」(以下「個別型」)と対比してみることができよう(寺田氏のいうB規範とA規範)。
この場合、所有の本源に関する論理は、「全体型」は「全体のなかでの公正な分配」に帰着するのに対し、「個別型」は「社会の形成に先行する個人の占取や労働投下」に帰着することが自然である。中国の場合は前者の考え方が強く(「井田の崩壊」論)、それに対しロックなどの議論は後者の典型であるといえよう。むろん、井田崩壊後転転と受け継がれてきた土地所有につき、「個別型」の主張をすることもありえよう。また、後述のように、労働所有説が全体の富を増進させるという「全体型」の功利主義的な見地から主張されることもある。したがって、単純に類型化できるものではないが、おそらく、「所有」の正当性の語り方のあらゆる事例について、この両者をいわば「原色」のような基本要素として考えることができよう。
ただし、こうした語り方の相違から、直ちに「全体型=所有権観念の未発達=集団主義=実質的正義論」「個別型=所有権観念の発達=個人主義=形式合理的法観念」といった通説的図式を導くべきではない。注意すべき点をいくつか挙げてみたい。
(1)「全体型」の論理のなかで事実上の所有権が極限にまで強化されることはいくらでもあり得る。即ち、中国においては「民の所有に政府が介入することは却って混乱をまねき全体社会の害になる」といった考え方から、むしろ民間の土地所有に介入せず放任する傾向が強かった。一方、「個別型」の論理を貫徹するとしても、そのなかで所有権者の合意により厳しい規制が課されるということもある。
またロック自身をはじめとして、個別的権利の保護を強調する近代西欧の議論のなかでも、それが結果として全体の福利に寄与に寄与するといった功利主義的な説明のしかたも多いのであって(「取引費用の低減」といった経済学的説明もその一つのバリエーションであろう)、全体はどうあれ個々の権利が重要といった「原理的リバタリアン」はむしろごく少数ではないか(私的所有の功利主義的な見地からの擁護について批判的に論じたものとして、ライアン1993)。即ち、裁判など法的枠組の内部では「個別の権利」を基点に論じられるとしても、その権利の正当性が問題になるようなより原理的な議論の場面では、「全体型」の論理が登場せざるを得ないということである。プラグマティックな発想のもとでは、両者は自然にからみあい、論理が全体型か個別型かということは、事実上の所有権の強さ(自由に使用・収益・処分できるかどうか)ということとはほとんど関係がない。
(2)また、論理が全体型か個別型かということは、「集団主義か個人主義か」という性格づけともほとんど関係がない。個別的権利主張の単位となるのは、「個人」とは限らない。共同体や社団の権利主張も、全体社会に論理的に先立つ固有の権利の主張であるならば、個別型ということができる(その際、その内部では全体型の論理構成がなされることもあろう)。ここで全体型、個別型というのは、それぞれの場に応じた語り方の問題であって、ある社会全体が全体型であったり個別型であったりするという意味ではないのである。むろん、どちらが優勢な語り方かという問題はあるであろうが。
全体型の論理構成のなかでは、個別的権利主張をもつ強固な団体が成立しにくい結果、むしろ「個人主義的」な行動様式が優勢になるということもある。中国にせよ、イスラーム世界にせよ、全体型の論理構成のなかで極めて個人主義的な行動様式が目を引くことは、我々にとって馴染み深い問題である。こうした行動様式を「近代的」ととれば、前近代中国やイスラーム世界は極めて「近代的」ということになる(イスラーム自由都市論)。一方で、団体から個人へと受け継がれる「権利観念」に「近代」の指標を見出すならば、前近代中国やイスラーム社会には、「近代的権利の確立は見られない」ということになろう。これは、どちらが正しいという問題ではなくて、「近代」の定義のしかたの問題なので、むしろ「近代的」というような言葉を使わずにその概念的中身を直接に論じたほうが適切な議論ができる。
(3)イスラーム世界での「征服地において土地の物自体の所有権はムスリム共同体全体にある」という考え方は「全体型」に近いといえる。しかし、中国の場合、全体を見渡して正しい配分をすべきパターナリスティックな判断主体(皇帝を頂点とする徳の高い人々)の存在が人間社会において常に想定されているのに対し、イスラーム世界の場合は、論理的にいってそういう極限的「正しさ」を体現する人格が人間社会には想定しにくいので、非人格的な法の支配が優越するのではないだろうか。このように考えれば、「全体型」の発想のなかで形式合理的な法観念が発達することもあるといえよう。したがって、「全体型」「個別型」の区分は、形式合理的な法観念の存否とはほとんど関係がないといえる。
(4)こうしたことを論ずる理由は、近代西欧の歴史経験から導き出された「個別型=所有権観念の発達=個人主義=形式合理的な法観念」といったセットが往々にして一人歩きし、その対極にその裏返しとしての「全体型=所有権観念の未発達=集団主義=実質的正義論」といったセットを想定する二分法的な発想を生み出しているように思われるからである。こうしたセットを一度きちんと解体して、さまざまな組み合わせが可能であることを考えてみる必要がある。
何か(例えば土地)を所有する(自由に使用・収益・処分できる)ということは、必ずしも単一の所有者がそのすべての側面を完全な形で保持していなければならないということを意味しない。使用・収益はできるが処分は許されていないということもある。収益の一部を誰かに払うという約束つきで、その土地を自由に使用・収益し、かつその使用・収益の権利を処分できるということもある。論理的にいって、一つの土地に対する諸種権利の設定のしかたは無限に多様である。土地そのものに対する一元化された権利を絶対的な「物権」として考え、派生的「債権」と峻別する考え方は、歴史的に見ればむしろ特殊であろう。
ある権利を強化することは、他の権利を弱化することである。ここにおいて、所有の修辞はポジティブというよりはネガティブな意味で大きな役割を果たすことがある。
(1)ここではまず、多くの社会で見られる「理念的上級所有権」について考える。中国の王土思想などがその例である(ちなみに中国では「官田」などといって、政府所有の土地があるが、それは今日の国有地と同様、民間の所有権と同様のレベルで政府が土地を持っているということであって、ここでいうのは、民の所有する土地の上にかぶさっている王土観念をいう)。
こうした理念的な上級所有権は、国家が「自由に土地を利用・収益・処分する権利」というよりはむしろ、民間の土地所有に対する調整・規制を正当付けるというところに意味がある。旧い共同体的所有の遺制ではなく、私的所有の展開に伴う問題点の是正という機能をもつ。
①第一に、私的所有に対する全体的福祉の観念からの介入を正当化する。中国でいえば、歴史上しばしば見られる大土地所有制限論、土地売買規制論の背景には、こうした王土論がある。その意味では、こうした王土論は、私的土地所有の展開に伴って退潮するものではなく、むしろ私的土地所有の過度の展開と弊害が意識される局面で盛んに唱えられる。
②しかし、こうした理念的な上級所有権は、民間の土地流動を抑える方向にのみ機能するものではない。むしろ、民間の絶対的な所有権を排除することによって、却って多様でスムーズな土地利用権の流通を支えることもある。中国でもイスラーム世界でも、土地国有(王有)観念のもとで、農民の土地用益権の流通が、慣行的に盛んに行われていた。ここでいう用益は、所有権の下位にある権利ではない(土地王有論のもとでは、民間にそうした絶対的所有権者が存在しない)ため、用益権は所有権の掣肘を受けることなく、事実上の所有権として安定し、かつ必要に応じて多様に分割されて流通し得る(多様な権利の「物権化」)。イスラーム世界のワクフも、「(寄進されてワクフとなった商館は)建物全体の所有権は凍結されたまま、部分賃貸借権の売買を通して、その商業・経済的機能に対する長期的・短期的需給に弾力的に対応することができた」(加藤博1995)とあり、同様の機能をもっていたといえるかもしれない。
土地王有論は、王自身の権利という観点からみれば実際にはほとんど意味のないフィクショナルな議論と見ることもできるが、民間の絶対的な所有権を排除する論理という点では大きな意味をもっていたのである。近代の土地国有(公有)論と対比してみると、前掲①の方向が社会主義的な国有論と類似するのに対し、②の方向は、農業資本に対する地主的土地所有の制約を排除しようとするブルジョア的土地公有論(椎名重明編1978)と共通する論理を含んでおり、こうした理念的上級所有権のもつ意味が前近代の中国やイスラーム世界に限られたものでないことを感じさせる。
③以上のように、理念的上級所有権は、古代の不合理な遺制ではなく、私的土地所有のもつ問題点を解決するためのさまざまな洗練された仕組みを支える機能を果たしてきたといえよう。ただし、こうした機能が逆に、自由な経済活動を阻害したり(①)、経済の過度の流動化を招いたり(③)するとみなされる局面もあるわけで、そのときは、所有権の一元化が課題となってくる。近代物権概念の「絶対性」も、それが成立・導入されるそれぞれの歴史的背景のなかで考えなければならない。
(2)以上述べた土地に対する理念的上級所有権との対比で、他人の所有について考えてみたい。中国の場合、土地所有問題と人身所有問題とは、ある程度パラレルに考えることができる。王土王民思想によれば土地と人民は本来君主に属するものだが、民間で困窮した人々が土地を売ったりわが身や子供を売ったりすることは避けられない。したがって、政府としては、全体の福祉と秩序を勘案しつつ、放任と介入との間でバランスをとっていくことになる。総じて、土地に対する介入に比べ、人身所有に対する介入のほうが強いが、債務奴隷の存在を(事実上はもとより法的にも)認める時代も多い。そうした奴婢が「半人半物」的扱いになるのは、奴婢に対する主人の所有が絶対的なものでなく、「王民」の根っこがつながっているからであると考えられる。
それに対しイスラーム世界では、ムスリムの間での債務奴隷化は認められないという。神のものであるムスリムを人間が所有してはいけないということであろうか。異教徒であれば、いわば無主の地のごとく、所有してよいことになるのであろう。こうした中国やイスラーム世界における債務奴隷化制限志向は、人間の自己所有という考え方に基づくのではなく、むしろ自己を越えた「王」や「神」の所有にその理念的基礎をおいているといえよう。
したがって中国では、土地売買の放任傾向と人身売買の放任傾向とが、王土的規制の弛緩という方向で連動している。それに対し、近代ヨーロッパの場合は、土地に対する一元的・排他的所有権の確立(土地売買の自由化)と、自己所有観念の確立(人身売買の否定)とは、「個人の自立」の楯の両面をなしていた。
ただし、「自己所有」の観念を徹底すれば奴隷契約の自由(「自分が売りたいときに自分を売ってどこが悪い」)の議論も可能だろう(ノージック1996)。近年の「自己所有」をめぐる議論は、「王」や「神」とは言わないが、自己を越えた「なにものか」を志向しているように思われる(立岩真也1997の「他者性」など)。即ち、自らを超えたなにものかに規制されることなくして、人は自由であり得るのかということである。
(3)そのように考えてきたとき、「所有」という語のもつアイロニーに思い至る。人が自分自身をも含めて何物かを失わずにずっと持っていられるーー人と物との固着した関係を保てるーーのは、それを手放す自由がないこと、他者に束縛されていることと表裏一体である。「所有」という語を、処分権でなく、そうした人と物との具体的な固着にひきつけて考えたとき、「無所有の自由」が却って私的所有と商品経済に親和性をもつというパラドクスが生まれる(網野善彦1978)。日本史のなかでは、そのような「固着的所有」に大きな関心が払われてきた。徳政や「地起」の観念に見られる開墾者と土地との強い結びつき(勝俣鎮夫1979)や、近世の無年季的質地請戻し慣行の基礎にある小百姓的所持の観念(白川部達夫1994)などである。
こうした「固着的所有」観を中国と比較してみたとき、確かに中国でも前所有者の権利が売買後も残っていることがある。例えば找価(売値足し前請求)や回贖慣行(中国では年季がないのが普通)などである。しかし、中国の場合は、土地の「真の所有者」を決める基点(例えば開墾とか検地)が希薄であり、前所有者も「自分がその土地の唯一の真の所有者である」といったことを主張するわけではない。むしろ、売買の正当性が主に前所有者によって証される(そのほかの公証制度があまり発達していない)ために、前所有者のごり押しに対し買い手が弱い立場に置かれるということだと思う(岸本美緒1997)。
本来、「所有の対象」「所有の主体」の順に論じていこうと思ったが、「自己所有」などに触れているうちに混乱してしまった。以下は簡単に、所有の主体にかかわるその他の問題に触れたい。
アフリカ・北米・ニューギニアなどでインフォーマントから採取されたという「人間は土地を所有しているのでなく、土地(の霊)に所有されている」(杉島。アタリ1994より引用)といった観念の例が示すように、「神」や「(非常に抽象化された)王」を含め、所有の主体はさまざまに構成され得る。「土地」や「神」が実際に意志をもってその所有物を支配することは確認不可能なので、これは擬制に過ぎないともいえるが、要するに人は何をしてよくて何をしてはいけないかということの説明方法だと考えれば、実際的所有論と擬制的所有論との間に線を引くことは難しい。そうした方向を徹底すれば、所有の問題は、より大きな社会観の問題と融合する。所有の問題は、人と物の関係という形で表現された人と人の関係である。
例えば中国法制史研究上、家産は父のものか父子の共同所有かという問題をめぐって対立があったが、それは中国において父と子が別人格として観念されていなかった、という点から考えてみるべき問題である(滋賀秀三1967)。法的には「父のもの」といえるが、それは「息子たちのものではない」ということを意味するわけではなく、父の人格のなかに息子たちが融合していると考えられているのである。所有の主体の構成は千差万別であり、「人」の概念自体、「団体」の概念自体、さまざまである。このあたりは、議論をしようにも力及ばぬところであるので、ここでは断念する。
以上、全体の論旨は、所有観念のもつ多様な側面を可能な限り単純なパーツに分解し、ニュートラルな「比較」の俎上に載せてみようとするところにあった。これでそれぞれの地域の所有論の全体像がわかるかというと、そのようなことはないが、むしろ、パーツの組み合わせについての思い込みを解体し、さまざまな個性的組み合わせの可能性について考える糸口を作りたいと思った。人間社会のあり方は筆舌に尽くしがたい個性をもつが、個々のパーツについていえば、人間の考えることにはある程度の共通性(というか、多様性の限界)があるようにも思われる。そのあたりをうまく解きほぐして、硬い普遍的モデルでもなく硬い固定的類型論でもない、柔軟な理解をめざしたい。
本報告で扱ったのは、所有権の理念に関わる問題に過ぎないが、全体としては人間社会の秩序の組み立てを考える際の基層的な部分を扱ったつもりである。契約・市場・公正という問題群は、所有の問題と絡み合いながら、より立体的にその組み立てを考えていこうとするものである。専門家からごらんになればおかしなところも多々あると思うが、ご批判をいただければ幸いである。
引用文献
杉島敬志「土地・身体・文化の所有」同編『土地所有の政治史』風響社、1999
森村進『ロック所有論の再生』有斐閣、1997
加藤雅信『「所有権」の誕生』三省堂、2001
Huang, P.C.C., Civil Justice in China: Representation and Practice in the Qing, Stanford University Press, 1996.
寺田浩明「権利と冤抑」『法学』61-5、1997
岸本美緒「『租覈』の土地所有論」『中国ー社会と文化』1、1986
ライアン、アラン(森村進など訳)『所有』昭和堂、1993
加藤博『文明としてのイスラム』東京大学出版会、1995
椎名重明編『土地公有の史的研究』御茶の水書房、1978
ノージック、ロバート(嶋津格訳)『アナ―キー・国家・ユートピア』木鐸社、1996
立岩真也『私的所有論』勁草書房、1997
網野善彦『無縁・公界・楽』平凡社、1978
勝俣鎮夫『戦国法成立史論』東京大学出版会、1979
白川部達夫『日本近世の村と百姓的世界』校倉書房、1999
岸本美緒「明清時代の找価回贖問題」『中国―社会と文化』12号、1997
アタリ、ジャック(山内 訳)『所有の歴史』法政大学出版会、1994
滋賀秀三『中国家族法の原理』創文社、1967
関本照夫
まずはじめに人類学において市場がどんな視角で研究されてきたか、明らかにしておこう。それは新古典派経済学的な極度に抽象化された市場(しじょう)論ではなく、「市・いちば」や売買の場の研究、人々のあいだで展開される「やりとりtransaction」の実相の研究から始まる。(以下で「市場」と言うときには、人々のあいだの具体的なやりとりの場としての市、店舗、その他売買の場をさす。)とは言ってもそこにはマクロな研究とミクロな研究とがある。前者はSkinnerが中心地理論を用いて行ったヒエラキカルな中国地域市場圏論に代表される(Skinner 1964; 1965a; 1965b; Smith 1976)。ただしこの種の研究は地理学において広く採用されているもので、人類学では少数派と言えよう。数の上で圧倒的多数をしめる後者は売り手・買い手の行動、とくに両者間の持続的顧客関係、価格の交渉と決定、さらに情報探索一般を、特定の市場において集約的に研究し、何らかの一般化を試みるものである。論議は、まずそこで見いだされたものが新古典派経済学のモデルで説明できるのか、できないのかに向けられる。できないとしたらそれを、定価販売、商人と消費者の明確な区別、商品の規格化と製造者名・販売者名のブランド化、大量の広告、商品の種類・質・価格についての大量で誰もがアクセスできる情報などの存在によって特徴づけられる近代工業社会での売買と区別し、特有のバザ-ル経済の型としてモデル化していったり、新古典派モデル自体の欠陥の証左とする方向に議論が進む。
人類学には、婚姻交換(女性のやりとり)をふくむ贈与交換について古くから多くの蓄積がある。それで市場における売買を論ずる時にも贈与交換との関連において、あるいは対比において議論が進められることが多い。つまり人類学的市場論の大勢は交換と社会という議論の一部分として行われているのである。交換が社会を作り出すというのでもない、社会が交換の形を作り出すというのでもない、両者の相互作用を問題にしているのである。その点では、経済学者原洋之介が強調する個人利得の最大化動機以外の社会的制度・文化的信念といったものが(原 n.d.:3,5)、つねに重視される。
人類学の市場研究はまた内部に、かならずしも容易には調和し得ないふたつの志向を潜在させている。ひとつは個々の研究者が対面している土地の社会的・文化的個性を探ろうとするものであり、もうひとつは交換についての一般的洞察に寄与しようと言うものである。前者には固有の困難がつきまとう。土地といい、地域といい、社会といっても、それをどの範囲で捉え、どう区切るかは恣意的な「任意に切り取られた」というものにならざるを得ないからである。原は地域の個性を強調し「市場競争圧力だけを強調する普遍論理は、『世界システムに対する地域ごとの異なる反応』を説明できないのだ」という(原 1999:13)。この見解に多くの人類学者は賛同するに違いない。しかし原にしても「地域」をどのように「恣意的」でなく切り取ることができるかに回答を与えているわけではない。
ギアツのモロッコ、Sefrou市の地方中核市場の研究は(Geertz 1979)この小地域の歴史、政治、社会組織、文化的諸形式からアラビア語の意味論にまで詳細に言及し、地域の個性を探ろうとする点で、人類学的市場論の上記のふたつの志向の中の前者をもっとも良く追い求めたものである。だがその結論は情報ゲームという一般概念の洞察で終わっており、そこで彼が見いだしたもの、あるいはモデル化したものが、モロッコ一般、マグレブ一般、中東一般への考察に役に立つかも知れないと言う、慎重な付言にとどまっている。アレクサンダーの中部ジャワ地方小都市市場についての詳細で明快な研究は(Alexander 1987)、たとえば「資本」といった概念がけっして普遍的ではなく、文化特定的な意味を持つといったことにも十分配慮しながら、結論的にはバザール経済の価格決定モデルを提示することに終わっている。そしてジャワ人の企業、商業が植民地の権力と政治体制・言説制度の中でどのような制約を被っていたかという歴史的考察を、それとはまったく別に行っているのである(Alexander and Alexander 1991)。このことは、ひとつの地域というものをもっとも自然に与えてくれるのは政治支配体制だという常識的な、しかしそれのみに頼りすぎるなら地域というものを見る目を曇らせてもしかねないことがらを示唆している。
さて、地域ということで言うなら、アラブ・イスラム世界は世界でももっとも内部の均質性の高い、ひとつの地域として扱うことの容易な世界であろう。たとえば東南アジアを主語として、その全域に通用することとして語れることがらは、きわめて限定される。インドネシアを主語としても、事情はおなじことである。13万平方キロの面積をもち、内部に5ないし6の民族を擁するジャワ島についてもおなじことが言える。その最大の民族であるジャワ人に関してだけでも、少なくもその内部の3つの地域的区分を度外視して、一般的に語るのは容易ではない。中国を主語としてどれほどのことが語れるのか、内部の地域区分や時代区分をどのように考えたらよいのか、私には判断がつかない。これまで7回の研究会を通じ、中国研究の専門家が「中国では・・・」という語り方をすることが多かったことからして、中国を主語にして語ることは自然な考え方なのかも知れない。(ただし、第3回研究会報告の青木敦氏の「観戦記」参照。)市場を論ずるについて、アラブ・イスラム的な市場の類型、東南アジア的な市場の類型、中国的な市場の類型をそれぞれ提示し、その間の共通性と相違を全面的に論ずるといったことは、比較の論点を注意深く絞り込み十分な資料を集積しうるなら、何かの洞察を生むものになるかも知れないが、ここで私にできることではない。
一個の文化や文明をそれを代表する一個ないし複数の制度によって特徴づけようとするのは、もちろん正統的で広く行われる手続である。中国の文人官僚制、東南アジアの劇場国家やマンダラ的政体システム、インドのカースト制、そして中東のバザールなどを、たとえば挙げることができよう(Geertz 1979:123)。だが、これはつねに反論を招き、べつの特徴付けの方法を招き寄せる手続である。そして比較はおよそ容易ではない。以下では、3つの論点から市場と商業ということを考えてみたい。
市場はもの、サービスが貨幣を媒体として交換される場であり、情報の探索が基本的な役割を占める場であり、その主役は専業であるかどうかを問わぬ商人である。そこでは個人的な利得が、すべてを決定するのではないが、主導動機となる。利得を追求する個人としての商人の倫理的位置(moral status)のことを考えてみよう。アラブ・イスラム文明のもとで商人文化が花開いたこと、商業がその文明を担う代表的な存在のひとつであったこと、政治や法や宗教にわたる諸制度が商業を支えており、前近代のイスラム社会は市場社会としての性格を十分に備えていたことは、加藤氏によって明快に明らかにされている(加藤 1995;および第3回研究会における報告)(注1)。つまりそこには個人の利得追求をいかがわしいもの、「悪の根源」とする見方は存在しなかった。私は加藤氏の論から多くを学び啓発されるとともに、氏が、中東やイスラムにとかく無知である日本人の蒙を啓くための彼の地の実情紹介といった域を越えて、「自分のイスラム社会研究の足元をいま一度見直してみたいという欲求」(1995;15)から、イスラム社会の大きな総括をなそうとしているその姿勢に敬服するものである。
だが加藤氏はイスラム文明の独自性を強調するあまり、他の諸社会における商業と商人の位置をあまりに否定的に描いていないか。氏は、「世界の大宗教はおおむね商業・商人に否定的であるのに対して、イスラムという宗教は、商業、商人を肯定する点において際立っており・・・」(1995;18)と言う。また「前近代のキリスト教世界、日本の徳川時代など、商業という職業とそれを独立した生業としている商人という人間集団とに対し、否定的な態度をとる社会は歴史上多かった」と述べ、そこでは商業が「共同体倫理とは異質な、共同体を攪乱する要因として位置づけられていた」とし、「このような、商業を共同体の周辺あるいは外に位置づけるような社会にあっては、商業を生業とする人間集団である商人は共同体にとっての『異邦人』として恐れられるとともに、侮蔑と差別の対象となる。かくて、そこから生み出される文明が、商業と商人を高く評価するイスラム世界の文明と根本的に異質であることは、容易に想像がつく」と言う(同)。
アリストテレスからトマス・アクィナスと中世キリスト教会へ、そして残滓としては、近代西欧の労働価値説からマルクスにまでいたる、ヨーロッパでの使用価値と自給的所帯の賛美、商業利得の否定の思潮の流れに対しては、氏がイスラム文明を特徴づけるやり方は十分に有効であろう。だがもちろん世界はヨーロッパとアラブ世界だけから成っているのではない。
スペインによる征服以前のインカ帝国中核部のように、貨幣と市場をまったく知らず、ミクロな互酬とマクロな再分配だけで構成された文明もかって世界には存在した(Murra 1979)。この例が興味深いのはそのこと自体ではない。スペイン征服後のアンデス高地において、貨幣と市場を知らないインディオたちがほしいままにスペインの搾取にさらされたというかつての史観は、最近の研究によって批判されている。反対にインディオが、拡張する市場経済に対して、急速、大規模かつ成功裡に適応し、植民地支配という制約下に可能な範囲で、それを積極的にわがものとしていったことが明らかになっている(Harris, 1989, 239; 関)。徳川時代の日本において、商業と商人は恐れ、侮蔑、差別の対象だったろうか。恐れ、侮蔑、差別は「士農工商四民」の外におかれた人々にこそ向けられたのであり、商人に向けられたものではなかった。この時代にはむしろ商人文化が大いに開花したのではないか。もちろんその実態は、加藤氏の説くイスラム文明下の商人とは大いに異なったものだったろう。「商」は徴づけられたものであり、「農の自給経済、その上に立つ士・公儀」という理念とのあいだには微妙な緊張が存在した。だが「商」はたえず貶められていたわけではなく、「士農工商」が貴賎の序列だという観念は一部の儒者のものだったにすぎない。中世のヨーロッパは、トマス・アクィナスの論に代表されるように、物質的利得・商業利潤を否定視する観念がとりわけ強かったひとつの代表例であるが、そこでもすべてが自給経済と閉鎖的共同体の中に逼塞していたわけではなく、中世後期には都市と商業の発展が見られた。貪欲の罪は悪についての公式のイデオロギーから次第に消え去り、より社会にとって破壊的である野心、権力欲、肉欲の代替物として許容されるようになっていった(Hirschman 1977、Bloch and Parry 1989:19に引用)。インドにおいては、『マヌ法典』にはじまりその後のヒンドゥー思想にいたるまで、商業と商人を本来的な悪とする見方、さらには利子付きの金貸しを退ける見方は存在しない。北インドに「蛇とマルワリ(商人)に会ったらマルワリを殺せ」ということわざがある。だが、商人の強欲さは彼のjati dharma、つまりカーストにより定められた地位の一部であり、彼の本性である定まった行動の一部である。それについて道徳的に憤激するのは、サソリが刺すのに道徳的に憤激するのとおなじことだという(Parry 1989:78-79)。中国には、古くは商業を「賤」視する考え方があり、宋代くらいまでは、官僚の家では商業をしてはいけない、という規定があった。ただし、明・清時代には商人の地位が上昇し、「儒商」といわれるような学者商人も出てきたことは、余英時などの力説するところ(『中国近世の宗教倫理と商人精神』)だという(岸本美緒さんのご教示による)。
ここで言葉を換えて、個人の利得追求と全体としての社会の長期的生存というふたつの志向のあいだに、調和を見いだす見方と対立を見いだす見方というふたつの極を考えてみよう。前近代のイスラム文明は前者の極に一番近い文明の典型であろう。このことについて加藤氏の所論にはまったく異議はない。ただ商人を全面肯定する社会と全面否定する社会とに諸社会を分類できるわけではなく、どの社会においても程度の差はあれ、上記のふたつの見方のあいだにやりくりやしのぎ合いの関係があり、特定の時・所にある個別社会ではそれぞれ違う形で一時的均衡が成り立っていると私は考える。エジプトで時に見られたという食糧暴動、官による価格統制などもこのふたつの見方のあいだのしのぎ合いの結果ではなかろうか。ここで上記のふたつの極をつなぐ線分上のどこかに個々の社会が位置していると考えることは、われわれの比較史の試みにとって魅力的である。だが残念なことに特定の社会を線分上の特定の点に位置づけるべきインデックスをわれわれは持っていない。だからこの考え方は過剰な一般論、無限の相対主義に陥る危険がある。それゆえにこそ私は加藤氏によるイスラム文明の特徴付けを基本的に肯定する。だが、上記のふたつの極のあいだのせめぎ合いの結果として特定社会にある均衡が成り立っているという見方、ある社会がこの両極のいずれかにきわめて近寄って存在しているとしても、抑えられたもう一つの志向性は、やはり陰の対抗原理としてどこかに身を潜め、秘やかな形で社会を制約しているという見方は有益なものだと思う。
寺田浩明氏は明清期の中国を論じてA規範、B規範ということをいう(第7回研究会報告)。A規範は個体から出発してその持ち分を基礎づけるルール、「市場的ルール」で、社会生活の大半はそれを用いて営まれるという。B規範は全体的利益の観点から出発して個体に応分のものを割り振る仕方である。中国近世国家権力は天下の全人民を対象に基本的にB規範の上に立つという。岸本美緒さんは中国における「所有」の観念を論じて、「『全体』を論理的前提としつつ、いわばそこから流出した形で認められている『所有』。そこでは『所有権』は、それが個人のものであれ、君主のものであれ、全体社会に原理的に対抗するような形では主張され得ない。問題の建て方は、人々の売買行為を通じ事実的に展開する所有の『勢』と、それのもたらす社会的弊害とを勘案して、全体の福祉の観点から最適点を求めるには如何にすべきか、ということになる」と言い、「あらゆるプリンシプルに拘泥せず、随時随時、状況に応じてもっとも良い実質的効果を導き得るよう虚心に努力する正しい態度を、当時の人々は『中』と表現した」とも言う(第1回研究会報告)。この「中」は原理の論ではなくバランスの問題だという(岸本さんのご教示による)。これらのことも、文脈を変えれば、上記のふたつの極のあいだのしのぎ合いの結果生まれてくる現実を表現したものと考えて良いのか否か。それとも上記の対立軸自体を無効にする現実がそこにあるのか。残念ながら私には不明である。ただ中国の「徳」のある人々は、世の中を、この二つの極とその中間のいずれかにある折り合いの付く点という私が提示した見方と、同じ見方で見ていたのかもしれない。
私が上で述べた、個人の利得追求と全体としての社会の長期的生存というふたつの志向のあいだに、調和を見いだす見方と対立を見いだす見方というふたつの極という見方と、出発点で類似した観念が、人類学者ブロックとパリーによって提示されている。社会には短期・長期のふたつの「やりとり(交換)」の秩序が存在する。長期のものは、社会ないし宇宙の長期的な再生産にかかわっている。短期のものは個人間の競争の領域にかかわっている。彼らは多数の例を挙げているが、インドからのものでいうなら、商人、盗賊、王が正道をはずれたやり方で得た富(短期的やりとり)ですら、その一部が、長期の宇宙論的浄化サイクルの一部としてブラフマンに贈与されるならば(長期的やりとり)、なんら倫理上の問題を生じない(Bloch and Parry 1989:24-25)。さらに逆説的なことに、人々の罪の浄化のための贈り物を受け取るブラフマンは健康を害し、苦悶に満ちた不幸な死を遂げ、その一族は2,3代の内に死に絶えると信じられているに対し、強欲な商人、高利貸しが。その行為ゆえに不幸に見まわれるという信仰は存在しない(Parry 1989)。ブロックとパリーは全体社会的・宇宙論的なやりとりと短期的・個人的なやりとりとのあいだに連関と相補性、つまり調和のみを強調する。そこがふたつの志向性のあいだに調和を見るか対立を見るかという私の両極論と異なる点である。人類学者や社会学者は彼らの見解に機能主義の亡霊を見いだすであろう。
彼らの見方にならうならば、アラブ・イスラム社会の商業活動の利潤は(短期的やりとり)、ワクフに代表されるザカ-トとして全体社会的・宇宙論的な贈与のサイクルに入り、それがまたワクフで建設される商業施設などとして商業活動を栄えさせるということになる。だがはたして世の中の諸制度はそれほど予定調和的にぴったりとかみ合っているのだろうか。坂井信三氏は、植民地化以前の西スーダンにおける市場と政治権力を論ずる中で、定期市が小地域社会の「土地の精霊」を祀る首長=「土地の主」の儀礼的権威の下に組織され、小地域を越える越える政治的統合を作り出す王権とのあいだに構造的な断絶があったと指摘する(第4回研究会報告)。これと対称的な例はインドネシア、バリ島の19世紀に見いだされる。そこでは地域内のローカルな市場と対外交易とがはっきりと切り離され、後者は諸王たちがそれぞれ独占管理して、業務をヨーロッパ人を含む島外の異人たちに独占させていた(ギアツ)。バリ島はイスラム化の波が及ばなかった地域であるが、現在インドネシアと呼ばれる領域内のイスラム化した各地にも、かつて類似の例が多数見いだされた。
坂井氏は、19世紀の西スーダンにおいて一連のジハードにより各地にイスラム国家が成立したことを、上述の経済と政治の構造的断絶を乗り越えようとする運動だったと解釈している。その詳細や意味は不明であるが、「断絶を乗り越えようとする」という表現には疑問が残る。前近代におけるイスラムの強さは、一貫した原理によってすべてを体系的に統一することにあったのではなく、異質なものを異質なままに結びつけ、至る所にすき間や断層を残したままゆるやかにネットワークで結びつける点にあったのではないか。マレー半島から東南アジア島嶼部にまたがるイスラム圏は、各小地域の文化的・歴史的独自性からイスラムの浸透度、その実践の内容に至るまできわめてたがいに異質で多様な世界であった。イスラム的法制度が確立し実践されたとはとうてい言えず、法による統治ではなく人格による統治のゆるやかな連鎖が秩序を作り出していた。それでもなお、イスラムの名の下に広い地域ネットワークが有効に機能し、さらにインド洋や南シナ海をわたる海上交易路と各地域を結びつけるのにも、イスラムは有効に機能した。これはまさに異質なものを異質なままに結びつけていくイスラムの都市的・商業的性格の故であろう。
ギアツによるモロッコの市場都市Sefrouの研究(Geertz 1979)においても、19世紀以来イスラエルへの移住が本格化する時期まで、トランス・サハラの長距離交易においても、Sefrouを中心地とする地方市場圏においてもユダヤ人の活躍がきわめて大きかったことが指摘される。マスターズによるアレッポ商業の研究においても、すべての住民が区別なく商業にかかわる傾向の指摘とならんで、そのなかでもとくに非ムスリムの宗教的マイノリティーの役割が、とくにオスマン朝後期になるほど大きかったことが語られている (Masters 1988)。こうしたこともイスラムの何か一貫した原理がくまなく浸透していたことの結果としてより、商業の持っている本来的に文化横断的な性格と、異質なものを共存させるイスラムの特質によっていたのではないか。
今から振り返るなら、こうしたイスラムの開かれた性格が、異なる原理に立つヨーロッパ商業の浸透を許し、中規模な集権的重商主義国家、さらには内部のすき間のない均質性を志向する国民国家体制に、近代において敗北する要因となったと考えるのである。そして今、この均質的な国民国家という擬制が、全世界的規模で現代的問題となり、桎梏となっている。
岸本美緒さんは第2回研究会の報告・討論の記録の最後に「蛇足」と題して、「イスラーム社会研究者は、中国研究者と比較して、その秩序の安定さや健全さに懐疑や悲観を抱くことなく、概して強い自信をもっているように見受けられる」と述べ、「やはりイスラーム社会には、俗権力を越えて人々の行動を定言命令的に規制する『信仰』と、それに裏付けられた『法』があり、それが秩序に関する根底的な信頼を生み出しているということが実際にあるのかも知れない。・・・私は今まで、中国社会とイスラーム社会とは『似ている』という点に主に関心をもってきたが、今後は、どこが『違う』のか、ということを、原理的なレベルで考えてみたい」といっている。インドネシアのイスラム社会についていうなら、私はそこに「信仰」は見いだすが、「法」と「秩序に関する根底的な信頼」を見いだせない。そこではすべてが不確かで正しい情報を得るのは容易ではなく、自分をその一部として安心してしまう親族集団、企業、その他社会団体もあやふやなである。その中で人々は、縦横の対人関係の連鎖、それ自体も不確かである連鎖をできるだけ広く確保し、そこで不確かな情報をできるだけ多く収集しながら情報の値踏みをし、また相手・他者がどのような情報をどう読んでいるかを値踏みしながら、たえざる小さな賭をしている。リスクを避けるには、いろいろの小さな賭をし、どれかが外れても、またべつのものが当たることを期待する(関本 1986)。それでたいていは何とかなるし、だめならあきらめるという楽観主義で人々は生きている。市場社会というものは、明確な制度的秩序、きっちりと諸部分が結び合わされたシステムがなくとも存在しうるものだと、私は考えている。
さて、イスラム社会と一口に言っても、インドネシアとアラブ・イスラム社会とは大きく違うようだ。このことを私は、おそらくアラブ・イスラム社会ではやや辺境であるモロッコの例、ふたたびギアツが取り上げる事例から痛感した。Sefrouのスークには販売と製造の各職種ごとにaminと呼ばれる調停者が存在する。彼はそれぞれの職種の中の高名で信頼あつく、敬虔な信仰を持つ高齢者であり、その職種の同業者間、さらに業者と客との争いごとの調停を任される。彼はさらに争いごとが発展したとき、市場監督官muhtasebや法廷の裁判官qadiの前で、イスラム司法においてきわめて重要な証人の役割を果たすのである(Geertz 1979:192-194)。これを私は、ギアツが描いているのは1910-70頃の時期ではあるが、加藤氏が言うイスラム文明における「法による統治」(加藤 1995:132)の一例と理解する。そしてイスラム社会に信仰に裏付けられた法があり、それが秩序に関する根底的な信頼を生み出しているという岸本さんの直感は、少なくともアラブ社会、中東社会について正しいのであろう。残念ながらというべきか、インドネシアにはそのような具体的に目に見える形で日常生活の中にある「法」は見いだせない。そこでは市場における争いごとの明示的に制度化された調停や裁きはない。もちろん近代的世俗法の裁判所は存在するが、争いはインフォーマルに調停されるか、どちらかが泣き寝入りするか、不和が長引くかという形でしか「解決」されない。だがそこにもイスラムの信仰はあり、市場も存続するのである。
古田和子さんの第3回研究会における報告「中国における市場、仲介、情報」は原氏の主張などと軌を一にして、情報の不確かさ、確かな情報の得難さ、情報のコストという観点から市場を論ずる点で、大いに関心をそそられ共感するものであった。質問もかなりそれに集中していたように、仲介人の存在、仲介という概念にその要がある。そこで中国の諸事情や研究の蓄積に私がおよそ不案内であることを前提とした上で、この仲介人をめぐる疑問を提出する。古田さんは「市場は生き馬の目を抜く所であったが、危険と裏返しに儲けの可能性もまた存在した」という。だが、生糸を売る農民は「物の取引に必要な情報を持っている仲介人」を介して生糸を糸行に売り、仲介人に手数料を払った。市場の価格は「伸縮的価格である。しかし、その価格にはその鎮市における安定的な価格の幅というものがあり、仲介者はその幅がどのくらいのものであるかを知っている存在」である。「仲介者が持っている細かい情報・知識は、それを保有すること自体にコストがかかることを、農民は充分に理解していたようだ」という。ここでは仲介人の存在、取引費用・情報コストを理解している農民という枠組みによって、不確実性が除去され逓減され、市場に安定した秩序が生まれるという面のみが強調されてはいないか。市場の生き馬の目を抜くような性格、そこに大儲けも没落もあること、取引者相互間の駆け引きということ、相手を出し抜くということ、相手の持っていない情報を持っていることによって利益を得るということ、さらに相手がどのような情報を持ってどのように行動するかをより的確に予測しそれをも自分の持つ情報の一部として戦略を立てるということ、要するに市場のダイナミズムが見えないのである。
市場における情報の不確かさ、情報の偏在という特徴に対応して、市場参加者が不確定性の逓減、何らかの安定を求める行動に出る例は世界に広く見いだされる。だが不確定性の全くの除去、完全な安定はあり得ない。たとえば良く報告される特定の売買のペアの持続的顧客関係の持続ということは、必要な情報探索の努力の部分的軽減であるか、あるいは掛け売りをする村の豊かな商人と、そこで高くつけ買いするしかない貧しい村人といった貧富の上下関係の問題であろう。
19世紀末から20世紀前半の中国の地方市場は、シカゴの先物取引市場と違って、もっと安定し危険も大儲けの機会も乏しい場だということではあろう。たしかにスケールにおいてははるかに慎ましやかな場であろう。だが市場の一面である情報ゲームの結果として勝者も敗者もいる場だという性格において、両者に本質的な差はないのではないか。今日のジャワにおいて、市場参加者の圧倒的多数はひとつひとつの取引を、その取引量においても取引の及ぶ範囲においても小規模にし、小規模な取引をできるだけ多数維持することでリスクを分散し軽減しようという慎ましい参加者である。だがその中には、情報探索力、相手の出方を見る能力にとくに優れた者がいて、大きく成功する者、あえてリスクを冒して成功したり没落したりする者がいる(そうした人々は高い比率で華人であるというのがインドネシアの現実だが)。慎ましいリスク忌避者だけが集まっても市場は動かないのである。同時に慎ましい市場参加者にも小さいながら場が与えられ、そうした者が時に痛い目を見ることもあるが、大方は成功も没落もしないで細々とやっていける。そしてそうした小さな参加者多数の、個々には小さくとも総計すれば大きくなる取引も、市場の秩序の一部である。彼ら、彼女たちもまたささやかながら情報ゲームの参加者である。私は市場というものをこんな風に見ている。
注
(1)加藤氏は、市場が見いだされる社会一般と区別して「市場社会」を厳密な基準で定義づけようとしている(加藤 1997)。氏はある社会が市場社会であるか、いまだそうでは無いかの区別に関心を持つのだが、私の出発点には、互酬・再分配・市場が、実態としてはかならずしも相互に明確には区別できないものとして、折り重なりもつれ合っている状況への関心がある。たとえばジャワのほとんどの地域とスマトラのかなりの部分で市場経済が主導的力になったのは19世紀後半からであるというのが、インドネシア研究者の常識的見方であるが、今日インドネシアと呼ばれる地域のすべてのそうなったのはいつからだと問われれば、ここ30年ほどのことでしょうくらいにしか言えない。そしてそうではあっても古くからさまざまなスポット、さまざまな局面に市場はあり、市場原理は働いていたのである。近代の植民地体制によって市場原理が浸透した社会は、外部からゆがんだ形で押しつけられたものであって市場社会とは言えない、という論者もいるかもしれないが、私はそうした見方は取らない。また、第3回研究会の冒頭の提起で私が「ローカルな地域市場と資本主義」ということを言ったのも、ここに述べたような状況を念頭においてである。またおなじ研究会での報告で石川登氏は、1930年代のボルネオ島サラワクで国際市場と結びついたゴム栽培と取引が活発化していく中で、ある小さな地域社会がむしろ自給経済に退行していくという、興味深い例を提示している。
文献
Alexander, J.
1987 Trade, Traders and Trading in Rural Java. Singapore, Oxford University Press.
Alexander, J. and P. Alexander
1991 Protecting Peasants from Capitalism: The Subordination of Javanese Traders by the Colonial State. Comparative Studies in Society and History, 33
-2: 370-394.
Geertz, C.
1979 Suq: the Bazaar Economy in Sefrou. In C. Geertz, H. Geertz and L. Rosen, Meaning and Order in Moroccan Society: Three Essays in Cultural Anlysis, Cambridge University Press.
原洋之介
1999 『エリア・エコノミックス-アジア経済のトポロジー』NTT出版。
n.d. 「アジア経済の方法:反市場原理主義の知的基盤を求めて」草稿。
Harris, O.
1989 The Earth and the State: The Sources and Meanings of Money in Northern Potosi, Bolivia. In J. Parry and M. Bloch (1989).
Hirschman, A.O.
1977 The Passions and the Interest: Political Argument for Capitalism Before Its Triumph. Princeton University Press.
加藤博
1995 『文明としてのイスラム-多元的社会叙述の試み』東京大学出版会。
1997 「『市場社会』としてのイスラム社会」『社会経済史学』63-2:81-100。
Masters, B.
1988 The Origins of Western Economic Dominance in the Middle East: Mercantilism and the Islamic Economy in Aleppo, 1600-1750. New York University Press.
Murra, J.W.
1979 The Economic Organization of the Inca State. JAI Press.
Parry, J.
1989 On the Moral Perils of Exchange. In J. Parry and M. Bloch (1989)
Parry, J. and M. Bloch
1989 Money and the Morality of Exchange. Cambridge University Press.
関雄二
1999 「ワカを掘る先住民-植民地時代ペルーにおける資本主義の拡大と先住民の生存戦略」『民族學研究』64-2:178-198。
関本照夫
1986 「ジャワ農村経済への社会人類学的視点」板垣與一編『アジア研究の課題と方法』東洋経済新報社、pp.273-293.
Skinner, G.W.
1964, 1965a, 1965b Marketing and Social Structure in Rural China, Part I,II,III. Journal of Asian Studies 24: 3-43, 195-228, 363-399.(邦訳あり)
Smith, C.A. ed.
1976 Regional Analysis, Vol.1: Economic Systems. Academic Press.
三浦 徹(2001.12.13)
目的は、個々人を起点として、社会関係あるいは社会モデルを探るところにある。その理由は、10年前の重点領域研究「イスラムの都市性」プロジェクト(1988-90、研究代表者板垣雄三東京大学東洋文化研究所教授)およびこれに関連して編集した『イスラム都市研究』(東京大学出版会、1991)にさかのぼる。そこでは、制度に自治・自由の保障をもとめる西欧の自治都市論に対して、中東・イスラーム世界の都市や社会の流動性や柔構造が強調された(後藤明や、I.M.ラピダスなど)。私自身は、社会集団やその関係に着目したラピダスの方法と社会モデル(ネットワーク)にひかれながら、同時に、分析レヴェルが集団間の関係の留まっていること、集団の内部の規範やメンバーの意識が議論されていないこと、および社会経済条件が無視されていること、に不満を覚えた。本研究会の幹事である岸本氏は、ネットワークという方法やモデルが中国社会にも適応可能であることを了解したうえで、集団間の争いを律するメタ秩序がなにか、を問題として提起した(以上は、『イスラム都市研究』の終章、および三浦「イスラム都市研究を超えて」1999を参照)。
以上のような反省から、研究対象を個々人のレヴェルまで下げていくこと、を自分の研究課題として設定した。ここで私が飛びついたのは、イスラーム法廷で記録された法廷文書(資料としては、個々の契約を記帳した台帳)である。なぜなら、そこでは、15世紀から20世紀までの、さまざまな地域のイスラーム法廷(シャリーア法廷)における売買、賃貸借、相続、婚姻などの個々人の間の契約が、イスラーム法とその書式に則って、大量に記録されているからであった。
単に個人を出発点ということであれば、伝記資料を用いるという方法も考えられるが、契約文書に着目した第二の理由は、売買や賃貸借に代表されるように、物や権利の移転の取り決めであり、個々人の間の利害(より広義には経済)、それに対する意識や戦略が分析できるのではないか、という点である。
第三には、個人間の契約を文書化する、という行為は社会性をもち、当然のこととして、契約の履行(あるいは違反)、そこから起こる紛争や調停、といった問題を射程に入れることになる。つまりここで、人々の関係の土台となる法や秩序を議論することができる。
私が抽出したモデルはつぎのようなものであった。
(1 )法廷上の権利主体はすべて個人である(女性や未成年者を含む)。
(2 )個人間の権利関係は、文書契約によって結ばれ、法廷に登記される。
(3)権利の確認と契約の保障は、第三者の証言によって行われる。このため、証言する人間をもたない者は、権利関係から排除される。
(4)契約にあたっては、当事者個人の意思にもとづくこと、および公益に合致することが要件とされ、個々人の権利と公益の調整が図られる。
まとめていえば、「個人の権利(ハック)と公益という二つの理念を基礎にしながら、人間関係の連鎖によって、社会関係が運営される」。
以上のような社会モデルは、18-19世紀のダマスクスの小法廷の台帳をもとにしたものであり、地域や時代による差が当然ありうるが、イスラーム法にもとづくイスラーム法廷をもつ地域において(アラブ、トルコ、イラン、さらには、南アジア、東南アジア、西アフリカ)、比較可能なモデルと考えている。
以上のような手の内を明らかにしたうえで、契約をもとにした社会モデルを比較の観点から考察する際の座標軸を考えてみよう。私はここで、契約の主体が個人か団体か、そして、その結合原理が、形式的なものか人格的なものか、という二つの座標軸を設けたい。
X軸は、契約の主体がだれか、換言すれば、権利主体となりうるのはだれか、である。イスラーム法では、よく知られているように、所有権の権利主体は個人に限られ、家のような共同体あるいは会社のような法人組織の財産権は認められていない。これを端的に示すのは、相続であり、被相続人の財産は、相続権をもつ親族によって完全に分割され、不動産についても、持ち分を設定し共有して相続し、相続人がその持ち分を売却したり賃貸借することは原則としては妨げられていない。実際には細分化された家屋や農地を持ち分所有者全員が平等に利用することはできないわけで、その場合には、実際の利用者が、他の相続人の持ち分を購入したり賃貸借したりするが、親子、兄弟などの間柄でも、売買や賃貸借の契約が結ばれ、法廷で認証手続きをとっている。
これに対して、ヨーロッパでは、共同体や同業組合、会社に、自然人と同様の権利、とりわけ財産権を認めている。そして、会社組織とりわけ株式会社組織の有無が、ヨーロッパとイスラーム世界の資本蓄積、ひいては資本主義の発達の差となったとする議論がある。イスラーム法では、複数の人間による資本と労働の投資のため、法人にかわる組織として、協業partnershipの形を認め、実際に、船舶を用いた貿易投資から町の小さな工房まで、このような協業が行われ、ここでも契約が結ばれた。しかし、協業はあくまでも、期間をかぎった投資であり、期間がすぎれば精算され、運営の意思決定は特定の個人が握ることはなく、パートナーの意思によっていた。
ヨーロッパとイスラーム社会を両極とすれば、中国はその間にくるのであろうか。相続は、イスラーム法と同じく成員(兄弟)間の均分を原則とし、財産権についても個人名義とその連鎖が一般的であったようだ(官業来歴のしくみ、寺田浩明氏の報告参照)。しかし、ここでいう個人は、ヨーロッパ(近代法)でいうindividualともイスラーム法でいう個人とも異なる理念と実態をもっていた。前近代の中国における社会経済の単位は、同居共財の家であり、それは、「父祖から子孫に向けて流れる血・気を共有する人々(及び男子の配偶者)が一体として暮らす状態」として意識された。したがって、原則としては財産の均分やこれに基づく家産分割があり得るとしても、「ひとつの生命体には最初からひとつの心しか無い、一体であるからこそ誰か一人によって全面的に代表され得、またそれが正しく代表される限りにおいて、別の個別構成員の意志を顧慮する必要はな」い(寺田浩明「合意と斉心のあいだ」)。寺田氏は、郷村大でつくられる約(村の規約、盟約)において、リーダーによる主唱とそこに結集する人々による唱和によってつくられる「斉心」(内心の一致)も、このような家の一体性の延長において理解されるとする。つまり、ここでは、家長やリーダーの人格の一体化する形で団体・集団がつくられており、これに対比すれば、ヨーロッパ(近代)の法人組織は、法の主体としての個々人を前提とし、これらを括る上位の法人格を新たに創出する、二重の構造になっている。ヨーロッパでは、個人と団体の双方を形式的に個人とみなし、中国では、個人も団体も人格的に捉え、イスラーム社会では、団体を形式的に個人とみなすことはないということになる。東南アジア地域の交易に交わされた口頭や文書による契約の主体はどうであったのか?契約文書そのものが残りにくい状況ではあるが、主体が誰かよりも、二者が結ばれることに重きがおかれていたような印象をうける。
このような類型を想定したうえで、さらに団体については、その意思決定がどうやってなされるのか、が検討されなければならない。イスラーム世界や中国のように意思を個人にしか認めないのであれば簡単であるが、ヨーロッパの法人概念のような二重組織ではこれが大問題になり、株主総会や取締役会議という舞台が必要になる。また、イスラーム社会についても、団体が存在しないわけではなく、家・家族は基本的な社会単位であり、またスーフィー教団や同業組合が活動する。しかし、実態上は、家や教団が使用する財産も、形式的には個人の所有、管理に委ねられ、教団や宗教施設に寄進されたワクフ財源は、管財人が管理し、蓄財の手段ともなっていた。
もうひとつの軸(Y軸)として、契約の性格、なにによって契約が結ばれるのか?という点については、形式主義(形式を満たすこと)と人格主義(当事者や証人の無形の信頼など)を両極に設定した。後者については、人格を含めた実質性とよんでもよいかもしれない。
イスラーム法についていえば、極端な形式主義をとっている。まず、さまざまな契約の種類に応じて、書式が定まっており、物件や権利内容の同定において齟齬が生じないように、きわめて綿密細心な書式ができあがっていて、当事者が、いわば空欄に当該の契約に固有の情報(物件や価格など)を埋めるだけで契約文書ができあがる。最終的な契約内容は、証人の証言によって保証される。契約文書には裁判官(カーディー)の署名も付されるが、証人による保証が一義的であり、裁判官はそれを権威づける役割を果たす。証人の証言が第一であるという点では、一見、人格的な保証のようにもみえるが、ここでいう証人は当該契約内容についての知識や情報をもっている必要はなく、形式的な証人で事足りる。その意味では、形式主義に分類することができるだろう。また、偽証が頻発し、偽証とわかっていても形式を満たすかぎり有効とせざるをえなかったのは、このような形式主義の負の側面である。他方で、同席した町の名士などの名前が記録されていることは、形式を満たしたうえで、人格的な保証を加味する意図があったことを窺わせる。
ヨーロッパについては、同じような形式性を重んじながら、その担い手が国家・機関であった。中世イタリアの公証人は、イスラーム法世界の証人・公証人と類似した役割をもっており、教皇と都市コムーネの双方から任命・承認され、公と私の性格をあわせもったが、任意の個人としての保証とは異なり、徐々に官吏に移行した(徳橋曜氏の研究)。イスラーム世界の公証人もまたカーディーによる任命を必要としてはいたが、個人としての資格で行っていたことに相違をみることができる。中国では、「中人」とよばれる仲介者の存在が知られている。そこでは、形式的な証人ではなく、取引についての情報をもち、当事者(売り手と買い手)とを引き合わせるような実質的な仲介者であり、保証人であり(古田和子氏の報告)、人格性が重んじられる。
東南アジアでは、二つの側面が混在する。Andaya氏の報告によれば、地域内のローカルな取引や契約においては、親族関係kinshipが保証となり、アラブやペルシアなど外来の商人との取引では文書契約が用いられた。前者を人格的、後者を形式主義とみることができるだろう。
ここでどちらにも分類しがたいのが、神による保証である。イスラーム法廷でも、証言や宣誓は、「神にかけて」行われた。これは、当事者間の人格的な信頼関係とみるべきか、それとも形式的なせりふとみるべきか、議論の余地がある。
ここまで、契約の主体と結びつきについては、契約の内容(対象、相手)を度外視して表面的に論を進めてきた。しかし実際には、何を誰と契約するかによって、契約の形式も異なっていた。
第一には、口頭契約と文書契約の使い分けである。イスラーム法廷で扱われた契約の大多数は、不動産の移転(売買、賃貸借、ワクフを含む)、相続、債権債務、婚姻である。これらはいずれも、契約の効力が当事者のみならず、家族、親族、子孫などに関わり、永続性をもっている(債権債務は効力の範囲はより狭いが)。これに対し、動産の取引については、法廷で記帳されることはまれであり、おそらくは、口頭の契約ですまされていたと考えられる(Reilly報告参照)。
不動産契約についても、そのすべてが文書化され、法廷で記録されたかどうかについては疑問が残る。記録された契約の頻度や形式、時代や時期によって異なっているからである。文書化や法廷での記録には、公証人や書記などに支払う手数料が必要であり、経済不況のときには、文書化を控える動きがみられた。つまり、当事者は、契約内容、相手、外的状況に応じて、契約のやり方を選んでいたと考えられる。
第二の問題は、契約書の内容が、実際の取引の記録である、と考えてよいかどうか、である。イスラーム法廷文書については、近年この問題に関する関心が高まっており、形式的な仲介者、利子つき金融、形式的な賃貸借契約や訴訟など、イスラーム法の形式を踏みながら、それをすりぬけて利潤・利益追求が合法的に行われていたことが指摘され、法廷文書の内容は、現実の利害関係のそのままの写しではなく、これを形式的に処理したものと考えられるようになってきた。中国や日本などの契約文書ではどうなのだろうか?もし、このような傾向がイスラーム法廷文書にのみみられるとすれば、その原因は、極端な形式主義に由来するのかもしれない。
第三は使用される言語の問題である。文書契約が、見知らぬ相手の場合により以上に必要されたとすれば、両者が共通に理解できる言語で書かれたのか、それとも、理解できなくとも、証人や裁判官などによる保証能力に重点が置かれたのか。
いずれにしても、契約と文書化という行為を、目的に応じた戦略として捉えることによって、当事者の意思・意識を明らかにすることができる。
契約の履行を担保する力、いいかえれば、不履行の場合の制裁はどうのようになされるのか?また、紛争となったときの解決方法はなにか?現実には、多様な制裁と解決法があったわけだが、ここでは、座標軸として、制裁や判定の執行者が権力(団体)か個人(当事者)か、また、判定が一方的絶対的(判決型)か当事者の合意を前提とする調停型かという、二つの軸を設定してみよう。
イスラーム法世界では、民事契約や民事事件に関して、これを管轄するカーディー法廷は、強制的な執行力をほとんど欠いていた。債務者は債務を弁済するまで投獄される規定になっていたが、支払わなければそれまでである。執達吏とよばれる下僚が強制的な取り立てを行うこともあったが、これも手数料を必要とした。裁判は、きわめて形式的なルールによって運営され、証人の証言か当事者の宣誓によって、判決が決まり、裁判官自身が裁量を下す余地はほとんどなかった。このような形式主義が徹底していたため、法廷での裁判に持ち込まれた場合には容易に判決が予想され、同時に法廷がその判決を執行する強制力を欠いていたため、実際には、町の有力者・有識者のもとで調停や仲裁が行われ、多くの裁判はその形式的な確認を行う場となっていた、と考えられる。このような点からすれば、法廷という権力の力を借りながらも、基本的には、当事者間による解決、調停型に分類できるであろう。
中国清代の民事訴訟については、滋賀秀三氏をはじめ多数の研究があり論点の違いもあるが、「情理」にもとづき、当事者の合意によって成立するという点で調停型の解決法といえるであろう。しかし、イスラーム法世界では、きわめて形式的な準則ができあがっており、調停もまたこれに準拠して行われたのに対し、中国では、情理という目に見えない、裁判官の人格に依拠していたことは大きな違いかもしれない。と同時に、どちらも調停型であるがゆえに、個々人の権利は「ぶよぶよ」としたものにならざるをえず、秩序もまた、「ずるずる」とできあがることになる。
しかし、イスラーム法世界については、つぎの留保が必要である。調停における準則は、イスラーム法に限定されず、地域の慣習(アーダ)や君主の定めた行政法(カーヌーン、近代の制定法)もまた考慮された。東南アジアのマレー世界では、イスラーム法が導入され、イスラーム法廷が設置されていたはずであるが、それについてはほとんど研究がなく、むしろ現地の慣行(アダット)やオランダ植民地法・裁判所との併存関係が予想され、いずれにしても、特定の法や制度に一元化されず、地域や当事者や取引によって異なる原理・方法の併存が考えられる。これを含めて、法の多元的な構造を考慮する必要があるだろう。
第二は、いかに中国やイスラーム法の裁判官が調停型であるとしても、いずれも国家権力によって任命されており、国家権力はどのようにとらえられていたのか?西尾報告では、東南アジアのムラユ(マレー)世界の王権が、王と臣下の誓約として捉えられることで、王権の神聖性が弱まり臣下による掣肘の原理がともなった、ことが報告された(第2回研究会)。そもそも、イスラーム国家(ウンマ)は信徒の契約によって成立し、また中世の中東においても、神のもとでの君臣あるいは王と臣民のあいだの誓約が、統治のさまざまな節目で行われた。つまり、国家権力自体が契約によって成立し、絶対的な権威や構成をもっていなかった。裁判に喩えれば、調停型だったのである。
以上の契約の考察からは、中東・イスラーム地域では、個人主義的で形式主義的、という社会像がうかんでくる。しかし、個人も秩序も形式主義的、つまり空っぽな容れ物であるとすれば、サブスタンスはなにによってあたえられるのだろうか?生身の人間は各種の社会集団に所属しながらも、原理原則としては形式的な個人をベースとしなければならないところに、大きなジレンマと自由があるように思われる。
以上は、これまでの研究会での報告をもとにきわめてラフなスケッチを試みたものであり、誤解や理解不足もあると思われる。また、比較の座標軸も洗練された概念とは言い難く、私個人の思い入れに引きずられている。研究会の当日に厳しいご批判を頂戴したい。
参考文献抄
「比較史の可能性」研究会『活動の記録』1999年度、2000年度(残部はイスラーム地域研究第5班事務局にあります)
MIURA Toru ed, Ownership, Contracts and Markets in China, Southeast Asia and the Middle East: The Potentials of Comparative Study, IAS Proceedings Series, No.3, Tokyo, 2001.
Barbara Watson Andaya, “Orality, Contracts, Kinship and the Market in Pre-Colonial Island Southeast Asia,”, in Miura ed., op.cit.
Reilly, James, “Local and Regional Economics of Ottoman Syria during the Eighteenth and Nineteenth Centuries”, in Miura ed., op.cit.
寺田浩明「明清法秩序における「約」の性格」溝口雄三編『社会と国家』東京大学出版会、1994。同「合意と斉心の間」『明清時代史の基本問題』汲古書院、1999。
同「近代法秩序と清代民事法秩序:もう一つの近代法史論」『近代法の再定位』創文社、2001。
羽田正・三浦徹編『イスラム都市研究:歴史と展望』東京大学出版会、1991(同英語版、London, 1994).
三浦徹「イスラム都市研究を超えて」『創文』410、1999
同「カーディーと公証人:イスラム法世界における裁判と調停」『紛争と訴訟の文化史』青木書店,2000。
7