三本木さんがご病気のため、川島さんに代わりにお話しいただきました。

第18回コーヒーサロン
「コーヒーで取り組めるCSR」
(サステイナブル・コーヒー・シンポジウム
2009)
2009年10月17日(土)13:30~17:30
次回は 日本サステイナブルコーヒー協会 の主催になります。
場所は、東京大学(本郷) 経済学研究科棟 地下一階 第一教室 です。
お間違えのないように。
詳しくはこちらをご覧ください→
☆申込方法:E-mail
による事前申込
題名に「イベント申込(10 月17 日)」、本文に氏名・所属先・電話番号・E-mail アドレスを記して、info@suscaj.org
までE-mail
でお申込ください。
☆問合せ:
日本サステイナブルコーヒー協会
info@suscaj.org
http://www.suscaj.org/
第17回コーヒーサロン
フレンチプレス:コーヒーをおいしく飲むために

フレンチプレスを分解して説明する村山さん
ヨーロッパではフレンチプレスがコーヒー用であって、日本のように紅茶にはあまり使われていないというお話は意外でした。ボダム社お薦めのコーヒー1杯分にお湯120cc、4分抽出でとてもおいしく飲めました。

第16回コーヒーサロン

当日の様子
参加者は70名ほどになり大会議室が満席になるほどの盛況であった。
まず池本が挨拶として、焙煎のおもしろさについてラオスやベトナムでの焙煎の写真を見せながら説明した。ラオスの写真は鉄製で球体の焙煎機で、火力は薪をスライドさせることによって調整する。一方、ベトナムの写真は少数民族であるエデ族の女性が自家用にフライパンで焙煎している様子である。ベトナムのコーヒーの品質は良くないと言われるが、自分たちが飲む豆は丁寧に選別している。いずれの場合も30分も焙煎するので、かなりの深入りである。そこまでしないとおいしくはならないという事情を理解しておくべきだろう。自分で焙煎をすれば、コーヒー豆の良し悪しはよく分かる。
続いて、福島さんがコーヒーの焙煎の歴史について話された。コーヒーの発見から始まり、その後、世界各地に広がる過程で様々な焙煎道具が発明され、産業革命と同時に大型化・複雑化してく様子がよく分かる。燃料が木炭からコークス、ガスへと変わると同時に、焙煎機も一段と進歩していった。大型化・高速化することが、必ずしも味の良さにはつながらない。

講演の後、200グラムの豆が焙煎できる小型焙煎機を会議室に持ち込んで、焙煎の実演が行われた。


参加者から2名選ばれ、実際に焙煎を体験した。


焙煎のできあがり。
以上
第15回コーヒーサロンのご案内
ブラジル: 一つな国、多様な味
◇ 日時: 2009年5月21日(木)午後6時~8時
◇ 講演者:マルシア洋子下坂(Marcia Yoko Shimosaka)さん
◇ 講演内容
ブラジルは世界で5番目に広大な国土に1億9千万人の人々が住む国です。ブラジルのコーヒー生産量276万トンは世界の34.3%を占め、輸出量180万トンは世界の30.6%を占め、世界最大のコーヒー生産国であることはよく知られています。同時に100万トン近くを国内で消費する世界で主要なコーヒー消費国でもあります。一人当たり年間消費量は4.7Kgにのぼり、日本の3.2Kgを大きく上回っています。
今回のコーヒーサロンでは、数々のカッピングやバリスタの大会で審査員を努められるマルシア洋子下坂さんにブラジルという大きな国で飲まれるコーヒーの多様な味についてお話しいただきます。
また、カッピングも実演していただきます。
◇ 講演者紹介:ブラジル生まれ。カンピーナス大学法学部およびサンパウロ大学経営学部を卒業後、ブラジルのコーヒーの大家ホセ・ルイス・バルボサ氏に師事し、カッピングを学ぶ。現在、ブラジルのカッピングとバリスタの審査員を務める。

◇ 参加費: 無料
◇ 定員 40名(先着順)
◇ 申し込み:事前にEメールまたは電話で下記までお申し込みください。
E-mail: coffee.salon.ioc@gmail.com
または(電話)03-5841-5877(池本研究室)
◇ 場所: 東京大学 本郷キャンパス内 東洋文化研究所 3階 大会議室
◇ 主催:コーヒーサロン/東京大学 東洋文化研究所 池本研究室
第14回 コーヒーサロン
コーヒーと残留農薬
●第14回 コーヒーサロン
(終わりました)
コーヒーと残留農薬
◇ 日時: 2009年2月25日(水)午後7時~9時
◇ 報告者:石脇 智広 氏(石光商事株式会社 研究開発室長)

報告内容については樋口美枝子さんのブログをご覧ください。
http://cafehiguchi.blog55.fc2.com/
◇ 報告内容
食の安全性に対する不安は日に日に大きくなっています。なかでも残留農薬はマスメディアに採り上げられることも多く、特に関心の高い問題となっています。これまでコーヒーは不安の対象になるような作物ではありませんでしたが、昨年はエチオピア産コーヒーの農薬残留基準値越えが相次ぎ、一気に消費者の不安の目が向けられることとなりました。
農薬はこわいものといわれます。でも、もっとこわいのは私たちが農薬のことを知らないことです。うまく付き合っていくにはまず知ることから。それは相手が人でも農薬でも同じです。当日はコーヒーに残留した農薬のリスクについてお話します。安全と安心について一緒に考えてみましょう。そしてもう一つ。丹誠込めて作ったコーヒーを拒絶された生産国側のことも考えてみましょう。
◇ 報告者紹介:1969年鹿児島生まれ。東京大学大学院工学系研究科修了、博士(工学)。全日本コーヒー検定委員会コヒー鑑定士講師。著書に『コーヒー鑑定士検定教本』(共著)、『コーヒー検定教本』(主筆)、『コーヒー「こつ」の科学――コーヒーを正しく知るために』がある。
◇ 参加費: 無料
◇ 定員 70名(先着順)
◇ 申し込み:事前にEメールまたは電話で下記までお申し込みください。
E-mail: coffee.salon.ioc@gmail.com
または(電話)03-5841-5877(池本研究室)
◇ 場所: d-labo(ミッドタウン・タワー 7F)
都営大江戸線「六本木駅」8番出口より直結
◇ 主催:コーヒーサロン/東京大学 東洋文化研究所 池本研究室
コーヒーサロンのページは左の「研究会」からお入りください。
なお、、予告していた下記の講演は日を改めて開催する予定です。
「コーヒー『こつ』の科学:コーヒーを正しく知るために」
◇ 内容:2008年9月に『コーヒー「こつ」の科学:コーヒーを正しく知るために』(柴田書店 1800円)を出版された石脇智広さんにおいしいコーヒーの「こつ」についてお話いただきます。

第13回 コーヒーサロン(修了しました)
ケニアのコーヒーと紅茶:サステナブルな発展を目指して
◇ 日時: 2008年12月5日(金)14:00~17:15
ポスター

石光商事株式会社と日本紅茶協会のご協力により神戸で開催しました。
講師の方々を始め、ご協力いただいた多くの方々に御礼申し上げます。

ケニア共和国大使 デニス N.O.アウォリ 閣下

Good Inside オルティスリベラ美由紀 氏
 (株)ヒロコーヒー 山本
光弘 氏
(株)ヒロコーヒー 山本
光弘 氏

(株)セレクティー 聞谷 正人 氏

日本紅茶協会 シニア・ティーインストラクター 遠山幸子さん
第12回 コーヒーサロン
「ケニア・コーヒー/紅茶のサステイナビリティ」
(修了しました)
◇ 日時: 2008年10月9日(木)17:00~19:00
◇ 講演者:
1)「ビジネスと外交から見るケニアと日本」

在日ケニア共和国大使 デニス N.O.アウォリ 閣下
2)「ケニアにおけるサステナブル・コーヒー報告」

Good Inside 日本事務所代表 オルティスリベラ美由紀 氏
3)ケニア紅茶のチャイ(ロイヤルミルクティー)の実演

在日ケニア共和国大使館 フローレンス・スワ さん
4)「ケニアの紅茶のサステイナビリティー」

(株)セレクティー 聞谷 正人 氏
ケニアは、年間35万トンの茶を生産する世界第3位の一大生産国であり、輸出量では世界第1位を誇ります。また、コーヒーも、1893年から1世紀以上にわたり栽培されてきたという古い伝統を持っています。今回のコーヒーサロンでは、トヨタ・ケニア総支配人、トヨタ東アフリカ総支配人としての実績を買われて、駐日大使として着任したアウォリ大使に、ビジネスと外交の視点からこれまでの、そして今後の両国の関係を話していただきます。
サステナブル・コーヒーの認証機関である「グッドインサイド(Good Inside)」のオルティスリベラ・美由紀さんには、ケニアにおけるサステナブル・コーヒーの実際の取り組みについてご報告いただきます。そして、ケニアに長く滞在しておられた(株)セレクティーの聞谷正人さんにはケニア紅茶の特徴や栽培の様子について現地体験を踏まえてご紹介いただきます。
また、大使館の現地採用職員のFlorence Suwa さんには、ケニア紅茶のチャイ(ロイヤルミルクティー)の作り方を実演していただきます。また、ケニア・コーヒー/紅茶と特産品のナッツなどもご用意します。
どうぞ、お気軽にお越しください。
◇ 関係URL
在日ケニア共和国大使館ホームページ
Good Inside
(株)セレクティー
◇ 参加費: 無料(事前の申し込みは必要ありません)
◇ 場所: 東京大学東洋文化研究所 3階 大会議室
■問合せ先: 東京大学東洋文化研究所 池本研究室
電話: 03-5841-5877
E-mail: coffee.salon.ioc@gmail.com
第11回 コーヒーサロン
コーヒーハンター
サステイナブル・コーヒーを求めて

講演する川島氏
◇ 日時: 2008年7月9日(水) 18:30~20:30
◇ 講演者: 川島Jose 良彰 氏(日本サステイナブル コーヒー協会理事長)
(日本サステイナブル コーヒー協会については http://www.suscaj.org/)
◇ 参加費: 無料
◇ 場所: 東京大学東洋文化研究所 3階大会議室
川島氏は1956年生まれ。高校卒業後、コーヒーを勉強するために単身エルサルバドルに渡る。しかし、やがてエルサルバドルは泥沼の内戦に突入し、多くの人々が殺され、コーヒー農園が荒れていくのを目撃する。その後、ジャマイカのブルーマウンテンや、インドネシアのマンデリン・コーヒーの開発に従事。レユニオン(ブルボン)島ではブルボン・ポワントウの復活に成功するなど、コーヒーを通した国際協力の分野でも活躍。一方、コーヒー価格の暴落に喜び、生産者の苦しい状況を考えようともしない消費国のあり方に疑問を抱き、日本サステイナブル コーヒー協会を設立。持続可能なコーヒーの普及に努める。
今回のコーヒーサロンでは、『コーヒーハンター』の出版に合わせて、コーヒーからサステイナビリティ(持続可能性)に辿り着いた経緯をお話いただきます。
■川島良彰 著『コーヒーハンター 幻のブルボン ポワントウ復活』平凡社
インド洋に浮かぶレユニオン島で起きた突然変異が、たぐいまれな香りと品質を持つ幻のコーヒー『ブルボン ポワントウ』を生み出した。世界中をめぐってコーヒーづくりに携わった日本人の矜持と情熱により、絶滅の淵から救われたコーヒーの再生と復活の物語。それは、政治に翻弄され世界の表舞台から忘れ去られたレユニオン島民を巻き込んで、コーヒー産業復興に挑んだ『サステイナブル コーヒー』のあり方を考えさせるコーヒー環境論でもある。
■問合せ先: 東京大学東洋文化研究所 池本研究室
電話: 03-5841-5877
E-mail: coffee.salon.ioc@gmail.com
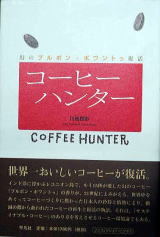
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
第10回コーヒーサロンのご案内
『The 80 years of Coffee Partnership & Sustainability』
コロンビアコーヒーの80年にわたるパートナーシップとサステナビリティ~
80年前コロンビアのコーヒー生産地メデジンで、生産者達が集まって結成した組合が、現在ではコロンビア国立コーヒー生産者連合会(FNC)となって、活発な活動を続けています。東京にも事務所を構え本国から派遣された駐在員が、コロンビア・コーヒーの普及に努めています。
FNCは、国内でサステイナブル・コーヒーに積極的に取り組んでいます。
今回の コーヒーサロンでは、FNCのコーヒーやコーヒーキャンディと共にアジア・太平洋事務所長のゴメスさんのご講演をお楽しみください。
========
第10回 コーヒーサロン
『The 80 years of Coffee Partnership & Sustainability』
◇日時:2008年1月10日(木) 18:00~20:00
◇内容
・講演:コロンビア国立コーヒー生産者連合会(FNC)
アジア・太平洋事務所長 ルイス・ゴメス氏
・コーヒーのおもてなし
◇費用:無料
◇場所:東京大学工学部8号館7階736号室
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
コンサベーション・コーヒーに関するセミナー
「第9回コーヒーサロン」のご案内
:7月18日(水)東京大学にて
毎日飲んでいるコーヒーの、色や香り、味以外のことを考えたことはありますか?
今飲んでいるコーヒーが、どこからやって来たのか・・・
どんな環境で、どんな人たちが作っているのか・・・
コーヒーの背景に目を向けると、そこからいろいろなことが見えてきます。
世界のコーヒー生産地の多くは、実は、「生物多様性ホットスポット」と重なります。CIのコンサベーション・コーヒー・プログラムでは、生物多様性ホットスポット内のコミュニティとともに、環境に配慮した生育方法によるコーヒー栽培に取り組んでいます。今回のセミナーでは、CIのスタッフが「コンサベーション・コーヒー」の取り組み事例をご紹介します。
-第9回 コーヒーサロン-
『コンサベーション・コーヒー:コーヒー生産地の生物多様性保全と生計向上を目指す』
◇日時:2007年7月18日(水)19:00~21:00
◇内容:
・講演:コンサベーション・インターナショナル 日比保史、山下加夏
・CIの取り組みのDVD上映-コロンビアより
・コーヒーのおもてなし
◇費用:無料
◇場所:東京大学工学部8号館7階736号室
***********************************************
コンサベーション・インターナショナル(CI)
TEL03-6911-6640
E-mail:ci-japan@conservation.org
http://www.conservation.or.jp
***********************************************
コンサベーション・インターナショナル(CI)は、自然生態系と人とのかかわりを重視
して環境問題を解決することを目的に設立された民間非営利の国際組織(NGO)です。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
◆
第8回コーヒーサロンのお知らせ◆
上智大学ポルトガル・ブラジル研究センターでは、来たる2007年1月26日(金)に第8回コーヒーサロンを開催いたします。ご興味ある方は、是非ご参加ください。参加費は無料です。
タイトル: コーヒー生産地の歴史と今 ~ブラジル編~
第一部 「コーヒー大国ブラジルと日本移民」
講演者:三田千代子(上智大学ポルトガル・ブラジル研究センター長兼外国学部教授)
講演内容:
現在、日本にポルトガル語話者が27万人もいるのをご存知ですか。ポルトガル語はブラジルの言語です。そう、日本で生活している日系ブラジル人の数です。では、なぜ日系人がこんなに多数ブラジルにいたのでしょうか。100年前に、ハワイ移民に代わりブラジルのサンパウロ向け日本移民が始まりました。以来1978年まで、第二次大戦前後の数年を除いて、25万人の日本人がブラジルに移民として渡りました。その子孫は現在、150万人と推定されています。
サンパウロ州のコーヒー農園の労働者として蓄財を目的に、ブラジルに渡った日本移民の当時の生活とその後の日本移民の歴史をテレビドラマ「ハルとナツ」のDVDを観賞しながら紹介し、日本で は決して経験したことのなかった未知のコーヒー栽培に挑んでいった日本人のチャレンジ精神を紹介したいと思います。
第二部 「コーヒー大国ブラジルのスペシャルティーコーヒーへの挑戦」
講演者:長谷川 勝彦(日東珈琲株式会社・株式会社カフェーパウリスタ代表取締役社長)
講演内容:
近年ブラジルで、数々の技術革新によって、品質の向上したコーヒーが生み出されています。私が目撃したここ10年の、ブラジルコーヒーの品質面の変化をレポートします。
日時:2007年1月26日(金)、18時〜20時
場所:上智大学中央図書館8階812号室
対象:一般の方
参加費:無料
問い合わせ先:上智大学ポルトガル・ブラジル研究センター
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
第7回コーヒーサロン
(上智大学ポルトガル・ブラジル研究センターセミナー)
タイトル:コーヒー生産地の歴史と今㈰:ハワイ島コナ編
講演内容:
第一部 「日系移民から見たコナコーヒーの歴史」
発表者:飯島真里子(上智大学非常勤講師)
第二部 「コナコーヒー開発に従事して」
発表者:川島良彰(UCC執行役員農事調査室室長)
日時:2006年10月13日(金)、18時~20時
場所:上智大学中央図書館8階812号室
対象:一般の方
参加費:無料
問い合わせ先:上智大学ポルトガル・ブラジル研究センター
第6回 コーヒーサロン
「コーヒーとバイオの世界」
日時:2006年7月11日(火) 18~20時
場所:経済学研究科棟 第2教室
報告者:安田武司教授 (神戸大学名誉教授、大手前栄養学院教授)
第6回 コーヒーサロン
コーヒーとバイオの世界
本研究会「コーヒーサロン」は、過去5回にわたって、コーヒーをめぐる様々なトピックを扱ってきました。
これまでの社会科学的な視点から一転、今回は自然科学の切り口から講演会を開催します。
コーヒー、カカオ、イネ等について永年にわたり研究してきた神戸大学農学部・熱帯有用植物学研究室の安田武司名誉教授をお招きし、コーヒーの植物学、栽培の歴史、組織培養、人工種子等について発表していただきます。
コーヒーを普段とは一味違った「バイオ」の世界から覗いてみませんか?
一般の方にも分りやすい発表ですのでぜひお気軽にお越しください。
無料でコーヒーもおもてなし致します。
■日時:2006年7月11日(火)18時~20時
■場所:東京大学 本郷キャンパス内
経済学研究科棟 第2教室
■内容:
◇発表者:安田武司
(神戸大学名誉教授、大手前栄養学院・教授)
◇テーマ
コーヒーの植物学、栽培の歴史、組織培養、人工種子などについて
◇質疑応答
◇コーヒーの無料試飲会
~~どうぞお気軽にお越しください。~~~~~~~
■ 問合せ先
東京大学東洋文化研究所 池本研究室 担当:大城
〒113-0033 文京区本郷7-3-1
Tel. 03-5841-5877/Fax: 03-5841-5899
coffee_salon_ioc@yahoo.co.jp
第5回 コーヒーサロン
「Women in Coffee Leadership ~コーヒー産業と女性のリーダーシップ~」 (終了)
Women in Coffee Leadership Programは、Coffee Quality Institute(CQI)がUSAID(米国国際開発庁)の支援を受けて行なっているもので、中央アメリカと北アメリカでコーヒー産業に関わる様々な分野の第一線で活躍する著名な女性たちを対象とし、そのリーダーシップとスキルを高め、人的ネットワークを構築することを目的としています。このプログラムに参加している女性たちの職業は、生産・流通・販売企業の経営者やNPO団体の代表などです。
詳しくは、
http://www.coffeeinstitute.org/other_women_in_coffee.aspをご覧ください。
このプログラムに参加する女性たちが来日するのを機に、女性の視点から見た中央アメリカコーヒー産業と北米市場の最新事情について話していただきます。
どなたでも参加できます。 どうぞ、お気軽にお越しください。

■日時:2006年5月10日(水)18時~20時
■場所:東京大学 本郷キャンパス内 山上会館 大会議室
■内容:
◇講演
・Margaret
Swallow(アメリカ CQI専務理事)、
「Women in Coffee Leadership Programについて」
・Lorena Calvo (グアテマラ、Finca Bohemia農園主)
「生産者から自ら率先する女性のエンパワーメント」
・Dania Alvarez (ニカラグア、CISA Exportadora社長)
「輸出業から支援する社会プログラム」
・Trish Skeie (アメリカ、ZOKAコーヒー 取締役)
「欧米のロースターの取り組み」
・Ruth
Elizondo (ニカラグア、Casa del Cafe S.A.代表)
「コーヒー・ショップから教育を考える」
(発表は英語で行なわれます。発表者は都合により変更になることがあります。)
◇質疑応答
◇コーヒーの試飲会(無料)
■発表者紹介
・Margaret Swallow
…2002年からCQIで専務理事として働き、Coffee
Corps(専門家ボランティア派遣)、Q-Auction(ネット・オークション)といったプログラムにおいてリーダーシップを発揮し、生産者の観点からの支援実現に取り組んでいる。
・Lorena Calvo
…グアテマラにて環境保全に貢献する生物学者で、野生生物保護のためにプロジェクト・マネージャー、自身のNGO運営に長年関わってきた。子供たちへの環境教育の専門家でもある。
・Dania Alvarez
…コーヒー産業やそのステークホルダーのSustainabilityへの貢献を使命とするMCGグループの輸出会社CISAの社長をつとめる。“Adopt
a School”という学校支援プロジェクトを開発し、教育環境整備から子供たちを支援している。
・Trish Skeie
…最高品質のコーヒーを提供することで有名なシアトルのZOKAコーヒー。
その取締役の彼女は自身最高のロースターの一人であり、焙煎業者の視点からスペシャルティ・コーヒーの専門家ボランティアとしてもプログラムに関わっている。
・Ruth
Elizondo
…ニカラグア初のコーヒーショップを開き、同国では最も成功したビジネスウーマンとして知られている。その他にも、心理学者、ダウン症児の母、障害児教育支援のNPO代表、農園主、などの顔を合わせ持ち、国の教育政策にも関わっている。
■ 問合せ先
東京大学東洋文化研究所 池本研究室 担当:大城
〒113-0033 文京区本郷7-3-1
Tel. 03-5841-5877/Fax: 03-5841-5899
coffee_salon_ioc@yahoo.co.jp
第4回 コーヒーサロン
「エチオピア・コーヒー:コーヒー発祥の国」 (終了)
講演:コアング・トゥトゥラム・ドゥング博士 (エチオピア大使)
コーヒー・セレモニーの実演 by エチオピア大使館 コーヒーマスター
日時:2006年2月22日(水)18時~20時
場所:東京大学東洋文化研究所 大会議室(3階)
コーヒー発祥の国エチオピア連邦民主共和国の
Dr.コアング大使にコーヒーの起源から現在に至るまでをご講演いただきます。
また、エチオピア大使館のコーヒーマスターにはエチオピアのコーヒー・セレモニーを実演していただきます。
どなたでも参加できます。
参加費 無料 コーヒー付(セレモニーの試飲には限りがあります。)
連絡先:東京大学 東洋文化研究所 池本幸生 Tel.
03-5841-5877
ポスターは
http://avatoli.ioc.u-tokyo.ac.jp/~ikemoto/ethiopia.jpg をご覧ください。
第3回 コーヒーサロン
地域をつなぐ:なぜ地域研究者が東ティモールのコーヒーを売り歩いているのか
(終了)
下記の通り東文研セミナーを開催します。コーヒーに関心のある方、東チモールに関心のある方、環境と開発に関心のある方、東チモールのコーヒーを飲んでみたい方、その他、さまざまな関心を持つ人が東チモールのコーヒーを飲みながら一緒に考えてみませんか。どなたでも参加できます。
記
日時:2005年12月7日(水)18時~20時
場所:東京大学東洋文化研究所 大会議室(3階)
報告者:阿部健一 助教授(国立民族学博物館・地域研究企画交流センター)
報告の趣旨:
東ティモールは、2002年にようやく念願の独立を果たす。世界中が今世紀最初の国の誕生を祝ったが、人口80万人の山がちの小国は、食糧の自給もままならない世界の最貧国でもある。唯一、資源といえるのはコーヒー。国民の4分の1が、収入のほとんどをコーヒーに頼っている。
コーヒーは、農薬も化学肥料も使わず、除草も剪定も行わず、庇陰樹の下で天然に近い状態で「栽培」されている。そのため収量は低いが、幸運なことに品質は高い。標高1000以上の高地で育つ東ティモールのコーヒーの潜在的品質は、ブルーマウンテンにも匹敵すると言われている。しかし、これまでは市場が限られていたこともあり、品質管理へのインセンティヴは低く、収穫後の処理も不十分なまま、きわめて安い価格で買い上げられてきた。
今回は、収穫後の処理を指導することで高い品質の豆を生産し、高価格で買い上げようとする試みを紹介したい。東ティモールのコーヒーは、単に味が良いだけでない。貧しくて購入できなかっただけなのだが、結果として無農薬栽培である。また、草地に庇陰樹を植えて、10年ほど木が大きくなってからコーヒーを植裁する。昔ながらの植え付け方法は、「環境保全的な栽培」でもある。
この東ティモールのコーヒーを実際に味わってもらいながら、さらに話を続けたいのは、地域を「つなぐ」ということについてである。地球上のさまざまな地域の相互依存関係が、いびつかつ短絡的に強まっているのが現代世界である。こうしたなか、外部者として他地域のことをもっともよく理解している[はずの]地域研究者は、地域と地域を「正しく」つなぐ「媒介者」の役割を果たすことができるのでないか。東ティモールのコーヒーをとりあげ、生産地と消費地を「正しく」結ぶ(mediation)ということを考えてみたい。 (阿部健一)
連絡先:東京大学 東洋文化研究所 池本幸生 Tel.
03-5841-5877
第2回コーヒーサロン
「熱帯雨林をどう守るか:
持続可能なコーヒー栽培のための認証制度について考える」 (終了)
コーヒー生産者はその国際価格の低迷によって、深刻な貧困に喘いでいます。一方、低価格のコーヒーで恩恵を受けている私たち先進国の消費者は、生産者の生活を配慮した商品を買うことにより、コーヒー農民を支援することができます。
今回取り上げる「レインフォレスト・アライアンス」(Rainforest
Alliance:以下RA)は生産者の生活向上とともに熱帯雨林の持続可能な管理を目指して、森林/河川の保護、農薬の制限や廃棄物の管理、農民やコーヒー農園で働く労働者の生活向上や、子どもたちの教育/医療の保障などの基準を満たす農園に対して認証を与えています。
すでにRAのトレードマークの《カエル》が付いたコーヒーをご覧になった方も多いと思います。先進国の消費者は、このマークのついたコーヒーを買うことによって生産国の熱帯雨林の保護にも貢献することになります。RAの活動は、コーヒーばかりでなく、バナナやオレンジ等の果物、チョコレートのような第二次産品、林業からはギターや鉛筆、自然保護のエコツーリズムまでカバーしています。
レインフォレストのサブリナさんに、RAがどのような活動を行なっているかを紹介していただき、そのRA認証のコーヒーを試飲しながら、持続可能性とは何か、消費者の行動はどうあるべきかなどについて参加者のみなさんと一緒に議論してみたいと考えています。
コーヒーに関心のある方、熱帯雨林に関心のある方、持続可能な地球環境保全に関心のある方、途上国の貧困問題に関心のある方など、様々な関心をもつ方々の参加を歓迎いたします。どうぞ、お気軽にお越しください。
レインフォレスト・アライアンス(Rainforest
Alliance)とは熱帯雨林の保護を目的に1987年に設立された国際的NPOです。詳しくは
http://www.rainforest-alliance.jp/ をご覧ください。
プログラム
18:00-19:00 講演
「レインフォレストの認証制度について」
サブリナ・ビジランティ(RA)
19:00-19:30 レインフォレスト・コーヒー試飲
19:30-20:00 質疑応答
日時: 6月6日(月)午後6時~8時
場所: 東京大学
東洋文化研究所 3階 大会議室
費用: 無料
問合せ先: 東京大学東洋文化研究所 池本研究室 担当:大城
Tel.
03-5841-5877
第1回コーヒーサロン
「アメリカのコーヒー生産国への支援とサステーナブルコーヒーの今後」(終了)
ゲストスピーカーとテーマは次の方々です。
1. Ted
Lingle (Specialty Coffee Association of America
専務理事)
「世界のコーヒー市場の動きについて」
2. Charles Overbeck (USAID
グアテマラ代表)
「USAIDのコーヒー生産国への支援策」
3. C. Franquemont (Coffee Quality
Institute 理事)
4. Gerry Larue (Coffee Quality Institute
中米担当)
「Qグレードについて」
5.
Ricardo
Espitia (エルサルバドルコーヒー協会会長)
「Qグレードへの期待」
日時と場所は次の通りです。
日時:2005年3月10日(木)18:00~20:00
場所:東京大学 東洋文化研究所 3階 第1会議室
ご不明な点は池本までお問合せください。
池本幸生
東京大学 東洋文化研究所 教授
Tel.
03-5841-5877 Fax. 03-5841-5899