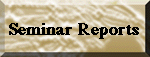
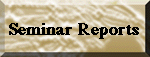
(※報告責任者:赤堀雅幸(上智大学))
日時:1999年2月25-26日
場所:上智大学9号館252号室
2月25日
セッション1(10:15 - 12:00)
赤堀雅幸(上智大学)
"Ziyara and Saint Veneration among the Bedouins in the Western Desert of Egypt"
司会:和崎春日(日本女子大学)
コメント1:大坪玲子(東京大学大学院)
コメント2:子島進(総合研究大学院大学大学院)
発表者の調査するエジプト西部砂漠において、一般に聖者廟へのズィヤーラが女性の行う行為であるとされることを出発点として、この地域におけるジェンダー観の分析を通して、聖者信仰が公的に男性と結びつけられるのとは別個に、価値を認められるいわば非公式の価値体系のなかにとらえられることを論じた。コメンテータからはそれぞれの専門を生かした民族誌的事実に関する指摘の他、近代化プロセスとの関わりの中に発表者の議論をとらえなおす可能性などが指摘された。また、個人的なズィヤーラと集団的なズィヤーラの対比が重要な観点となることがフロアから指摘された。
セッション2(13:30 - 15:15)
アブドゥッラフマーン・ラクサースィー(モロッコ・ムハンマド5世大学)
"Ziyara to a Pilgrimage Center in South Western Morocco"
司会:羽田正(東京大学東洋文化研究所)
コメント1:宇野昌樹(東京外国語大学)
コメント2:佐島隆(大阪国際女子大学)
モロッコにおけるスィディ・フマド・ウ・ムーサ廟へのズィヤーラが、祝祭的雰囲気をもって実践され、そこが巡礼センターとして昨日している様子が、ビデオなどの資料を併用して紹介された。また、このズィヤーラがハッジを祖型とした構成がなされていることが指摘され、ズィヤーラとハッジのもつ関係性について興味深い指摘がなされた。コメンテータからは、それぞれが専門とするドゥルーズやトルコにおけるズィヤーラ慣行が対比的に紹介され、またズィヤーラを構成する諸要素のもつ象徴的意味合いについて議論が行われた。
セッション3(15:45 - 17:30)
佐藤規子(カーイデ・アザム大学)
"The Shi'i Women's Practices of 'Ziyarat' and 'Nadhr' in Quetta, Pakistan"
司会:宮治美江子(東京国際大学)
コメント1:森本一夫(東京大学東洋文化研究所)
コメント2:村山和之(和光大学)
パキスタンのクエッタにおけるシーア派女性を中心としたズィヤーラトについて、豊富なスライド資料を用いて紹介と分析がなされた。コメンテータからは男性の果たす役割についての質問や、サイイド(預言者の末裔)概念と聖者信仰の関わり、また近接するヒンドゥー系のコミュニティにおけるズィヤーラ慣行との関わりなどにつて、指摘と質問がなされた。
2月26日
セッション4(10:00 - 11:45)
イリーナ・ペトロシャン(ロシア・東洋学研究所サンクトペテルブルク支部)
"Pilgrimage Sites in the Early Ottoman State: The Problem of Interrelation
of Islam and Christianity"
司会:黒木英充(東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所)
コメント1:三沢伸生(慶應義塾大学)
コメント2:今松泰(神戸大学大学院)
豊富な史料を用いて、オスマン朝初期の小アジアにおける聖者信仰と巡礼慣行の事例が、イスラームとキリスト教をときには対比し、ときには超越する形で整理発表され、複雑で多様な象徴化の作用について紹介がなされた。コメンテータからは、今日の同地域との連続性の他、同じ地域を異なる観点から研究する利点を生かして、発表者の研究が秘めている可能性を補うコメントがあった。
総括討論(12:00 - 13:00)
司会:赤堀雅幸
四つのセッションを介して浮かび上がってきたいくつかのテーマ―個体と集団、境界性、ジェンダー、象徴化、ノーブルネスなど―について議論が行われ、今後さらにそれらを究明していく必要が強く認識される、よい形で課題を残す議論となった。
全体としては、誰にとっても母語ではない英語を使わざるえないことの問題はあっても、非常に前向きに参加者が取り組み、実り多いワークショップとなったと自負している。ワークショップ組織担当者の責任で、このワークショップの成果はしかるべき形で刊行したい。
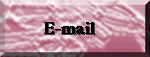 |
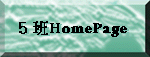 |
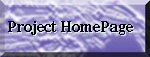 |