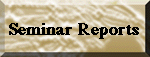
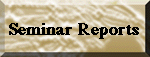
5b「歴史の中のイスラーム」の「ミクロへの接近」小グループ(担当、杉田英明)は、11月14日(土)に東大・東洋文化研究所で今年度の研究会を開催しました。3人の報告者を含め、参加者は16名。2時から始まった研究会は7時近くまで続き、さらに参加者の多くは場所を移して遅くまで熱い議論を続けました。以下はその報告です。
栗山氏が解題を行ったのは、オランダのライデン大学図書館に所蔵され、今回マイクロフィルムを入手したAbu Makhrama, Qiladat al-Nahr fi Wafayat A'yan al-Dahr(アブー・マフラマ『時代の名士たちの死去に関する首飾り』)という写本である。これは16世紀半ばにアデンのカーディー職を務めたアブー・マフラマによるヒジュラ暦501年から920年までの名士2239人の死亡録と年代記で、写本が書写されたのは1030/1621年のことである。主としてハドラマウト、イエメンの名士を扱うが、例えばサラーフアッディーンのような有名人の死亡録も含まれている。
栗山氏は、写本の内容、この著作が参考にした資料、既存のハドラマウト関係史料との関係について説明し、この著作の史料的価値として次の3点を指摘した。
栗山氏は、今後松本弘、大坪玲子両氏とこの写本の講読会を続けて行くとのことである。
深見氏は、まず、イスファハーンの都市構成、宗教建築、世俗建築について簡単な概観を行い、その後このイランの古都の住宅建築について報告した。氏は、サファヴィー朝時代にシャルダンが残した文献学的な記録と今夏の現地調査の結果を併用し、17世紀におけるこの町の邸宅の特徴を、1)独立棟式およびパヴィリオン、2)中庭式、の二つの場合に分けて説明した。また、スライドによって、現存するサファヴィー朝期の建築(市内全体で10点以下、うち調査済みが4点)やその装飾の特徴を具体的に解説した。
ソレマニエ氏は、カーシャーンに残る約20点のガジャール朝期の住宅建築を今夏調査し、その結果をスライドやOHPを交えて報告した。従来、イランの伝統的な大規模住宅はアンダルーニー(内庭)とビールーニー(外庭)という二つの性格の異なった中庭を持っているとされてきた。すなわち、アンダルーニーは家族の私的な空間、ビールーニーは来客用の公的な空間という理解である。しかし、ソレマニエ氏は、これに必ずしもあてはまらない邸宅の例を示し、特に小中庭の役割について、考察を深める必要があることを指摘した。また、サルプースィーデと呼ばれる独特の天井を持つ空間についてもその機能に注目すべきであると主張した。
発表は3本とも最近の研究成果を存分に織り込んだ熱の入ったもので、多くの質問、コメントが出されました。発表のレジュメやスライドの一部は5班のホームページに近く掲載予定です。ご期待下さい。
(文責 羽田 正)
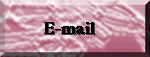
|
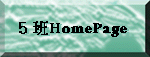
|
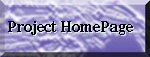
|