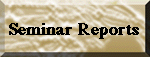
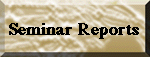
中東・イスラーム研究において、我が国では本テーマ関連の総合的研究会はほとんど開催されることなかったと思われる。また、「インフォーマル・セクター」というのが曖昧かつ問題を多く抱える概念であることも多言を要すまい。しかし、一方で、この名を冠した研究がエジプト等を中心に中東地域で続出していることも事実である。
そこで、今回は試みとして、中東・イスラーム世界における「インフォーマル・セクター」研究の現状・固有性と展開の可能性を探るとともに、そこから中東・イスラ ーム世界を越えて問題をどのように照射できるのかを考えるための第一歩としたいと念願している。さらに「開発」や「環境」、(あるいは植民地主義や共生)その他の 問題群へ展開できるのかどうか、今回は地理学、社会学、経済史学、社会史、人類学 、宗教学など様々な角度から異なるディシプリンを交錯させてみたい。
|
日時 |
1998年2月21日(土) |
|
場所 |
九州大学箱崎キャンパス 文学部4階大会議室 |
|
|
趣旨説明・・大稔哲也 |
|
13:30〜14:00 |
加納弘勝「インフォーマル・セクター研究と社会---トルコの例にふれながら-----」 |
|
14:00〜14:30 |
店田廣文「エジプトの首都カイロのゴミ収集人たち」(スライド付) |
|
14:30〜15:00 |
大稔哲也「カイロのゴミ回収・養豚と肉流通---現状報告---」(スライド付) |
|
15:00〜15:10 |
長沢栄治(コメント) |
|
15:10〜15:40 |
質疑応答 |
|
15:40〜16:00 |
休憩 |
|
16:00〜16:30 |
熊谷圭知「「都市インヴォリューション」 か、それとも「再農村化」か?---パプアニューギニア、ポートモレスビーにおける都市移住者の生存戦略とインフォーマル・セクター ---」(スライド付) |
|
16:30〜17:00 |
上田元「ケニアにおける零細企業群再生産の歴史と理論」 |
|
17:00〜17:10 |
遠城明雄(コメントとガーナの事例) |
|
17:10〜18:00 |
質疑応答と討論 |
|
|
新プロ「イスラーム地域研究」の説明・・後藤明 |
まず最初に、大稔哲也の方から本研究会の趣旨説明がなされた。特にILO等に始まるその定義の変遷、および開発(経済)援助を背景として発した観方の偏りなど多くの問題点が俯瞰された。
その後、最初に、加納弘勝の方から中東におけるインフォーマル・セクター研究への3アプローチ(社会マージナル、国家規制、小企業)の概要が述べられ、それにインター・ネットをいかに活用し得るか実例が示された。さらに、データを基にアンカラの事例が提示された。
店田廣文の報告では、エジプト・カイロのゴミ収集人(ザッバーリーン)の事例が取り上げられた。まず、その歴史的展開・ゴミ収集システムを解説後、コプト・キリスト教徒の地区であるマンシヤット・ナーセル地区を舞台に、現在のリサイクル産業の担い手としての在り方や、ガマイーヤと称す各種組織の実態と機能が報告された。
大稔哲也は店田発表を受けて、カイロのゴミ回収・処理人とその養豚業、およびコプト中心のマンシヤット・ナーセルとムスリムのゴミ回収・養豚集落の比較、回収人のライフ・ヒストリー等について、スライドを中心に現状分析した。さらに、オール
ド・カイロ地区の革鞣し、窯業、漆喰作り、屠殺業等との関連についても伝統的技能の問題を絡めて付言した。
これらに対して長沢栄治からコメントとして、「都市の農村化」の問題、また特にエジプトにおいて都市のインフォーマル・セクター研究ばかりでなく、農村部におけるその展開を追う必要性も指摘された。
後半部では、まず、熊谷圭知からパプアニューギニアのポートモレスビーの事例をもとに精緻な報告がなされた。そこではパプアニューギニアにおける「都市」の在り方から説き始められ、「インフォーマル・セクター」活動実態と成長の契機が報告された。さらに、部族共有地上に立地する集落形成と生活様式の変化も明らかにされる。加えて、都市における「貧困の共有」と農村への「回帰」へと議論が展開され、インフォーマル・セクター概念に関しても、その「権力・制度外の活動」という側面から極めて重要な問題提起が行われた。
次いで、上田元発表ではケニアを舞台に、その歴史的・空間的文脈への顧慮の欠落した従来の「インフォーマル・セクター」研究の克服のために、多くの貴重な提言がなされた。そして、上田自身はインフォーマル・セクターの代わりに「零細企業群」の用語をもちい、まず、国家社会関係の中で捉え直した後、ケニアの零細企業群研究に潜む問題点として、企業単体主義、企業拡大主義、生産・雇用関係捨象主義等を指摘。その超克を意図して、ニェリ市の屋外自動車修理工の調査研究実例が報告された。
これらに対して、遠城明男の方から再度まとめ直された後、コメントとガーナの事例との比較が付け加えられた。特に、ガーナの場合では北部から大都市(ここではアグラ)へ移住してきたハウサ部族のムスリムが、インフォーマル・セクターとより多く関連している事例も述べられた。
この後、討論の中では、「インフォーマル・セクター」という用語・概念の問題点、使用の可否、あるいは我々がそれをどのように定義してゆくかが検討された。特に、経営規模や行動様式を強調するか、権力・制度外である点に力点を置くべきか討論された。また、前近代からの存続する「インフォーマル・セクター」は、近代起源のそれとは区別して、伝統的産業として理解すべきかどうか、また、全般に中東地域におけるインフォーマル・セクター研究が盛んではないことの理由とそのこと自体の評価をめぐっても議論された。
さらに、中東・イスラーム研究をインフォーマル・セクター研究の前に冠することによって、積極的意義が見出せるのか。これは、「イスラーム地域研究」にも同様に課された問題であると言えよう。その意味では、今回は、試論的意味合いに過ぎないものであった。
最後に、やはり反省点を2点ほど付け加えるならば、前半部の中東を舞台とする報告対象と後半のアフリカ・パプアニューギニア対象の議論では、双方ともその現地では「インフォーマル・セクター研究」と称されているものの、かなりその色合いが違ったことも事実である。前者においては、いわば「スラム」や「貧困」が表面上目につきやすい一方、インフォーマル・セクター研究の蓄積豊富なアフリカなどの後者の場合、もっと精緻な分析のうえに総合的な対象把握がなされているように見受けられた。ただし、これをどちらかの誤りと断定する方向よりも、様々な文脈に即した「インフォーマル・セクター研究」の在り方を探ってゆく方が有効との意見も提出された。
また、開催が遠隔地であったことと多忙な時期であったため、九州以外からの参加者が若干少なめであったのは幾分残念であった。
なお、研究会では最後に後藤明(第5班責任者)から、新プロ「イスラーム地域研究」全体の解説もなされ、今回初参加の研究者達からも大いに理解と今後の協力約束を得たことを付記しておく。
加納弘勝(津田塾大学)、店田廣文(早稲田大学)、熊谷圭知(お茶の水大学)、上田元(大東文化大学)、長沢栄治(東京大学)、遠城明雄(九州大学)、後藤明(東京大学)、田中哲也(福岡大学)、清水宏祐(九州大学)、大稔哲也(九州大学)他、計24名。
(以上、大稔哲也 記)
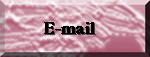
|
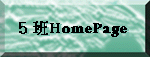
|
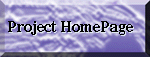
|