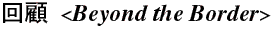
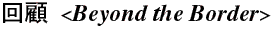
阿久津正幸
1999 年 10 月 8 日から 10 日にかけて、Beyond the Border というテーマの下に、京都で国際会議が開催された。筆者が参加したこの会議のセッション・サブセッションは、時間順に 1-1、1-2、2-2 (以上 10 月 8 日)、1-4、2-4、2-5 (以上 10 月 9 日)、そして 3-1、3-2 (以上 10 月 10 日)である。
このなかから、筆者が特に強い印象を受けたセッションにまつわる論点を中心として、時系列に関係なく各サブセッション中の発表を取り上げていくことで、関連した考察を行う。筆者が本会議への参加にあたって興味を抱いた以下の点が、そこでの主要な話題となる。それは Beyond the Border というメイン・テーマの設定意図、そしてそれに対する発表者個々人の取り組み姿勢、の2点に終始する。
ホームページや電子メール等による事前の告知においては、メイン・テーマの副題となる、A New Framework for Understanding the Dynamism of Muslim Societies 以外には、本会議の意図に関する詳しい説明はなされていなかった。そのため、筆者はこのテーマ設定になおさら注目をした。会議に参加した結果、なかでも The Concept of Territory in Islamic Law and Thought という表題の下に発表と討議が行われた、第一セッションに強い関心を抱いたことから、これを中心として報告を進めていく。
Dar al-Islam as an Ideology と銘打たれた 1-1 において、たとえば Michael LECKER の発表、On the Burial of Martyrs では、イスラム史初期、ヒジュラ歴 1 世紀における殉教者の宗教思想的概念やその定義を巡って、実在する存在としてのダール・アルイスラムの「虚構性」が問題とされているのだろうと筆者は理解した。対内・対外双方を含めた、初期のムスリム共同体の拡大過程における戦闘では、前例のない規模の死傷者が続出し、多くの犠牲者の屍が積み重ねられた。
未だ発足当時にあって、新興勢力として少数派とみなされるムスリム共同体においては、こうした事態は共同体存続の根幹に関わる危機的状況であったことは容易に理解される。そうしたなかで、対内的戦闘においては、啓典の民として同じ信仰を保持する同胞であり、かつ同一の神話を共有するユダヤ教の周知のモチーフが利用されて、犠牲者が神話化されていく。また対外的戦闘においては、ジハードの促進のために、たとえ悲惨な末路を遂げようとも、異教徒が多数を占める地において刃に掛かることの宗教的価値が強調されることで、犠牲者の来世が保証される。
犠牲者を殉教者として神話化していくことが、思想的あるいは概念的な側面から、誕生間もない少数派共同体の凝集性と連帯感を確保しただけでなく、さらに地理的・空間的に拡大していく政治・社会的過程においても作用をした。つまり思想や政治双方におけるイデオロギー的側面こそが、ダール・アルイスラムという概念を存続させ得た鍵であり、またそうした概念でもって理解される実在的空間あるいは領域が拡大していく過程の鍵ということであろう。
LECKER によるこのような研究は、歴史的にムスリムが保持してきた「虚構性」を積極的に肯定し、現実の歴史理解の作業で利用していくための方法として有効性があると筆者は受け止めた。発表後の討論においては、史料操作上の問題、また実証性の問題を指摘する意見が出された。確かにこうした声が指摘する通り、イデオロギー性を帯びたムスリムによる歴史記述は、後世において追加された部分が多いものと考えるべきである。当然ながらそれだけに依存して、当時の実際の状況を再現し、描写することには慎重でなければならない。こうした点は、そもそも本セッションの表題にも明確に示されており、共通に理解されていることと筆者は考える。しかし、前述したように、後世のムスリムによって脚色された「虚構性」もまた、注目すべき点なのではないだろうか。
たとえばハディースの多くが贋作であり、後世の捏造であると指摘する研究があるが、次にそうした事実から引き出すべき理解とは、そのようにムスリムの著述家を差し向ける背景や理由ではないか。ふさわしいかどうか検討の余地はあろうが、筆者はそれをここまで「虚構性」と表現してきた。
そこで、思想的特徴のなかでも、イスラム法学の分野に目を転じてみる。たとえば1-2 の柳橋博之による発表、Solidarity in an Islamic Society では、定義上ムスリム共同体によって統治されるのがダール・アルイスラムという実在的領域であり、その領域内外の非イスラム共同体や、あるいは領域内部の非イスラム的要素に対する軋轢を生じる潜在的な傾向をもつという。
発表では、後者の非イスラム的要素に注目するために、主にイスラム以前の部族的伝統が取り上げられる。非イスラム的な部族的慣習が完全に払拭されなかったことは、コーラン研究の分野においても認められていることだが、イスラム法においては、基本的に同様の傾向をもちつつも、次第にそれが排除され、部族的伝統からイスラム的原理に基づく方向に向かっていく領域があると指摘される。その考察のための事例として、解放奴隷の庇護者の地位、婚姻後見人の就任、扶養の権利義務、財産後見人の就任などを定める法制度があげられている。
現代的観点からは、これらが家族に関係した法制度であることが容易に連想される。だがこれらのなかで、たとえばイスラム法における扶養の権利義務の問題は、家族を核とした比較が当を得ないことが明らかとなる。扶養義務者である夫に対して、扶養を受ける妻は夫との婚姻契約の観点から考察され、対して子供は親族の定義上の問題として扱われるという。そして直接に関係する当事者集団の範囲で判断がなされる前者が、よりコーラン的原理に基づいたものという。
社会を構成する基本的社会集団である家族は、社会を構成する様々な社会集団のひとつである。それを規制する社会制度としてのイスラム法の法学的特徴は、イスラム的要素と非イスラム的要素とが重層的であることが指摘されている。こうした社会の中における小集団の考察を発展させることで、ダール・アルイスラムという共同体(あるいは社会)は、イスラム法によって統治された実体であり、コーラン的原理が体現された存在であるということができるのだろう。
しかし指摘されるように、そのコーラン的原理のなかには、本来的にコーランの規定によって排除されるべき要素が含まれているのである。そしてそもそもコーランのなかには、歴史的要素と非歴史的要素が併存しているのである。こうした本質的特徴が、小集団としての家族に関する社会制度や、あるいはその小集団が属する社会全体とそれに関わる諸制度――ここで問題としている法――においても、コーラン的要素と非コーラン的要素を重層的にさせる原因を生み出しているのではないだろうか。それを的確に表現したのが第一セッションの表題 Dar al-Islam as an Ideology なのであろう。コーラン的原理が体現された、イスラム法に基づいてムスリム共同体によって統治されるダール・アルイスラムとは、そうした意味を持つのである。
そもそもイスラム世界に限らず、社会制度は相対的であり、相互に調和を保つとは限らないものと考えられている。家族というひとつの社会制度の考察だけでなく、その対極である国家という別な社会制度に関する法学的思想を検討しつつ、比較を行っていくことが不可欠なのではないか。本会議で扱われた事例を例に挙げると、ジハード思想の面にも、同様の法学思想的特徴が如実に現れている。
神の道のために努力することという原義を持つジハードであるが、その努力が戦闘という形態をとる場合には聖戦と訳されうるものである。前述の LECKER においては、初期史における殉教者概念の手段として、対外的戦争(ジハード)促進において、犠牲者の神話化が利用されたことが指摘されている。一方で 1-4 の中村妙子の発表、Territorial Disputes between Syrian Cities and the Early Crusaders においては、12 世紀シリアにおけるジハード思想の現実的側面を描写するために、フランク(十字軍)とムスリムとの外交関係を、両者の間で達した「合意」に注目し分析を行っている。両者の間に取り交わされた合意からは、政治的・経済的覇権の獲得が主眼とされていたこと、こうした状況において、時にムスリム側支配者によって提唱されたジハードは、ムスリム側の見解を統一することもなく、むしろ政治的駆け引きの道具と化していたことが報告される。
フランク対ムスリムという対立の構図を想定して、ムスリム支配の確保という宗教的・政治的イデオロギーでもって当時のウラマーやその後の史料においてジハードという言葉が言及されようとも、現実においてそれは純粋に宗教思想的意味を持ち、かつそれが実際に用いられていたわけではない。
法解釈学的側面から、社会において実際に適用されてきた法の是非を問うイスラム法の実定法学は、その法律を不可欠とする世界、あるいは社会との関連において、それが適用されている事実だけに注目してきた。しかし因果的側面を問題とする場合には、根本的な法学思想と実定法学が完全に一致するものでないことは、たとえば法的擬制の原理からも明らかである。こうした傾向は特にイスラム法だけに固有の特徴でないことは言うまでもないが、それをイスラム法の柔軟性として法解釈学的結論で片づけず、そうした柔軟性の現実的状況を、社会的関連において思想的に描写していくことが、社会を全体的に見つめていくために必要なのではないだろうか。
LECKER の報告において、初期のウラマーは、ある面では支配者に反対しつつも、殉教者概念の創造においては積極的だった。こうしたウラマーの行為が支配者の体制擁護に機能していたと言われているのである。指摘されるこうした構図において、ウラマーが担った役割やその立場が大変示唆的ではないだろうか。イスラム的価値観に基づいた凝集性を持つ共同体の存続は、ウラマーの協力なしには不可能であったろう。だが、だからウラマーが支配者に協力をしたのではないということである。
法とは民族的・社会的言説の枠組みであり、最も具体的に事実を明示する「社会的事実」を表象するものである。そうすると、イデオロギーとされるダール・アルイスラムを統治するのがイスラム法であり、イデオロギー性の事実を具体的に明示するのがイスラム法なのであろう。こうしたイデオロギーを巡って、現実的な社会の指導者である支配者を中心におくと、ときにこれら支配者に反対し、ときに(結果的に)協力的な態度をとるウラマーの二面性は、歴史的要素と非歴史的要素を併せ持つコーランを、歴史の現実において実在的に説明しようとするムスリムのもつ「虚構性」が思想的に存在するゆえであって、その両側面の相違点、つまりウラマーの言説を描き出していくことが、今後の課題なのではないかと感じた。柳橋が行っているように思想的側面からの考察を押し進めると同時に、それらを生み出した政治や社会との関係の下で、ムスリムが使い分ける虚構性の言説を読み解いていくことが、概念的、そして実際的な歴史理解につなげられるひとつの方法ではないかと考える。
絶対的で普遍的な重要性が付与されるコーランの思想は、ムスリムによって展開されてきた歴史において等しく共通して重視されるものである。それは 2-5 の Dale EICKELMAN の現代的考察、Blurred Boundaries においても共通に見いだせる特徴である。現代の発達したマス・コミュニケーションを媒介として、コーラン解釈を中心とした宗教的機運(発表者が別な論文で指摘する自己客体化の現象)が、一般庶民という従来みられない階層においても拡大している。その背景としては、一見すると宗教に深い関係をもっていない、識字率の向上に貢献する大衆教育の普及、その下でのマスコミという技術的発展の側面に目が向けられている。
そもそも聖と俗を区別しないというか、未分化というべきか、こうした特徴をもつとされるイスラムにおいて、それを理解するためには、聖と俗、たとえば宗教と政治・社会という区分でもって、歴史なり社会なりをみていかざるを得ないのが、中東の伝統文化を身につけた住民でもなく、またムスリムでもない筆者の立場であると考えている。しかし宗教という区分によって、すべてが宗教的性質、あるいは動機でもって判断すべきではないことも重要な事実である。
宗教思想に基づいた法的定義をもつワクフ制度であっても、それが宗教的価値観のためだけに作用していた訳ではなく、共同体の社会福祉事業的作用も看過できない重要な機能であることが、3-1 の Michael DUMPER の発表、Muslim Institutions and the Political Process から典型的に読みとれよう。宗教的寄進が起源とされる、ワクフ制度に基づく各種ワクフ施設が発展した歴史的過程において、その背景はムスリム共同体が拡大する方向にあった。しかしここではまったく正反対となり、縮小を余儀なくされているパレスティナ人ムスリム共同体を背景に、ワクフ制度がいかなる働きをしているかが問題とされている。
宗教的価値観を反映した法思想、そしてそれに基づくという虚構の下で展開される法解釈学という溝が存在するのは、ムスリムとして絶対視すべきコーランそのものの性格にあることも、看過できないひとつの要因として検討課題に加えるべきであろう。コーランとは歴史的側面と同時に、非歴史的側面をも併せ持つ存在であり、こうした特徴をもつ思想を現実に保持していくためには、思想的側面で必ずしもすべての現実を説明し切れないものであろう。しかしこれはイスラムという宗教に対する倫理的否定や反論ではない。宗教とは本質的に理性を超えた存在であり、そうした存在を尊重するために、理性的側面にそぐわない面があっても当然のことではないか、むしろそうした宗教にこだわり続けるムスリムの社会が未だ展開され続けていることに注目し、その社会を成立させるメカニズムを理解するという視点こそが、本会議の副題に即した方向性なのではないかと考える。
研究者の視点と研究対象、つまり史料(あるいはその著者)のもつ視点との相違、時代的背景の相違、そして研究手法上の学際的相違といった、超えるべき境界は多く存在しているのであり、今後研究を継続するにあたって、大変に有意義な示唆を得られたと報告することで締めくくる。(文中敬称略)