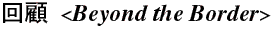
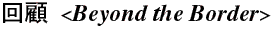
原山隆広
はじめに
本稿は、国際シンポジウム "Beyond the Border" (以下「京都国際会議」あるいは単に「会議」とする)の第三セッション "A City of Interactions: Jerusalem" のなかの、第二サブセッション "The Middle East Peace Process and Jerusalem" についての報告記である。以下の内容は、報告者が本サブセッションに参加したさいの記憶をもとに、配布されたペーパーなどを参照しつつ作成したものであり、実際の発表内容に対して記述の欠落や誤った解釈があった場合、その責任は全て報告者に帰する。
全体の構成としては、各発表と質疑応答に関して簡潔にまとめ重要と思われる点を挙げたのち、その内容を報告者なりに論じることとする。さらに本サブセッションの意義についても考えてみたい。
1.会議概要
まずは、会議全体のなかでの本サブセッションの位置づけについて触れておきたい。境界を生みだす概念や境界を越える「移動」という現象など、かなり漠然としたテーマが設定された第一、第二の両セッションに対して、第三セッションはエルサレムという一都市がテーマとされる点で前二者と趣を異にしている。そのなかでも本サブセッションは、パレスチナ和平交渉におけるエルサレム問題という現在進行中の事柄に対象を絞り込んでおり、全11のサブセッションのなかでも特徴的なものとなっている。このようなテーマ設定が、結果として本サブセッションの議論全体に一貫性を与えている一方で、後に触れるような課題をもたらすことになる。
事前に調整がなされたのか、各発表者の役割分担はかなり明確になっていた。議論の前提として、(一)パレスチナ問題の解決にはエルサレムの政治・宗教的な位置づけ、帰属確定の問題は避けて通れない。(二)イスラエル占領下のエルサレムで、現在も居住、移動、経済活動、宗教活動、徴税、公共サービスなどで規制と差別を受けているパレスチナ人の状況改善は不可欠である。(三)そのためにはイスラエル側も何らかの譲歩をするべきである、との認識が共有されていたのは間違いない。そのうえで、G. S. Khoury 氏が、エルサレムへの思いの丈を語った後、A. Lesch 氏が同都市でパレスチナ人が受けている抑圧の状況を報告し、池田明史氏がイスラエル当局による従来の都市政策の概括とエルサレムの拡大計画の分析をおこなった。これらを踏まえ、立山良司氏が採るべき解決策について幾つかの選択肢を挙げて検討するという流れになっていた。
問題の構造を明らかにするうえで重要なのが、エルサレムという都市が「イスラーム、キリスト教、ユダヤ教という三宗教の共通の聖地」と「ユダヤ人、パレスチナ人(パレスチナ・アラブ人)によるそれぞれの国家の首都」という二つの性格を持ち、さらにエルサレム問題自体が「シンボル」的意義と「本質」的意義の両義を有する事実を理解することである(ここで「本質」的意義とはパレスチナ人の置かれた上述のような状況の改善などを指すと考えれる)。また、エルサレムが地理概念としても可変的、重層的であった点も大きな意味を持つ。実際にエルサレムの範囲は、城壁内の旧市街に限定される場合から、エルサレムの現行政区域をはるかに越える広大な地域を含んだ "Metropolitan Jerusalem" まで、複数の定義のもとで用いられている。
発表中で立山氏は、同問題の解決へ向けて従来の諸案から一歩踏み込んで、氏独自の提案をするまでには至らなかった。他の報告者のうち Khoury 氏や Lesch 氏らも、発表あるいはペーパーのなかで解決策に言及していたが、やはり従来の諸案の枠内に留まる内容といえる。そのなかで、エルサレム問題の現実的な解決策に求める条件という点では、彼らの見解は大筋で一致していた。すなわち、エルサレムが都市としての一体性を失わず、イスラエルとパレスチナ人国家の双方の首都となり、そのなかでユダヤ人とパレスチナ人のそれぞれの共同体の自立性が保たれ、かつ三つの宗教に対して平等に開かれていることであった。
本サブセッションを含め、近年、有力な選択肢として検討されている諸案は、当事者間に存在するエルサレムについての認識の相違を利用し、概念操作によって新しいエルサレム像を作り出すことによって、上述の条件を満たしつつ、エルサレムの分割を固辞し続けるイスラエルとの妥協点を探ろうとする立場といえる。
2.発表内容をもとに
次に、以上でまとめた発表内容について、幾つかの問題を取り上げて検討する。
まずは、エルサレム問題の解決策として発表者達により提示(紹介)された諸案について、歴史的文脈から考察してみたい。各案ごとに相違点も大きいが、彼らが有力な選択肢と考えるものに関しては、全体の潮流として、宗教面ではイスラーム、キリスト教、ユダヤ教の三宗教の共存、政治面ではイスラエルとパレスチナ人国家の双方による主権の保持の方向へと進んでおり、宗教・政治の両分野で、対等な立場での関係樹立が重視されている。
ところで、エルサレムの将来像が語られるさい、諸宗教、諸集団の共存の範を過去のエルサレムに求めるケースがしばしば見出せる。しかし、これら諸案がかかげる目標は、これまでのどの事例とも様相を殊にしているのは明らかである。
もっぱら前近代のイスラーム期を対象とするが、各集団が主に宗教・宗派をもとに区分されていたこの時代(この点で現在と状況は大きく異なる)、十字軍による占領などの一時期を除いて、政治的にはエルサレムの支配権はムスリムの支配者達が保持し続けた。キリスト教徒、ユダヤ教徒はズィンミーとなりムスリムへの服従を認めることで彼らの信仰を保持することが許されたのである。このような状況での各宗教・諸集団の共存とは、優位な立場にある集団の宗教的「寛容」を背景として生み出されたもので、それら集団間の対等な関係を意味するものではなかった。この点では、実態はともかく、自らの主権のもとでキリスト教徒やムスリムの、あるいはパレスチナ人の地位や状況の改善をはかるというイスラエル側の建前は、これまでの構造を踏襲しているとみなすことができる。
上述の諸案が描く、エルサレム問題の解決へのシナリオは、諸集団間の対等な立場を前提とした関係を模索している点で、新たな段階へと歩み出していると言えよう。この試みが最終的にどのような形で決着するか報告者は予想しえないが、エルサレムをめぐる「概念操作の問題」がその成否の鍵として関わってくることは確かである。
イスラエルの存在そのものは認める方針で問題解決をはかる限り、イスラエル側が彼らが想定するエルサレムの範囲内に関しては譲歩する可能性は極めて低く、一方パレスチナ人側もエルサレムに彼らの国家の首都を置くことは譲れないというジレンマに直面することになる。双方の主張を擦りあわせようと試行錯誤するなかで、各案とも定義や概念自体に手を加えることに可能性を見出し、新たなエルサレム像の創出に至ったのであろう。しかし、方針自体は良いとして、いずれの場合もその後に進めるべき新たなエルサレム像の定着化のための見通しが示されていないことが問題である。
より多くの人間が納得しうるエルサレム像を作り出すことも重要であるが、如何に概念操作の段階で妙案を示そうとも当事者全てを満足させることが難しい以上(発表者のKhoury 氏が、一貫して1948年の分割時の東エルサレムを念頭に置いて議論を展開していることからも、彼らパレスチナ人側の思いの強さがうかがえよう)、どのようにしてそれらに実体を持たせて当事者達の間でコンセンサスを育んでいくかという作業が欠かせないであろう。本サブセッションのなかでは、この問題にまで踏み込んで何らかの提言をした発表はなかったと考えられる。
最後に、立山氏が指摘していた、エルサレム問題をめぐる「シンボル」と「本質」の関係に触れて本章のまとめとする。氏は発表中で、この問題についてさらなる言及は行わなかった。他の発表でも、三つの宗教・二つの民族の共存の場としてのエルサレムと、実際に人々が生活する場としてのエルサレムという双方の性格を考慮する必要性は述べられているが、それらはいずれも原則論の域を出てはいない。
しかし、この双方の追求を両立させることは実際には容易なことではなかろう。ある対象がシンボルとしての性格を強めていくほど、その対象自身の事情は二の次にされていく傾向が指摘できるのではないだろうか。
かつてパレスチナ問題自体が、アラブ民族主義というより大きな潮流のなかで、「アラブの大義」の名のもと、現実には政治・経済・社会状況とも様々に異なる人々の間に「アラブ」としての一体感を与え彼らをまとめていくためのシンボルとして位置づけられる状況を経験している。その間アラブ各国の思惑や国際情勢に翻弄され、パレスチナ人自身の事情はときに二の次にされてきたのであり、結局パレスチナの解放という目標は達成されずに今日まで引き継がれている。
パレスチナ人と呼ばれあるいは自認する人々の現状を見渡すに、イスラエル建国とその後のアラブ・イスラエル抗争の過程でまさしくディアスポラを経験した結果、同じパレスチナ人といっても、エルサレムの旧市街に居住する貧困層、エルサレム周辺に居住する者、パレスチナ自治政府の統治下の住民(そのなかでも、西岸地区と宗教的な雰囲気が強いガザ地区に分けられよう)、イスラエル占領下にある西岸地区の住民、難民としてヨルダン、レバノン、シリアなど周辺アラブ諸国に移住した者、その他中東地域や、欧米に移住した者など、彼らの置かれた立場は様々である。
このような状況のもとで、都市エルサレムは既にパレスチナ人の間で統合と独立のシンボルとして機能している。それゆえにパレスチナ人側にとってもエルサレムを自らの国家の首都とすることは譲れないところであろう。しかし、その要求の実現が、エルサレムに実際に暮らす人々の利益と合致する形で成し遂げられるか否かは約束されたわけではない。それは質疑応答のなかで藤田進氏が(エルサレム旧市街の貧困層の問題を挙げて)指摘していたように今後に残された大きな課題といえよう。
3.本サブセッションの意義
本サブセッションに関してはそれ自体の意義が問われるところである。当日の参加者のなかには発表自体の内容にもまして、質疑応答のさいの一幕、エルサレムから会議に参加したイスラエル人(ユダヤ人)のM. Lecker氏と発表者の一人でキリスト教徒パレスチナ人である Khoury 氏の間での応酬が印象に残っている方々も多いのではなかろうか。要点だけ挙げると、Khoury 氏らの発表の学問性を問題にし、イスラエルによるエルサレムにおけるパレスチナ人への対応が歪曲され伝えられているとした Lecker氏に対して、 Khoury 氏は彼の認識の誤りを指摘し、パレスチナ人に対する抑圧が事実であることを訴えるという経緯であった。
この両氏の論争は、奇しくも Lecker氏ほどの人物をして、自らの国家の問題ついては冷静ではいられないことを示すとともに、占領下のパレスチナ人の状況をめぐる一般的イスラエル国民の認識度の一端を明らかにし、パレスチナ問題(含エルサレム問題)当事者の間に厳然と存在する、加害者側と被害者側の意識差を改めて示す結果となった。それと同時に、ここでは、日本の研究者が中東地域を学問対象としていくことの意義について考えさせられるところがあった。
今回の会議でエルサレム問題を扱うことに関しても、第三者の中立的立場で問題の経緯を分析しその構造を解明するだけでは不十分であろう。とくに、この第三−二サブセッションは、その舞台となっているエルサレムとそこで生きた人々の活動を歴史的、社会的な視点から検討するという作業を第三−一サブセッションで扱うという形で切り捨てて、現在進行中のパレスチナ和平交渉で懸案となっているエルサレム問題に対象を特化することで(議論の一貫性に加え)現実社会との共時性を保ちえている以上、問題解決に貢献するような新たな提案を行い、さらにその成果を還元することから逃れられないといえよう。加えて、同問題についてこの時期に日本の学会で検討することの意義をも問われているのである。
このように考えたとき、本サブセッションが、エルサレム問題をめぐる従来の議論の単なる評価にとどまらず、上述の課題に対し積極的に解答を示し得たと言い切れるであろうか。報告者は、良くも悪くもまとまりすぎていたという印象を受け、さきのLecker、Khoury 両氏の応酬も含め、恐らく現地や欧米でこれまでに幾度となく繰り返されてきた光景の縮小再生産の域を出ないのではないかと感じた。
その一方で、本サブセッションの意義および評価は、いかにしてその成果を還元していくかという今後の作業により決定される部分も大きいと考えられる。この報告を執筆中にも、ガザと西岸地区を結ぶ南安全回廊が開通し、パレスチナ最終地位交渉が開始されようとしている。エルサレム問題をはじめ、難民帰還問題など残された議題は容易に合意には至らないだろう。しかし、オスロでヤセル・アラファト氏がレア・ラビン夫人の手にキスをする光景などを目にすると、当事者達が一時の停滞から脱して歩み始め、パレスチナ問題が新たな展開を見せていることが実感される。
京都国際会議の報告集は来年にも刊行されるということであるが、現地の動きに置いていかれないためにも、それを待つのではなく迅速な成果の公開が望まれる。電子メールやインターネットといった情報システムを用いた研究情報のリアルタイムでの提供は「イスラーム地域研究」プロジェクトが当初から掲げてきた目標の一つでもあろう。
おわりに
会議から一ヶ月が経過しようとしている11月18日現在、「イスラーム地域研究」ホームページ中の「京都国際会議報告」において第三セッションの報告は掲載されていない。