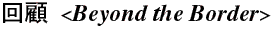
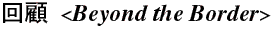
太田啓子
京都国際会議3日目・午前に行われたセッション3-1においては、「共存と紛争」というサブセッション・テーマのもと、 (1) Yasir SULEIMAN (The University of Edinburgh) (2) Michael DUMPER (The University of Exeter) (3) FUJITA Susumu (Tokyo University of Foreign Studies) (4) USUKI Akira (The National Museum of Ethnology) の4氏による研究報告が行われた。なお、予定されていたAmnon COHEN氏 (The Hebrew University) による報告「オスマン朝期エルサレムにおけるユダヤ人コミュニティ:コミュニティは実際隔離されていたか?」は、COHEN氏が東海村の原発事故により急遽来日を取りやめられたことから残念ながら中止となった。各報告は、DUMPER氏によるエルサレム問題についての15分ほどのレクチャーの後に行われた。
(1) SULEIMAN氏による報告「政治紛争の社会言語学的反映:エルサレムの場合」は、政治・社会状況と言語の関係をエルサレムを例に論じたものであった。
SULEIMAN氏は第一章において、言語の担う役割を、「意思伝達手段としての役割」と、「社会集団の象徴としての役割」の二者に区分する。そして後者の役割を認識することにより、それらの言語を用いる社会集団間の強弱関係を定義づけることが可能であることを明らかにする。すなわち、言語の強弱関係は集団の強弱関係を反映するからである。そしてこの象徴としての役割には、逆に現実の政治状況をも左右する力が内在することも示す。氏によれば、言語の持つ象徴的役割を用いて、現実をイデオロギーに合わせて作り替えていく過程が現在のエルサレムの状況であり(例えば、公共標識を全てヘブライ語のみに統一することにより、ヘブライ語民族であるユダヤ人の地位を向上させ、アラビア語を使用しないことにより、パレスチナ人の地位を低下させることなどがこれにあたる)、この状況こそが政治紛争の社会言語学的反映なのである。
第二章「言語における不均衡の状況」において、氏はユダヤ人とパレスチナ人の間の言語をめぐる歴史的経過について述べる。民族の紐帯としてのヘブライ語の重要性を当初から強く認識していたユダヤ人に対し、パレスチナ人が言語の持つ象徴的役割を意識しなかったことがイスラエル建国後のアラビア語の地位低下につながったのであり、アラビア語が当初パレスチナ地域の共通語として優位に立っていたこともパレスチナ人の認識の欠如を助長した。ヘブライ語に対するアラビア語の相対的地位の低下は、パレスチナ人がユダヤ人に政治的・社会的に抑圧されている事実の反映であると氏は指摘する。しかしその一方で、このような状況に対する社会言語学的抵抗がパレスチナ人の間に見られることは、パレスチナ人の民族的自己主張の現れであるとも氏は述べている。
第三章「エルサレムの標識」において、氏は道路標示、地名表記などを多数実例としてあげ、アラビア語が形式上も文法上もヘブライ語による侵害を受けており、これはパレスチナ人とユダヤ人の強弱関係の現状を反映していると指摘する。
第四章において氏は、報告内容を総括して次のように述べる。すなわち、エルサレムにおける、アラビア語に対するヘブライ語の優勢は、ユダヤ人がパレスチナ人に対して優位な立場にある現状を反映したものであり、このように、政治・社会状況の影響は社会言語学の領域において観察することが可能である。そしてこの報告は政治・社会状況と言語の関係を考察する研究の予備的研究の地位を占める。
(2) DUMPER氏による報告「ムスリム施設と政治プロセス:パレスチナのワクフとエルサレムをめぐる抗争 1967-1997」は、エルサレムにおいてワクフ制度が担ってきた役割と、ワクフ制度が政治プロセスに与えた影響について検討したものであった。
序論においてDUMPER氏は、エルサレムにおいてワクフ制度が果たしてきた役割を、イスラムの信仰心の振興、周辺地域の資産のエルサレム内部への吸収、ワクフ制度の整備に伴う行政の発達の3機能に分類する。その上で、これらの機能を実証的に検証すること、そしてワクフ制度がエルサレムの政治プロセスに与えた影響について考察することが報告の目的であると述べる。
第一章「イスラム、パレスチナとエルサレムにおけるワクフの起源」においては、いくつかの例証を用いてワクフの起源と性質についての検討がなされている。ワクフ制度が都市の発展において中心的な役割を担ってきたことも指摘されている。またワクフ制度は周辺地域の資産を都市内部に取り込むチャンネルであると同時に、困窮者や巡礼者にサービスを提供するという機能をも果たしていたとされている。
第二章「エルサレムにおけるワクフ資産の規模」においては、ワクフ制度が都市の発展において重要な役割を果たしてきたこと、そしてワクフ資産の多様性が明らかにされている。
第三章「現代における法的・政治的枠組み」においては、1967年以降の政治的現実のもと、ワクフ制度がそれまで果たしてきた伝統的役割が継続可能かどうかを検証するため、イスラエルによるワクフ行政の政治的法的枠組みの考察がなされている。その結果、イスラエルにおけるワクフ関連法が他のアラブ諸国と比較して極端に厳しいものではなかったこと、そしてワクフ制度を通じてパレスチナ人住民に対するサービスの範囲と質が拡大されたことが明らかにされている。
第四章「オスロ合意以降のエルサレムにおけるワクフの役割」においては、1993年のオスロ合意以降の状況においてワクフ制度がどの程度の影響力を持つかが考察されている。その結果、一見保守的・官僚的で、非効率な制度に見えるワクフ制度が、実は柔軟性を持つ制度であり、都市の発展において重要な役割を果たす可能性があることを歴史的考察から明らかにしている。
結論としては、ワクフ制度は衰退に向かいつつあるどころか、現在も都市の発展に重要な役割を果たしているのみならず、エルサレムにおけるアラブ・イスラムの特性を維持し、パレスチナ人住民の現実的利益を保証するのに重要な役割を果たしていることが明らかにされた。また、ワクフ制度は現代の政治情勢にも影響力を保持し続けていることが分かった。
(3) FUJITA氏による報告「エルサレムにおける紛争と結びつき:多様な人々の都市」は、エルサレムにかつて存在していたユダヤ人とパレスチナ人の共存関係が、対立状態へと変容していく過程を、自らのフィールドワークの成果と国際情勢の分析を通じて概括している。
報告によると、かつてのエルサレムにおいては、ムスリム地区、キリスト教徒地区、ユダヤ人地区などの宗教・民族などに基づく居住地が存在し、三宗教の共存状態が実現していた。また、都市エルサレムの持つ受容力は多様な人々の共存を可能にしていた。しかし、バルフォア宣言以降始まったアラブーユダヤ間抗争は現在に至るまで継続している。ユダヤ人は「大エルサレム」構想の実現を目指しており、現在もパレスチナ人の強制立ち退き、ユダヤ人の土地取得が、パレスチナ人の権利を脅かす形で継続されている。
(4) USUKI氏による報告「日本人の思考の中のエルサレム:オスマン朝期・英国委任統治期パレスチナについての二人の日本人クリスチャンによる著作と日本におけるクリスチャンシオニズム」は、当時の日本人知識人の知の足跡をたどることにより、日本におけるクリスチャンシオニズムの起源を明らかにしている。
報告においてはまず徳富蘆花によるエルサレム巡礼記が検証され、当時の日本のキリスト教徒知識人が持っていたエルサレム観、ユダヤ人観が明らかにされる。そしてこれを下敷きとしてその15年後に行われる矢内原忠雄によるパレスチナ巡礼へと話が進む。矢内原忠雄は内村鑑三による無教会運動の流れにある人物であり、キリスト教徒としての信仰心を背景に、行き詰まった資本主義的植民地政策の打開策としてのシオニズムを受け入れ、聖書に依拠した世界構築を行う第一歩としてのユダヤ人のシオニズム運動に賛同する。そしてこの日本におけるクリスチャンシオニズムの流れは幕屋の運動へと受け継がれていくのである。
すなわち内村鑑三の無教会運動に起源を持ち、幕屋運動へと受け継がれていく日本におけるクリスチャンシオニズムの運動とは、資本主義的植民地政策の行き詰まりを認識した日本の知識人が、新たなる指針として、非資本主義的・非利益主義的性格を持つシオニズム運動を見いだしたことに端を発するのである。
以上が各報告者のおおよその報告内容であるが、以下、個人的な感想を、会場においてなされた質疑応答をふまえた上で述べていきたい。
まず(1)の報告についてであるが、政治・社会状況と言語の関係を論じた報告として、高く評価できる。社会集団の象徴としての言語の強弱関係が、集団間の強弱関係をも象徴するという論理は筋が通っており、従って政治紛争を理解する一つの要素として社会言語学的反映の考察が有効であるという結論に結びつけることが出来る。また、この方法はエルサレムにフィールドを限定する必要がないという点においても、今後他の社会集団の関係を検討する上で有益である。しかし、若干の疑問点も浮かび上がってくる。報告者は言語間の強弱関係を例証する上で、各種公共標識におけるヘブライ語・アラビア語・英語の位置関係、占有面積などを取り上げているが、これらの条件が果たして報告者が強調するほどの意味をもつか疑問である。特定言語の使用・不使用が言語の強弱関係を判断する上で決定的な要因になることは理解可能であり、それだけで十分報告者の論理は立証されると思われる。具体例の扱い方という点についてはLecker氏が同様に、交通標識と建立碑を、その性質の違いを省みることなく同種類の具体例として扱うことが不適切であることを指摘していたことを記しておく。
次に(2)の報告についてであるが、私自身はこのサブセッションにおいてはこの報告が最も興味深く感じた。ワクフの持つ機能のうち、周辺地域の資産を都市内部に吸収するチャンネルとしての機能、異文化支配の中においては特定の文化を保護する機能など、今まで注目していなかったことに多く気づかされた。ただ、質疑応答において三浦氏により指摘された点であるが、歴史的に見てワクフが常に宗教的寄進、公共設備であったと言えるかというと必ずしもそうは言えず、時代と地域によってかなりの差があることから、ワクフの定義をはっきりさせないまま考察が行われているのは少し問題であると言える。家族ワクフの存在に言及されてはいても、結果的にはワクフの主な機能を宗教的精神に帰するのは、ワクフの持つ多様な性格の一面だけを強調しているように考えられる。
(3)の報告については、国際政治史およびエルサレムにおける事件史の繰り返しとなることなく、報告者自身による聞き取り調査の結果がエルサレム問題を考える上での考察対象に含まれている。このことが、今まさに現在進行形で進行しつつあるエルサレム問題の持つ今日性を明白にしたと言える。エルサレム問題は歴史的なテーマであると共にまさに社会学的問題であるがゆえに、このような「生きた歴史」を目撃することが許されるテーマである。ただ、フィールドワークを通じて得られたこのような「歴史」が、どのような形でアラブ人でもユダヤ人でもない現在の我々と関わりを持ってくるかが、もう少しわかりやすい形で示されれば、エルサレム問題の持つ今日性と普遍性がより一層明らかにされたのではと考えられる。
最後に(4)の報告についてであるが、今までほとんど注目されることがなかった、クリスチャンである日本人知識人らの運動を取り上げ、日本におけるクリスチャンシオニズム運動とのつながりを明らかにした点で評価に値する。内村鑑三による無教会運動から「幕屋」運動に至る一連のクリスチャンの活動を背景とするクリスチャンシオニズムに関する最初の学術的試みが、今後どのような形で実を結ぶか期待できる。ただ、日本人によるシオニズム運動の原動力となった資本主義的植民地政策の行き詰まりの背景についての検証が、今後の研究においてなされることを期待する。日本人知識人らの行き詰まりと日本の近代化を重ねて検証することにより、本報告がより一層の普遍性を持つことが予想されるからである。
以上、各報告に関する個別的感想を終えて、全体的な感想に移りたい。
このサブセッション全体が、エルサレムにおける「共存と紛争」というテーマに対しどれだけ答えを出せたかという問いは、現実的な社会問題としては「紛争状態を克服し、共存へと到達する可能性が、この4報告を通じて見いだせるか否か」という問いに言い換えることが出来る。そしてこれは、これらの諸研究がいかに現実社会の問題解決に貢献できるか、すなわち研究成果の社会への還元という問題と同義である。個人的な感想としては、いずれの報告も「紛争」「共存」のいずれかの一面に着目しており(むろん歴史的経過の考察を通じて、もう一方の現象も取り上げられてはいるが)、サブセッションとしては、「共存と紛争」という問いに対して十分に答えを出したとは言えないとの感想を持った。そして、まさにこの点に関する質問が、当日、サブセッション全体に関する質疑応答において、参加者から出された。すなわち、(1)(2)の報告に関しては、これらの個別研究をいかにしてハイポリティクス(国際政治史)と結びつけて考えるか、そして(3)(4)の報告に関しては、日本人がエルサレム問題を研究対象とすることに何らかの意義があるとすればそれは何か、という質問である。この質問は、「なぜ我々は研究活動を行うか」という質問に非常に類似している。研究者による個別研究が多数行われなければ、研究全体の発展は期待できないが、個別研究の積み重ねだけでは研究そのものの意義が認められないのは当然である。我々は、諸研究の成果を何らかの方法で現代の社会に還元せねばならないのであり、そのような形で社会に貢献してこそ研究活動は社会的意義が認められる。(1)(2)の研究は共に高い評価に値する実証的・分析的な研究ではあるが、ハイポリティクスと結びつけることが出来て初めて現代的な価値を持つのである。また、(3)(4)の報告に関しては、日本国内におけるマイノリティ問題(在日韓国人問題)などが、エルサレム問題との類似点としてあげられていたが、やはりそのように積極的に、現代社会の問題と結びつけて考えることが出来てこそ、個別研究は意義を持つのではないかと考えられる。
以上のような点から考えると、エルサレム問題(パレスチナ問題)とは、まさに最も社会に成果を還元する可能性のある研究領域ではないだろうか。問題の本質から考えて、ハイポリティクスとも密接なつながりを持ち、しかも欧米中東および日本などから見て、植民地支配、帝国主義、マイノリティ問題など、いくらでも今日性のある共通点が出てくる領域など、そうないと考えられる。