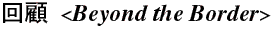
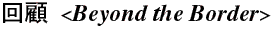
野田仁
これから報告されるサブ・セッションは、会議全体から見ると、二日目の午前に位置し、「イスラームの法と思想における領域の概念」と題されたセッション1の四番目に当たる。前日に続き、別会場においてセッション2が行われていたが、参加者は均等に分かれていたように見うけられた。当初予定されていた五名の発表者の内、最後のKAHERA氏に関しては、その不参加は既に告知されていた。そのことは非常に残念に思われたが、いざ報告を記す段になると、サブ・セッションとしてのまとまりという点では、年代順に発表が並ぶという結果を得て、必ずしも悪い面ばかりではないという印象も持つようになった。
先ず簡単に各発表の要点をまとめる必要があるだろう。なお、英文の表題、発表中の語句等は筆者が逐語的に日本語にしたものである事を注記しておく。最初に太田敬子氏の「初期イスラーム時代の移住とイスラーム化:アラブ=ビザンツ国境地域」である。ムスリムの移住とイスラーム社会の発展との関係に注目し、ビザンツ帝国と接する前線の地域アル=スグール(al-Thughur)の歴史に焦点を当てている。アル=スグールの歴史は、ビザンツによって七世紀から始まり、八世紀初頭からアラブ側が兵士を送りこみ、マッスィーサ、タルスースなどの都市の再生が見られた。特にタルスースには、多数の兵士、志願兵が移り、ムスリムの社会が形成され、ビザンツ軍との戦いに備えられた。タルスースは軍事的にも、また宗教的な意味でも、イスラームの前線たり得たのであった。ただし、経済的には大幅に出超であり、この辺りに氏はアル=スグールにおけるムスリム社会の限界を見出しているようである。最後に東方からムスリムが志願兵として多数移住してくることで、東方の文化が伝わると共に、相対的に土着の非ムスリムの人口が減少し、大規模な社会構造の変化につながったとしている。史料から導き出された、人口を示す数字は確かに、人口の推移を感じさせるに足るものであった。
次に中村妙子氏の「シリアの都市と初期十字軍間の領土問題:経済、政治上の支配を求めて」が続いた。太田氏の扱った時代から3、4世紀を経た、シリアのムスリムとその外敵である十字軍の間の「合意」(Agreements)に注目し、両者の関係を探ったものであった。その「合意」は、十二世紀前半に関しては、馬や金の手配を行う、貢物を行う、収穫物を分配するといった経済上のものが多く見られた。ある時期に、アレッポに関する「合意」が集中して見られることに着目し、アレッポの勢力減退に伴う「合意」の内容の変化を挙げる。アレッポにおけるザンギー朝の支配権確立により、十二世紀後半には、軍事的な協定が見られるようになった。例えば、ザンギー朝を共通の敵とするダマスクスとフランク軍が協定を結んだこともあった。さらにシリアの政治的不統一あるいはイスラーム勢力側の足並みの不一致、政治的な均衡を維持するためのジハード(Jihad)の乱用へと論は展開されていった。氏の発表においては表が活用され、「合意」の変遷を総体的に知ることに貢献したと言えるだろう。
続いてHamidullah BOLTABOEV氏の「中央アジアにおけるダール・アル・イスラームの概念の変動:ベフブーディーとフィトラトの作品において」である。中央アジアの歴史を振り返り、イスラーム化、とそれに続くアラビア文字の使用といった過程を確認した上で、後代のロシアの侵略とロシア化政策の影響を論ずる。それに関連して、ベフブーディーがその一部を担った、中央アジアのムスリムに与えられた「サルト」の名称に関する議論を紹介する。また、ガスプリンスキーに始まる新教育方式を、ロシア治下のムスリムを反ロシアに統合する作用を持ち、ロシアの圧力、ロシア化政策に対抗するものと見なしている。更に、そうした運動の系譜に連なるジャディード、フィトラトの作品群を時系列において見ることで、作中に見えるダール・アル・イスラームの概念が都市を単位とするものから、イスラーム世界全域へと、次第に広範になっていくことを指摘する。20世紀初頭に再び動的になったと思われた、中央アジアにおけるダール・アル・イスラームは、ロシア革命と、これら二人の活動家の死とにより、名実共に、限定的になったとし、ソビエト政権下での反イスラームのキャンペーンという現代的問題にも触れている。
最後にStephane DUDOIGNON氏の「北境を越えて:シベリア・ムスリムの歴史の全体像を求めて」でこのサブ・セッションは締めくくられた。先にBOLTABOEV氏も扱った「サルト」の名称に関する議論を取り上げ、そこから「シベリア・タタール人」について、その命名のされ方に注目し、十八世紀以降の民族としてのアイデンティティーを考える方法論を導き出している。その際には、内陸交易の中継点であったシベリアには様々な人々が移住し、混住してきた事実を踏まえなければならない。十七、十八世紀においてはその自己意識は曖昧なもので、むしろロシア人によって外から規定されるものであった。当初否定されたシベリア・タタールという名称であったが、十九世紀後半からヴォルガ・タタール人が移住してくることによって、彼らとの違いに基づき、この名称が自らを指す名として受容されることになった。また、同じムスリムである南方のカザフ遊牧民との間には明確な区別が存在していた。同時に、ロシア帝国の治下にあって、ロシア国会への参加、ロシア市民権の獲得が求められたこととも関連して、汎タタール意識のようなものが十九世紀末に生じていたことも指摘される。ヴォルガ・タタール人による教育もその名称と大きくかかわっていたようである。ロシア革命後もしばらく続いていたヴォルガ・タタール文語教育が、ソビエト政権により禁じられると、再びヴォルガ・タタールとシベリア・タタールとの意識レヴェルでの差異は大きくなり、現代においてもその概念は揺れている。
以上の四発表に対しては、各発表終了毎に述語、内容確認のための質問時間が与えられ、その後まとめて質疑応答の時間が設けられていた。だが、このスタイルには疑問も残った。勿論、各発表に対して平等に質疑の時間を与えるためには、このような形にせざるを得なかったのかもしれない。しかし、他のサブ・セッションも含め、後で答えるはずの質問に答える時間がなくなってしまったり、質問を後に回されたことで質問すべき事柄が曖昧になってしまったりといったことが起こったのは残念であった。BOLTABAEV氏の発表に際しては、質疑にあたり英露語間の通訳が設けられたが、時間の有効活用という点では多少マイナスになったように思える。
質問で思い出されるのは、立場の相違ということであった。即ち日本や欧米の研究者と、研究対象となっている当地出身の研究者の視点の違いといったほうがより正確になるだろうか。この違いを前提にしておかないと、議論はしばしば平行線をたどる。現にそういった場面は存在していたと記憶している。このことは、研究が、現代国家ないしは政治の枠組みから逃れられないこととも関連させて、考えを深めねばならないだろう。
続いて、サブ・セッションを通じて抱いた、ごく簡単な疑問について触れて行きたい。今回の会議は、フル・ペーパーの配布が義務とされている点を特徴とすると聞いた。このペーパーの役割についてはよく分からないところもある。当サブ・セッションにおいては、幸いにもそのペーパーに記された内容の殆どは発表内で扱われ得たが、無論全ての文章が読み上げられたわけではない。そのあたりに少し疑問を覚えた。また、参考文献ないし引用史料については各人の好みがあるのだろうが、明示されていたほうが、聞き手としてはより論が明確になると思われた。関連して、様々な専門分野から参加者が集まっているのであるから、ある程度以上の専門用語、固有名詞に関しては、説明を加えても良いのではないかという印象も持った。勉強不足を責められればそれまでなのだが。
最後に、このサブ・セッションを自分なりにまとめる作業を試みたい。折角各サブ・セッション毎に議長が置かれているのであるから、何らかの形で議長の総括が聞けると良かったと思うのだが、恐らく時間の関係で、そうした発言は聞かれなかった。従って、以下は筆者の個人的な理解に基づいて記される。
先ず、会議全体との関連を探る。タイトルである「Beyond the Border」に対して当サブ・セッションはどう答えたのだろう。一つの答えは、境界は甚だ不明瞭で不確かなものだということになろうか。しかし境界は決して存在しなかったわけではない。従って、境界に区切られる二者は必ず存在していた。その二者を分析するに際しては、単にA対Bというような二項対立の思考では物足りず、柔軟にして複雑な方法論が求めらることを当サブ・セッションは証明したと言っても良いだろう。
次にセッション1全体との関連はどうであったか。この問いを深めるためには、セッション1の全ての発表に立ち会うことが求められるが、筆者には残念ながら、セッション1を通観することはかなわなかった。そもそもダール・アル・イスラームとはどのように意識されるものか、について共通の認識がなければ議論は成立せず、セッション1‐1〜3では、まさにその根幹の認識にかかわる発表が行われたように思える。当サブ・セッションはそうした議論に続く、具体的な論証であったと思われるのである。当1‐4が残した課題を先に考えてしまえば、他者からの目、即ち非ムスリムの側からみたダール・アル・イスラームに関して議論を深めることではないかという気がする。自己意識には他者を鏡とする側面もあるのであるから、その視点を積極的に取り入れた上で、議論を差し戻していくことも必要になろう。いずれにせよ、サブ・セッション全体をテーマに即して概括するようなコメントが待たれる所である。
最後に、この1‐4というサブ・セッションをまとめるならばどのような言葉をあてることができるだろうか。前半二者の発表では、ダール・アル・ハルブの主な対象として、ビザンツ帝国、十字軍といったキリスト教世界をおいた。一方後半では時代を大きく下り、ロシア帝国を主に対象としている。この対比は更に、前半における領域に関する摩擦、後半における文化に関する摩擦という構図に置きかえることもできよう。後半のキーワードになるのは教育に代表される文化的な意味での対立、摩擦ではなかっただろうか。一方、ダール・アル・ハルブを対概念とする、ダール・アル・イスーラムの側から見た場合はどうであろう。そこには、イスラームの旗の下の統一を見せる太田氏、BOLTABAEV氏、決して一枚岩ではないイスラームを描く中村氏、DUDOIGNON氏といった構造が見えてくるかもしれない。勿論、発表で扱われた全てのダール・アル・イスラームを同一視できないことは自明である。各発表の論旨からも分かるように、ダール・アル・イスラームは、単にムスリムの社会といった一面的な理解ではなく、動的なものとして認識される必要があり、従ってダール・アル・ハルブも変化し、敵対勢力となる集団もまた変化してきたと考えられるのである。即ち、その時代、地域ごとに与えられた意味は異なっているはずである。
中央アジアに関する後半の二発表は、共にイスラーム世界の最前線としての姿を明確に示したものと理解できる。ロシアと中央アジアの関係は、同時代の大英帝国とインドの関係とも比較対照されるべきであり、例えば東南アジアのムスリムについても共通点あるいは相違点を考察することが可能になろう。そうした所にも、このサブ・セッションの発展の可能性を見出すことができるのである。
一方でイスラーム世界と非イスラーム世界の接触と、そこに生じ得る摩擦は現代的な問題でもある。例えばカフカースのチェチェン紛争などは良い例かも知れぬ。その意味ではダール・アル・イスラームは未だ動的であり続け、境界もまた刻々と変化しているものなのであろう。