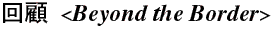
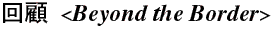
中町信孝
イスラームの領域概念として、世界を「イスラームの家(dar al-Islam)」と「戦争の家(dar al-harb)」とに区分するという世界観がよく知られている。イスラーム帝国たるアッバース朝において、早くも9世紀には各地に地方政権の成立を見、その後もイスラーム世界は多くの政権に分裂しつつも地域的な拡大を遂げたが、このような現実によっても上述の二項対立の世界観は根本的な見直しを迫られるにはいたらず、イスラーム世界としての統一性は保たれ得たとされる。しかし、現代の国際社会においてはイスラーム世界と呼ばれる地域は、近代的な意味での「国民国家」を含む様々な国家から成り立っており、「イスラームの家」と「戦争の家」とで全世界を区分する見方はもはや妥当性を持たなくなっている。本シンポジウム最終日に行なわれた総括討論において、第1セッションの総合議長である柳橋氏は、前近代における二項対立的世界観と、近代以降の国民国家的領域概念との間に横たわる断絶という命題を提示したが、そのような意味で、「イスラームの家から近代的領域概念へ」と銘打たれた本サブセッションは、イスラームの領域概念を扱う第1セッションの中でも最も問題を含んだ会であったと言えよう。
本サブセッションは、当初、4名の発表者による個別発表が予定されていたが、第4発表者のFrancois Georgeon氏が参加取りやめとなったため、当日は、Tetz Rooke、Iik A. Mansurnoor、Eugenia Kermeli-Unalの3氏が発表を行ない、それらを受けて質疑応答、討論が行なわれるという形となった。3氏の発表はそれぞれ、伝統的イスラームの世界観の変容と近代的領域・国家概念の形成を巡るテーマを扱っていたが、オスマン帝国崩壊後に新たな領域・国家概念の「創造」が必要であったシリア、13世紀以降イスラーム化が進み独自の領域概念を発達させた東南アジア、常にヨーロッパと境を接しイスラーム法による支配の正当化の必要に迫られていた16世紀のオスマン朝と、対象とする時代・地域は様々であった。以下に、上述のテーマに即した形でそれぞれの発表の概説、コメントを述べたい。ただし、本報告では論の展開上、紹介する順序は発表順とは変えてある。
第3発表者のケルメリウナル氏による"Custom Versus Theory: Ebu's Su`ud's Effort to Consolidate Shariah with the Ottoman Kanun on Land and Its Impacton Crete"は、オスマン朝がバルカン地方を併合する際に生じた土地所有および税制の問題を当時のイスラーム知識人がどのように解決しようとしたかを、時のシェイヒュル・イスラームであったエブッ・スウードが発布したカーヌーンナーメの分析によって考察したものである。異教徒の支配領域すなわち「戦争の家」を、武力によって征服し、「イスラームの家」に取り込むという当時のオスマン朝の歴史的状況は、初期イスラーム期と共通しており、また新規征服地を国家の所有地としてそこからハラージュを徴収するという法理論上の方策は、ウマイヤ朝期の国家的土地所有理論とも相通ずる。しかし、アブー・ユースフ等の初期イスラーム期の法学者があくまでシャリーアの再解釈によって問題を解決しようとしたのに対し、オスマン朝の法学者エブッ・スウードが世俗法をカーヌーンナーメの形で法制化するという手段を取っているのは、両時代の法学者の間にある大きな違いであると言え、興味深い。
とは言えケルメリウナル氏の発表からは、オスマン朝における領域概念は、初期イスラーム国家におけるそれを、ほとんどそのまま引き継いだものであるとの印象を受けた。ここではオスマン朝の領域概念は、伝統的イスラームの世界観に等しいと見なされており、「近代的領域概念」と言うテーマに関しては述べるところが無いように思われた。発表後の討論の際には「シャリーアと世俗法」という、イスラーム研究におけるもう一つの重要なテーマについて、多くの時間が割かれていたが、ここではそれについては触れない。
一方、第1発表者のルーク氏による"Colonial Borders Versus Natural Frontiers: History Writing in Syria After the First World War"は、第一次世界大戦後ダマスクスで出版された、ムハンマド・クルド・アリーの『シリア地誌』を中心的に扱い、シリアという国家が一つの歴史を共有するまとまりとして当時の知識人らによってどのように想定され、その領域がどのように形成されていったかを分析したものである。オスマン帝国による統治や植民地支配の線引きを経て漠然と認識されるようになった境界線が、シリアの自然国境として知識人により主張されるようになるという変容の過程は、同時に、シリア共和国の国民統合の過程であると言ってもよいだろう。特にルーク氏が中心に扱ったシリア北方のトルコ共和国との境界領域において、トルコ系住民が国境の北側に排除される一方で、アルメニア人、クルド人らが国境の内側に取り込まれたという指摘は興味深いものである(発表では時間の都合上、割愛されたが)。シリア北方の国境は、トルコとシリアの両共和国の国境であるばかりか、アラブとしてのカウミーヤの境界が重なり合う線でもあるが、ここにおいて非アラブであるマイノリティ集団をも国民として取り込む当時の知識人の態度は、第一次大戦後の現実政治を強く意識した結果であった。
ルーク氏の研究が、アンダーソンの『創造の共同体』の議論を援用しているのは明らかであろう。氏が提示したのは、まさにシリアにおけるアンダーソン的な国民国家形成の過程であり、ここには前近代的な「イスラームの家/戦争の家」という二項対立はすっかり影を潜めている。そのような意味で、ケルメリウナル氏が提示した、オスマン朝における初期イスラーム期から連続する伝統的な世界観との間には、大きな断絶があると言える。
第2発表者のマンスールヌール氏は、"The Impact of Territorial Expansion and Contraction in the Malay Traditional Polity on Contemporary Thought and Administration"と題し、東南アジア島嶼部・半島部でのイスラームの受容と領域概念の変遷を、マレー語、ジャワ語等で書かれた歴史的文献から考察した。マンスールヌール氏は、イスラームを受容し、「地上における神の影」としての王という王権神授概念を導入した支配者が、イスラーム法とマレーの伝統的領域概念とを折衷させた独自な統治概念を発達させていたと指摘する。そして、氏は明言こそしていないが、このような統治概念が現代東南アジアの国民国家に及ぼしている影響を念頭に置いていると思われる。これは、アンダーソンの言う「国民の創造」に対する現地研究者からの一つのレスポンスであり、植民地支配の時代より古い時代に遡りうるマレー世界の内在的な領域概念を提示したものと理解してよいだろう。
マンスールヌール氏の発表にも、ケルメリウナル氏の発表で提示された「シャリーアと世俗法(慣習)」というテーマが現れているが、マンスールヌール氏の言うところの、つまりは東南アジア史的文脈でのシャリーアとは、ケルメリウナル氏の発表でのそれとは若干ニュアンスの異なるもののように思われる。むしろここで注目したいのは、マレー的伝統を取り込んだ形でのシャリーアが、分立していた東南アジアのイスラーム諸政権によって、支配の正当化を図る道具として用いられたという点である。
ここで再び、上に述べた、柳橋氏の提示した命題に立ち戻ってみたい。ケルメリウナル氏の提示したオスマン朝の領域概念はあまりに伝統的であり、一方ルーク氏の描くシリアのそれはあまりにイスラーム的伝統から離れている。トルコとシリアとの間の地理的な近さにもかかわらず、両者の間の断絶はあまりに大きいように見える。しかし、両者の間にマンスールヌール氏の東南アジアの事例を置いてみると、前近代史と近代史との間に何某かの連関が見えてくるようである。すなわち、イスラーム世界の「辺境」と見なされる東南アジアにおいては、「イスラームの家/戦争の家」の二項対立的世界観は、実際には、分散したイスラーム諸政権の統治を正当化するものとして機能していた。そしてそのような領域概念はまた、近代以降の国民国家的領域概念とも親和性の高いものであった。
翻って前近代の中東地域を見るに、果たして当時の人々は二項対立的領域概念の他にはいかなる区分法も持ち得なかったのであろうか。例えばケルメリウナル氏は予め配られたハンドアウトにおいて、グルジアに対するカーヌーンナーメの例を挙げているが、グルジアはそれ以前、サファヴィー朝の領土であった。ここで報告者は、当時オスマン朝にとって、サファヴィー朝は「イスラームの家」の範囲内にあったのか、それとも「戦争の家」の一部と見なされていたのか、という素朴な疑問を抱いた。もしサファヴィー朝が「イスラームの家」であったのならば、グルジア併合に際してクレタの事例を踏襲したカーヌーンナーメが発行されたという事実は、当時の知識人が伝統的な二項対立とは異なる基準でもってサファヴィー朝を捉えていたことの証拠になろう。逆に「戦争の家」とされていたとしても、それはオスマン家の支配の及ぶ範囲を「イスラームの家」と見なすことに等しく、ここに現れる世界観はむしろ近代的な国家観に近いものと言えるのではないだろうか。ここにおいて、当時、「イスラームの家/戦争の家」という二分法は、すでに現実にそぐわないものになっており、それに代わる新たな世界観が成立しつつあった、という仮説を立てることも可能である。無論、当時オスマン朝領内に生活するすべての人々が、同じ世界観、領域概念を共有していたという前提は、慎重に避けるべきではある。
それでは、当時の現実に見合う新たな世界観、領域概念とはどのようなものであったのか、という問いに対しては、報告者は具体的な答えを持たない。しかし、このような問いにこそ、前近代史と近現代史との間の断絶を繋ぐヒントがあるように思えるのである。いずれにせよ、前近代史の研究者に対しては、イスラーム世界の統一性を重視するあまり、その内部での差異、他者観というものをなおざりにしてはこなかっただろうか、と言う批判が向けらる。歴史研究者は、イスラーム世界における前近代と近代との連続性に、より目を向けるべきであろう。