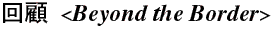
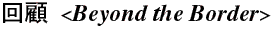
橋爪烈
京都国際会議初日(1999年10月8日)のSession 1-2は上記のテーマを掲げて行われた。Session 1で掲げられたメインテーマはThe Concept of Territory in Islamic Law and Thoughtであり、これに基づいて、イスラム世界の領土の概念をイスラム史の文脈の中で見ていこうという姿勢が打ち出されていた。発表者は東北大学のElmostafa REZRAZI氏、東京大学の柳橋博之氏、慶應義塾大学の奥田敦氏の三名で、発表題目はそれぞれ、"Iqlim and Political Identities as Established in Islamic Tradition"、 "Solidarity in an Islamic Society: `Asaba, Family and the Community"、"Two Dimensions of the Reception of Western Modern Legal System in the Territory of Islam"である。
三者の主張を紹介すると、まず、Elmostafa氏は、「イスラムの伝統に於いて、境界線というものが不明確であり、その分類が困難である」ことを主張し、その上で、地理学史料に見える様々な世界観からイスラム世界の領土概念を明らかにしようとしている。彼はまず、地理書の政治経済的必要性の理由として、ムスリム国家の領土に於ける徴税可能額の算定、スパイ活動、イスラム世界外部の軍事、経済的潜在能力の査定というものを挙げている。さらに、こうした理由から作成された地理書は以下に挙げる4つの文化的源泉、或いは見地に影響を受けているとしている。
まず、クルアーンとハディースを取り上げ、クルアーンには天地創造の描写が存在し、また、天界の層を7つとして描く場面もあって、地理書のみならず、神学、法学、哲学の分野に於いても、その世界観形成に非常に大きな影響を及ぼしていると述べている。ハディースに関しては、上に示した7つの天界についての思想を強固にするムハンマドの言及を伝え、これによってもムスリムの世界観がその初期からの伝統に影響されていることを指摘している。
次に、アラブ征服時代に、エジプトを征服したアブドゥッラー・ブン・アムル・ブン・アルアースの「世界はその形から5つの部分に分けられる。鳥の形を例にすると、頭、両翼、胸、尾である。頭は中国、右翼はインド、左翼はコーカサス、胸はメッカ、ヒジャーズ、 シリア、イラク、エジプト、そして、尾はアレキサンドリア以西である。尾の部分が最も悪い」という言葉を紹介し、この言及が初期イスラム国家の政治的関心を示し、領土概念が示されていると、位置づけている。
三番目に、地理書作成者の持つ文化的背景の違いによって、それぞれ独自の世界の分割、分類が(地理書の中で)可能となっていると述べている。例として、キリスト教からの改宗者の場合、その記述には黙示録的要素が示されていたり、ジャーヒズにはシュウービーヤ的倫理観が現れていたり、ということを紹介している。
最後に、アラブ地理書に於けるギリシアの影響とIqlimの語源についての議論が示されている。その語源をギリシア語のKlime(傾向)とし、その派生的意味として「地球の地域区分」とか「地方」と言う意味になったことを指摘している。しかし、ギリシアの影響と言ってもElmostafa氏が強調するほどの影響ではなく、氏の発表やレジュメを参照する限りでは、ギリシア以外のインド、中国、ペルシアなどの伝統も取り入れて世界観を示していると言った印象を強く受ける。さらに、ヤークートによるIqlimの定義を紹介し、文脈によってその意味が違うこと、その違いはIqlimと言う言葉が使用される時の社会、政治状況が影響していることを示している。
上記のことから、Iqlimは政治的に利用されることのない概念であり、どちらかと言えば、倫理的、宗教的な意味合いで用いられてきた、と結論づけている。
次に、柳橋氏は「dar al-Islamは定義上ムスリム共同体によって統治される」と述べ、そこから導かれる事として、その定義がムスリム共同体内外の他宗教との闘争の可能性を潜在的に秘めていると同時に、イスラム普及以前の部族感情に対抗するものであると見なしている。すなわち、ムハンマドの創始したイスラム教は共同体を形成し、そこでの支配原理として部族の掟を排除しようとするものであったと言うことを主張している。しかし、クルアーンにもあるように、完全な排除は達成できず、血縁や姻戚関係に基づく家族や集団の存在が認められ、世襲制度などに於いて、それは顕著であったとしている。しかし、全体として個人化の傾向を示していたとも指摘している。
柳橋氏はその議論に先立って、儒教に於ける人間関係を例示し、儒教社会が個人の関係で成り立っていたことを挙げている。その上で、イスラム世界に於ける人間関係、特に集団ではなく、個人間の関係を規定するものとしての幾つかの法律的制度を取り上げ、ムスリム共同体内の家族や社会のあり方を見ることを目標に定めている。また、イスラム法の文脈に於ける「家族」という概念の曖昧さを述べ、家族を維持するという事に関しては、妻の場合は婚約時の契約、子供の場合は相続法と言う具合に、家族を一体として見るのではなく個人の関係の上で述べられていることを指摘している。
一つ目の項目である個人的事柄を議論する前に、個人の関わりを規定する4つの法制度が示されている。walaの伝達、婚姻に関する後見、親族の扶養、財産に関する後見の4つである。
第一に、walaとは奴隷を解放した主人がその解放された元奴隷との関係を維持した場合に呼ばれるものであり、この関係は当事者同士だけでなく、両者の子孫に対しても継続して適用されたと説明している。このwalaは一族の間を移るものとされており、最終的にwalaを所有したのは一族の長老であったとしている。
第二に、婚姻に関する後見については2つのカテゴリーに分類している。一つ目は強制権を伴った後見であり、これは子女(後見を受けている未成年者)の同意無しに、婚姻契約を結ぶことができるものである。二つ目は強制権を伴わない後見であり、子女の同意を必要とするものである。強制権を伴う後見は前イスラム時代にまでさかのぼるアラブ社会の慣習であり、特に女子に対して絶対的な権利を有していたが、イスラム以降、次第に後見の範囲が狭められ、娘の父親のみがその権利を行使でき、一族の影響は受けなくなったと述べている。しかし、権利の枠が縮小されたとしても、原則的に部族社会の伝統であることに変わりないことも指摘している。
第三に、親族の扶養について、柳橋氏は4法学派とも部族社会の伝統を排除した法理論を展開していると指摘し、さらに、三つのカテゴリーに分類している。それは、直系の人々の扶養、傍系の人々の扶養、そして、遠い親類の扶養の三つである。このうち、傍系とは母方の親類(祖父母など)のことを指し、最後のカテゴリーに対する扶養は義務でないが、前2つについては複雑であったことを指摘している。さらに扶養の4つの関係について紹介し、母親と傍系の扶養について世襲関係の有無によって扶養の義務が生じたことを指摘している。
第四に、財産の後見については、未成年者に課される保護であったとしている。後見人としては父、祖父、裁判官、加えて、先に挙げた人々の指名による後見人が存在したが、母親が後見することもあった。また、孤児に対しても適用されるものであったとしている。ムスリム共同体に於いては、父親や裁判官が保護を代表する存在であった。
もう一つの項目として刑罰的責任のことを述べている。部族社会では、部族の成員が意図しない殺人や傷害事件を起こしたとしても、部族全体が血の復讐の責任を負うこととなっていた。しかし、イスラムの普及以降根本的変化が起こり、「個人の責任を重視」する傾向に代わっていったと説明している。その理由として、イスラム世界の広がりに伴い、部族成員の拡散が起こったこと、多くの人がディーワーンへ登録することによって、登録者同士の事件の場合、加害者、被害者双方の仲間が同時に血の復讐を行う者と受ける者になる可能性がでてきたからである、というJoseph Schachtの見解を紹介すると共に、柳橋氏独自の見解も示している。それは、血の復讐の責任が一種の保険として見なされなくなったからである、というものである。
以上のことから、柳橋氏はムスリム共同体とその法は個人の利益を守ることを目指すと言う傾向を有していたことを指摘している。また、以上の論は思想の分野のみの考察であって、現実世界との関わりを調べることが今後の課題であるとも述べている。
最後に奥田氏の発表を紹介すると、「国民国家にとって法の成文化は重要な課題の一つである」と言う前提を掲げ、西ヨーロッパがローマ法をモデルとして法の作成を行ったのに対してイスラム世界の法の成文化がどの様な形を取ったのかを調べることを目標に据えている。
まず、中東世界はローマ法を直接導入したのではなく、西欧というワンクッションを置いて導入した、と言う解答を示している。この西欧のワンクッションとは、ここではナポレオン法典のことを指している。その一方で、イスラム世界は伝統的に一つの政府と法によって統治されると見なされてきたが、この西欧型の法の成文化によってイスラム世界は元来の法体系を破壊され、西欧近代の法体系を受け入れることになったと、指摘している。奥田氏の論点は、シリア法とフランス法を比較し、イスラム法という理論の歴史的文脈に於ける現実状況の受容を明確にすること、その比較を宗教規範の点から取り扱うこと、そして、イスラム世界の法を議論することの三点である。最後の問題はイスラム法の歴史的文脈に於ける評価と未来のイスラム世界に於けるイスラム法の必要性を調べることに主眼を置いている。
まず、イスラム法とは神の啓示と預言者の言行が法源となっており、ここに教友たちの言行と4法学派のイジュマーなどが加わって形成されたものであることを述べている。しかし、オスマン朝崩壊後に生まれた統治国家による法の成文化、法典化を扱うと、ほとんどの国家が宗教と政治の分離を図っており、イスラム教の政治と宗教の一致という原則に反するものとなっている。従って、この場合の中東諸国による法制化はイスラム法によるものとは見なされない、と言う見解を示している。その一方で、こうした法制化に反して、結婚、離婚、相続などの分野では西欧近代法体系の進出は見られず、また、他の分野でもイスラム法の残存が確認されると指摘している。特に契約に関して、イスラムの契約は提供と受け入れ(reception)、そして、二者の同意が必要であり、また、二者の同時存在も必要なこととしているが、一方で、西欧の契約に関する説明が不十分であるため、イスラム法と西欧の法の違いがこの点では不明確である。
次にイスラム法の存在について、それが機能するかどうかは問題ではないが、実定法の中に残存することを指摘している。イスラム法と西欧近代法は完全に相反するものであると述べている。その根拠として西欧近代法は私的財産の不可視性、契約の自由、国民主権の三つに基づくものであるとする一方、イスラム法は人々が従うべき義務の制度であるとしている。
最後の指摘として、イスラムの領域(dar al-Islam)は多くの国家に跨って存在するムスリム共同体であるが、その結び付きは目に見えず、強固なものではない。その理由は、それを統治する政府が存在せず、内外的ビドア(革新)が存在するからである、と述べている。
奥田氏の結論を示すと、政府のない法体系は政治的分裂にも拘わらず、イスラム共同体の生き残りを示している。それはポスト国民国家の時代の方向性を示していると考えられるが、政府無き法体系は共同体社会の全成員に対して自制の重荷を課しているとも言える。
以上のように、三者の論点を整理してみたが、ここで少し考察を加えることにする。まず、このセッションのテーマである「イスラム世界の領土概念」とは異なった内容の発表が二つ存在することについて。最初のElmostafa氏はムスリムの領土概念を地理書から見出そうとしているが、あとの二人はイスラム世界、或いはイスラム共同体という枠組みを規定するイスラム法への関心を寄せている。Territoryとは「領土」、「行政区域」と言うように、実際の地域区分を示す言葉であって、法体系の存在する範囲というような概念的区域を示すものではない。奥田氏の発表はイスラム世界とされてきた地域による西欧近代法の導入を扱いながら、イスラム世界と外部との違いによって、イスラム共同体の輪郭をいくらか伝えているようにも思われるが、柳橋氏の発表は完全にイスラム世界内部の法の問題であり、本テーマからは外れていると見なさなければならない。セッション1のテーマに照らしてみてもそのことが言える。法や思想によるイスラム世界の規定がどの様に為されていたのか、それを明らかにすることを主眼に置いているので、このサブセッションの発表で最も注目すべきはElmostafa氏の発表であるといえよう。
さて、上記はテーマとの関連について述べたが、内容についてみると、まず、Elmostafa氏は地理書作成者の文化的背景やイスラム教の持つ(クルアーンなどに示された)世界観がイスラム世界の領土概念の規定に大きく関わったとしているが、これは地理書のみの情報から引き出された結論であり、いささか不十分に感じられた。と言うのも、Elmostafa氏はその論の最初で、哲学、神学、法学を挙げているように、これらの学問を担った学者達と地理学者達の文化背景が同じである場合も多数存在すると思われるので、彼らの世界観との一致、不一致を見ることが必要ではないかと考えるからである。
柳橋氏の論では法制度の説明に、ハナフィー派、ハンバル派、シャーフィイー派、マーリク派と、異なった見解を紹介しつつ行っていたが、印象として、一つの制度に関して運用に違いがあると言うことは一つの法体系が存在するという定義に反するのではないかと感じた。ハナフィー派内での規定、マーリク派内での規定と言う具合にそれぞれに法体系が存在するような印象を持つ。この場合、イスラム共同体は一つの法によって統治されていると言えるのであろうか?ハナフィー派の共同体、シャーフィイー派の共同体と各法学派の目に見えない共同体にムスリムは各自所属しているように見受けられる。法学ではこの様なことはどう説明されているのか、解答を期待したいところである。
奥田氏の論に関して、氏の発表時に一つ疑問を抱き、それについて質問を行った。その疑問を持った内容とはレジュメに於いて、「国民国家の理論による現在のイスラム世界の細分化が10世紀中頃のアッバース朝時代に始まった」という物である。これについて現在のシリア、イラク、ヨルダンというような中東の分裂とアッバース朝時代に起こった分裂ではその原因の性質が異なるのではないか、と質問したわけである。これに対して、奥田氏は分裂傾向の始まりがどこにあったかを考えるとアッバース朝期に求められるが、もちろん、その原因が国民国家理論ではない、と解答された。これについて、アッバース朝期の分裂に関しては本報告書執筆者の専門分野であるため、以後研究すべき課題として残しておく。
さて、セッション1-2全体を通して、このサブセッションの持つ意味を考えたとき、前後のサブセッションのテーマに照らし合わせると、いささか不十分であったと思われる。先程から述べるように、セッション1-1ではイデオロギーに見るイスラム世界の概念を、セッション1-3では近代的概念に於けるイスラム世界の規定と言うことをテーマとして掲げているわけで、それをつなぐ役目として「歴史に見る領土概念」と言うテーマが設定されていたわけであるが、イスラム世界の歴史的領土概念を明らかにした発表(ここで私が意味するのは年代記などの史料を使用した発表と言うこと)がなく、テーマと発表内容に乖離があったためである。もちろん、年代記史料のみが歴史ではないと言われればそれまでであるが、単なる感想でしかないが、年代記史料に見るイスラム世界の領土概念についての発表があれば良かったのではないかと考える。以上で、セッション1-2の報告を終わる。