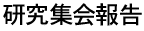
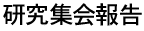
9月29日(土)、東京大学東洋文化研究所3階において、「西欧文化との接触」をテーマに3つの発表が行われた。30名近くの出席者を数え、興味深い発表に活発な質疑応答がなされた。以下にそれぞれの発表の要旨を抄録する。
宮井清一(建築史家)
北アフリカ、スペインの8世紀から12世紀の8棟の中世イスラーム建築について、使用されたアーチの分類、リブ・ヴォールト、廻廊、ミナレット、ドーム、モザイク、パラペットを調べ、これらの要素がスペイン、イタリア、フランスの11世紀から13世紀の15棟のロマネスク教会堂建築について、どのように表現されたかを説いた。特に、従来イスラーム建築の特色といわれる尖頭アーチについては、個別にその使用箇所について検討した。
富川倫弘(法政大学)
8世紀頃から13世紀中頃のレコンキスタまでイスラームの支配下に置かれたアルコスは、その後キリスト教の支配下で16世紀から18世紀まで経済的繁栄をむかえるものの、その都市構成の理念の中に他のアンダルシアの都市とは異なる部分が散見される。アラブの都市と比較することによって、アルコスの基盤となったイスラムの存在の有無を問うた。
サンタ・マリア教会にはミフラーブの痕跡がのこり、城塞もターイファの城であった。街の構成は、尾根に沿いながら褶曲する2本の主要街路とこれを結ぶ屈曲する細街路からなる。アラブの都市と比較すると袋小路は少ないものの整然とした構成が見られないことは共通する。また、邸宅の分布もヨーロッパ都市では集中傾向があり、アラブ都市では分散傾向があるが、アルコスは中間的存在である。
住宅については、中庭住宅であり、四辺を囲む部屋の列が2重になる場合と裏庭等第2の中庭を設けることに注目した。部屋が2重になり、縦長の敷地に適合する住宅はセビーリヤに見るようにアンダルシア的な傾向を示す。一方、裏庭は家畜や農作業の空間となりアグロ・タウンの性格を示す。しかしながら、街路に面する立面では、開口部が少なく、フェズなどイスラーム圏の都市と類似する。また、わき道に面する入口が多い点や、入口からの動線を屈曲させる点も、中庭を私的空間として認識するイスラーム圏と似ている。
鳳 英理子(筑波大学)
ガートルード・ベルについて、西アジアとの関わりを年代的に整理し、それぞれの著作の意義について検討した。彼女の研究には広域調査記録を含んだ紀行書、特定地域の建築研究書、ウハイディルを対象としたモノグラムと3段階の進展がある。
考古学者の態勢は19世紀の巨物選掘時代から、19世紀末から20世紀初頭の科学的綜掘時代へと移行し、さらに第1次世界大戦後、国家体制化の発掘の時代へと移行する。彼女は20代のペルシア旅行にはじまり、1900年から1910年にかけて紀行書および研究書の著述に没頭し、そして、第1次世界対戦中は英国外務省の補佐官となり、大戦後はイラク国王の顧問としてバグダードに留まり文化財保護と博物館設立に携わった。
なかでも、ウハイディルに着目したモノグラムは、評価すべき著作である。とくに、彼女の研究は19世紀の既往研究を踏まえて、パルティア建築、サーサーン朝建築、初期イスラーム建築へとヴォールト架構の体系化を試みている。そして、イーワーンの起源に関してもヒッタイトの宮殿遺構に存在する列柱玄関広間、ヒラーニからの起源を説いている。
彼女の西アジア建築への憧憬は、彼女が訪れた荒廃した遺跡群からも、感傷的なロマンティシズムに起因すると判断される。