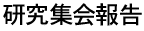
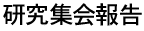
 ※PDFファイルを開くには、"Adobe Acrobat Reader" をインストールする必要があります。
※PDFファイルを開くには、"Adobe Acrobat Reader" をインストールする必要があります。
(右のボタンをクリックすると、無料ダウンロードのページにとびます。)
高見沢磨:(1)資金の目的は?質地の時期に季節性があるか。(2)土地所有権の根拠は?(3)お上からすれば、年貢の負担者は誰でもよかったのではないか。(4)貧民を働かせる人足寄場のような場があるから、貧乏人は怠惰だ、という観念があったのか?
答:(1)証文の文面では年貢納入資金のための質入れが一般だが、実際に、営業資金であることもあるが、あまり区別できない。12月の質入れが多く、生活費や営業資金を遣っていって最後に年貢が払えなくなるということになるのが普通のようだ。(2)土地は公儀のものという観念があり、将軍の統一的土地所有権が強調される。天保改革の水野忠邦がこの側面を強調して上知令を強行したとき、大名側は「先祖の功名によって」神君家康から領地を与えられたのに取り上げるのはけしからんと批判したとされ、「土地は公儀のもの」と言い切れなかったことがわかる。(3)村でも、検地帳が大切に保存されており、年貢負担者は誰でもよいと割り切ってはいなかった。(4)1830年代に「窮民」という表現が定着を始めた。そこに貧民は怠惰という見方がでている。二宮尊徳を含め、怠惰なものを働かせるいう発想ではなく、頑張って、上昇せよ、というもの。
菅豊:(1)質地請け戻しは、現在の日本の村にもみられるが、近世の慣行はいつごろ変化したのか。(2)検地帳や村請けの制度をみると、村の所有権のうえに個人の所有権がのっている、という理解でよいか。(3)永代小作はどのように理解したらよいのか。
答:(1)明治初期に、質地請け戻し慣行は転換したと考えている。(2)入会地に名請地があると村のものになり、村の惣有的傾向はあるが、惣有という考え方については、自分は懐疑的である。(3)永小作権の主張の発想が使用権的な方向ではなく、所有権的な方向で展開したのではと考えている。
柳橋:(1)売買というが、何を売ったと考えればよいのか。イスラーム世界でも、売買行為対して8世紀に、giveにあたるアラビア語(ata)が使われた例がある。値段は、どのように算定されたのか。(2)所有の主体は、村か個人か?イスラーム法には、先買権といって、近隣者が購入する権利が留保されている。村の他の成員に買い戻しの権利はなかったか。
答:(1)値段は、収穫高に相当し、10年サイクルで考えられていた。(2)村全体で、請け戻すやり方があり、その場合は、質地の売却者や親族が耕作者になる。
磯貝:質地に出した(売却した)土地を、売却者が借り請けることはないか。
答:借り受ける場合は、質地直小作とよび、借り請けないときは、別小作とよび、どちらも請け戻しがありうる。質地は、動産質とは違って、耕地を質取り側が経営し、収益をあげることができた。その収益が利子分と考えられ、利子が付かないのが普通だった。その収益計算が小作に出した場合(元金が)10年で回収できる程度に見込まれた(それでも請け戻しには、元金の返済が必要)。近世では公式には利子の上限は、最大は15%とされた。
磯貝:中央アジアの質地借り受けの小作料の例でも、借入額の15%であった。
岸本:中国でも、質地の小作料は、10-15年で回収できる率になっていた。
三浦:(1)質地請け戻しができるということは、土地所有権は、中国やイスラーム法のように、処分権と使用権に分かれていたのか。(2)所有権の根拠はなにか(中国やイスラーム法では、理念的には国家にある)。
答: (1)請け戻しは、土地を相手が利用していても利用していなくても、取り戻せた。所有権は、絶対的観念的なもので、内容についての議論・規定はなされていない。(2)太閤検地の時以後、検地帳に載ったものに作職を認めることになった。しかしそれだけで、百姓の所有権が確保できた訳ではなかった。近江などでは中世以来の証文での契約を重んじる土豪百姓の証文主義と、検地帳に載った上、「3代にわたって耕してきた」という小百姓の主張が対立していたが、やがて検地帳記載が権原として定着する。検地帳記載が定着するのは領主の政策ではなく、それを受け止める小百姓の自立闘争の結果として、検地帳記載と村での百姓の成員権をいう百姓株式との二重に規定されて所有権が根拠づけられたと考えている。近世後期には、勤勉による所有論が強まるが、その裏には、高利貸しや困窮者の切り捨てがあり、フィクショナルなものを含んでいる。
松原健太郎:(1) A とB の規範について、民事と刑事の区別はあるのか?A規範は、個体から出発する秩序、B規範は全体的利益から出発する秩序であるが、Aを前提としてB規範は成立しうるのだろうか。(2)現代日本の判決文も「・・・を相当とする」と結び、どうして相当かという理由は書かれていない。これも、「落着点」を探る裁判といえるだろうか。
答:(1)Bについては刑事を想定していない。個体間での利益の割り振りをめぐるロジックとして考えた。Bでは、全員が舞台にあがっているのが前提で、古代国家はBの純粋形。その後、中国では、国家がもはや経営しない状態での、AとBのアマルガム状態が続いており、今後もこの状態でずっといくように思う。(2)どの文化でも、「・・・に相当する」という説明の仕方しかできなくなってきている。中国の普遍化か。
岸本:生存権の主張も、B規範か?
答:生存権は、Aでは処理できない背理。
高見澤:(1)西欧では、慣習、一般原理、成文法の順で強い。中国では、慣習が弱く、これに相当するものは、「情理」という形を通じてしか表現できなかったのではないか。(2)落着点というのは、近しい人にとっては予想でき、内々で理解できるが、外部者にはわからない。現在の中国は、WTO加盟問題のように、外圧があり、外からみえているところで、落としどころを見つけることはできるのか。いま中国史上異常な時期にある。
答:(1)西欧では、慣習を既得権として、これをベースにできたのに対し、中国では、慣習と隔絶したところに政治があった。中国で「情理」の名の下に行われていることは、西欧法制史の初期に出てくる「法判告=法発見」と同様の操作だが、西欧ではその操作から慣習法が生まれたのに対して、中国では生まれなかった。その差異が面白いと思っている。(2)内と外の問題は、明清時代にもあったはず。一般には、もの覚えがよくなると、内々が出来なくなるので、情報化が進むとやりにくくなる。
柳橋:イスラームの統治がインドに及んだときに、統治・裁判の根拠となったのは、両当事者間の合意、法(但し慣習は含まない)、そして事実であったが、カーディー法廷は機能しなくなった。中国が新疆を支配したときは、どうだったか。
答:類似のことは新疆に限らず実は「慣行」あるいは「悪俗」をめぐって中国の全地方で起こっていたことであり、そしてそこでも統治者の理念を強行適用することはなされなかった、むしろ「人情」の名の下に事実的に当事者達の合意が参照・尊重された。相手ベースの裁判をやっても、うまくいったときに、「私のおかげです」といえばよかった。
松原:A規範とB規範は、非対称ではないか。
答:Aの花束がBと考える。あるいは、AがおかずでBが弁当(全体)。Bは、人々が抱く規範ではなく、現実。
三浦:実際の個々人が見えるのは、村のような全体の一部であり、B規範となるべき全体というのは、実際には見えようがないのではないか。
答:B規範が実現されているかどうかは、誰にもわからない。どんな規範であれ、一番上はみえない。現にあるものを、B規範の実現状態と考えるかどうかの問題である。
田口宏二朗:中東で徴税請負(イクターやプロノイアを含め)がよく見られるが、徴税の中味も請負者が決められるのか。
答:徴税請負や小作関係が幾重にも覆い被さっていても、実際に小作料を収めるものが納税者となる。ハラージュの場合、税率は20%に決まっている。
寺田:耕作者が帰還した場合について議論しているのは、フィクション(仮定)の問題か。
答:Johansenは、実際に帰還した例が文書にあると述べる。イスラーム法では、時効による所有権の消滅を認めていないので、しつこく議論をしている。
寺田:まるで、ステータス(土地概念区分)のころがしのようだが?
答:『ブハラ客人記』では、所有権の破棄を認めると、恣意的な接収につながると考えた。著者のルーズビハーンは、接収の根拠となる「君主は全ムスリムの監督者(ナーズィル)」というイブン・マーザの文言を、削っている。
三浦:接収の条件は、所有者・税納付者が相続人を残さずに死去した場合となっている。イスラーム法では、直系卑属以外の親族にも相続権が認められているので、まったく相続人がいない場合はありえなかったのでは?
答:実際には、所有者が耕作してハラージュを払うという状態ではなく、小作人ばかりであった。イブン・ヌジャイムは、「所有者の死によって」接収が可能であると、恣意的な引用によって、論理を改変している。実際には、所有者が逃亡していれば、これを適用しても問題はなかった。
岡:法と所有に関する意識について、ホアン氏(Philip Huang)のように、「法に基づいて権利を保護する裁判」が行われていたという見解について、どのように考えるか?
岸本:まず、史料の問題として、民事的訴訟における地方官の判語(判決)のなかには、ほとんど法の条文が引かれていないので、その判決を法に基づいたものとみるか、常識に基づいたものとみるかの判断は難しい。第二に、論証法の問題だが、ホアン氏は案件全体の何十パーセントが法に基づいた判決だったというような、統計的な論証のしかたをするが、問題はそうした割合の多寡にあるのか。当時の地方官のなかには、裁判における最適のバランスとして「法が四分、情が六分」といような言い方があるが、なかには、「法が九分」であるべきだと考える地方官もいただろう。その場合も地方官は「どの程度法を用いれば最適な結果が得られるか」という考え方をしているのであり、法よりも高次の常識判断が優越するこうしたやり方を「法に基づく裁判」といえるかどうかということだ。
高見澤:寺田氏は、納税は権利と余り関係ないとされたが、磯貝報告では、納税をすることが権利保証に役立っている。この違いについて?
寺田:来歴が怪しければ、納税は重要になる。もっともらしさは証として使えるが、その程度。
磯貝:民間人同士の争いであれば、文書と妥当とみえる証拠で決まる。しかし、原告に挙証責任があるので、双方が証文を出し合って不透明になることもある。
岸本:公証の仕方については、もっと議論があってよい。
三浦:(1)国家が、税を賦課する根拠はなにか、納めることの見返りはなにか。(2)西欧では、中世と近代の境目は、暴力と結びついていた所有権を、暴力から切り離し私法の世界においたことにあるという。これと対比すれば、中国や日本や中央アジアでは、暴力による所有権の侵奪に対して、どのような対応をしたのか。
小谷:司法作用と国家との関係が重要ではないか。イスラーム法世界では、法曹legal professionが、国家と距離をとり、国家から自立し、権力はそれをどう突き崩すかに腐心していた。中国と日本では、民衆と法曹をつなぐものがでてこない、という印象を受けた。西欧では、コモン・ローやイタリア公証人などの役割が問題になる。
白川部:領主は、どんなに小さくても領主で、力をもっていた。法には、一時しのぎの法と永代の法とがあり、これが矛盾することもあった。
寺田:(白川部報告に関して)日本中世の地おこしのような、土地と耕作者の関係は、近代に至るまえに、近世の名請地のような過程がはいることがわかった。百姓株式論は、継承ができない状況で、原初的な条件として想定されたのか。
(磯貝報告について)この国(イスラームの国)は、司法の世界だという印象を受けた。波及する領域を予測して、legal professionが議論を組み立てている。しかし、なぜ、legal professionがでてきたのか、その理由をどう説明するのだろうか。
(三浦の質問について)権利者は、自明のこととして、税糧を負担していた。出発点として権利を設定する議論は、出発点にはなにもなくても、最後のところで権利が認められればよい。皇帝の土地だから、国家を排除するような私的土地所有の論理はなく、国家にその根拠を問うこともない。暴力については、余りの弱者では誰も訴えを聞いてくれない、ということはあるば、耳を傾けさせる程度の力をもっていれば、十分にやっていけた。
磯貝:研究の現況としては、まず制度のあり方をおっかけるしかなく、今後文書を系統的に検討することができれば、細部が明らかになるだろう。権力と法曹との関係では、君主といえども、イスラーム(法)に反したことはできないし、すると周りにしめしがつかない。とくに、シャイバーニー・ハーンは、サマルカンド周辺だけを支配し、他は王族の支配下にあったので、ウラマーの評判は大事であった。税に対しては、征服ともにハラージュが賦課され、ハラージュは強制しえた。ハナフィー派には、軍隊を維持するには、ハラージュが必要で、ハラージュを納入するのは農民であり、農民は、これを保護する軍隊を必要とする、という説明の仕方があった。
(以上、文責三浦)
「中すれば吉?」