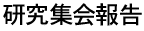
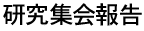
6月30日に行われた第5回「地域間交流史の諸相」研究会では、日本(博多)・ヨーロッパ(ルアン、ボルドー、ナント、マルセイユ)・中東(バンダレ・アッバース)という3つの地域の港町について、その立地条件、港湾施設の特徴、公的施設(市庁舎、税関、中央政治権力の拠点など)、宗教施設(寺院、教会、廟など)、商業施設(市場、倉庫など)、娯楽施設(酒場、伎館など)の位置と分布、諸「民族」集団の役割と居住地域の分布などが報告され、各地域の港町に見られる共通点と相違点が議論され、各港町の背後にある「地域文化」の特徴を明らかにすることが期待された。
羽田報告では、地理的諸条件を考察する際に海と後背地を視野に入れることの必要性を説いた上で、バンダレ・アッバースの港市としての好条件と悪条件が指摘された。好条件としては①ペルシア湾がモンスーン風、送風流の影響下にあるため、航海に都合の良い条件が備えられていること。②海の深度が浅く、比較的大きな船も停泊が可能であり、またバンダレ・アッバース付近には大きな島が3つほどあり、それらが風を遮る役目もしていること。③イラン-インド亜大陸(特に北部)との陸上交易の難しくなる冬期に於いて、陸上の代わりに海上ルートが用いられたこと。④ペルシア湾のイラン側のみならず、アラビア半島側の物産の集積港としても機能していたこと。一方、悪条件としては①気温、湿度が非常に高く、また雨が降らないことによる生活用水の不足。②山脈がちな地理条件から、大規模な農業は無理であり、特産品によって繁栄する事は難しかったであろうこと。③消費地から遠く(例えばバンダレ・アッバース―イスファハーン間は35から40日の日数を要した)、他の地域、都市との連絡は容易くはなかったことの3点が指摘された。この中心地との交通に関しては、家島彦一・上岡弘二による『イラン・ザグロス山脈越えのキャラバン・ルート』(東京 : 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所 , 1988)も参考になる研究の1つであろう。
次に略史としてホルムズ王国の成立まで遡っての説明がされた。このなかで氏は略史のために引用した史料が一部を除いてヨーロッパ史料であり、バンダレ・アッバースについては史料的な制約が非常に厳しいことを述べた。ペルシア語史料では軍事行為に関する記述はあっても、港のトポグラフィーを理解できる記述、その生活ぶりを示す史料は殆どないということである。
本題の空間構造に関しても、氏は現在バンダレ・アッバースに関しての考古学的調査はされておらず、現在の地図等からも復元することが非常に難しいという研究の現状を述べられた。それを補うために氏が多用されたのがケンペルなどヨーロッパ人の旅行記に見える絵画史料であり、以下の4点が指摘された。①非常に弱い市壁があり、有事の際には町の北東に設けられた城砦に逃げ込んでいた。②ヨーロッパの東インド会社の商館が3つほど海岸線上に並び、その中で18世紀半ばまでペルシアの最重要貿易相手であったオランダの商館が或る時期に移動をしている。③人々は夏には厳しい暑さのために山の方に移動をしており、町の人口は半分ほどになってしまう。また有力商人としてはインド系が多く、ペルシア商人、アルメニア商人などは本拠地をラール、或いはシーラーズに持って、シーズン以外は町を離れており、定住民は非常に少ない。④キリスト教会は無く、インド系宗教施設は市壁の外に設けられていた。
バンダレ・アッバースの都市空間について、主要な研究のひとつにGunther Schweizerによる Bandar 'Abbas und Hormoz Schicksal und Zunkunft einer iranishen Hafenstadt am Persischen Golf (Wiesbaden, Dr.Ludwig Reichert Verlag, 1972)がある。ただし、この研究は1960年代の統計、測量を基にしており、17世紀の都市空間に関しての記述は殆ど無い。また,今回は確認できなかったが,ペルシア語でのバンダレ・アッバースに関する研究が幾つかあるということは四日市康博氏から助言頂いた。
上に述べたように、多くの住民は交易のシーズンのみにやってくる商人であり、有力豪族、貴族も存在しなかったバンダレ・アッバースは都市としては成熟しなかったのではないかという指摘がされた。その一例としてサファビー朝陥落の際には町としての意思表示の無いままにアフガン勢力のラールに組み込まれてしまう。サファビー朝、特にアッバース一世は絹の独占貿易を行うなど、交易に対して非常に関心の強い王朝であり、バンダレ・アッバースはその意味で王と宮廷の人々の交易港であったという氏の見解が示された。更に、王朝権力の減退に伴い、道の安全確保がされなくなり、また交易への欲求が低下するとその重要性は著しく落ちていったことからも王朝主導の港であったことが確認できるであろう。以上のことを踏まえると、結論としてバンダレ・アッバースは王朝権力により作られた港であり、それ故に発展したという結論が提示された。
港に関してはその役割の面から「輸入港」、「輸出港」、「中継港」の大きく3つに分類できると思われる。私が今回の報告から察する限り、バンダレ・アッバースはその自然地理的な条件から「輸入港」の要素が強かったのだろうと感じた。つまり、港の立地条件として周辺に特産品が無く、また生活用水も不足しているという状況は「輸出港」,「中継港」として非常にマイナスなものである。それにもかかわらず、ある時期にバンダレ・アッバースがヨーロッパやインドとの貿易で「輸出港」としてペルシア湾を代表する港になり得たのは、如何にバンダレ・アッバースがサファビー朝による国家主導型の港であったかを強調していよう。更に興味深い点は、そのサファビー朝が決して(東南アジア海域に成立した国家モデルとして近年議論される)港市国家のような海上交易に重点を置いた国家ではなく、基本的には陸上の領域国家であったという点である。このような陸上の領域国家が積極的に海上交易に参入しようとした際の港町がどのようなものであったかについての議論は従来殆どなされなかったのではないだろうか。その点でバンダレ・アッバースは非常に興味深いモデルケースとなるかもしれない。
(文責:鈴木 英明)
中世の博多は、港湾都市・商業交易都市・政治都市(鎮西探題、九州探題が置かれた)として発展し、また、形成時期が早く、当時の港町とくらべて大規模であり、海外との交易の窓口であること、これらをふまえた上で、佐伯氏は博多が持つ中世都市としての要素を具体的に示された。
博多は自然地形的に見て二つの部分に分かれており、ひとつは古くから発展した博多浜と新興の息浜(おきのはま)から形成され、いわば、双子都市であった。博多の自然地形的な面から見た港湾としての魅力もさることながら、大宰府の外港であったことも11世紀後半には港町として発展をはじめていることの要因である。
現在の福岡の町並みが豊臣秀吉による「太閤町割」(碁盤の目状の街区整備だった)を基礎としており、十分な文献史料も無いため、中世博多の港の位置や市街構造を明らかにするのには困難が伴う。このような中で、考古学調査の他、「聖福寺古図」、「承天寺古図」のような絵画史料の存在は非常に重要である。もっとも、一部ではT字路や、斜めの小道など、中世的な市街構造跡が見られることが、翌日の現地調査からも明らかになった。特に、聖福寺周辺あたりでその面影が良く見て取れる。また、古くからある博多浜部分に、寺院など公共施設が集中している。考古学的調査から、中世当時の海岸線の位置や、住居、倉庫の遺構からそれらがどこにあったかが判明している。
博多は大宰府の外港として古くから公権力と関わってきたが、中世には鎮西探題、九州探題が置かれた。南北朝以来、興味深いことは、博多は二つに分かれている博多浜と息浜、それぞれ、支配勢力が異なるという二重構造を持っていることである。博多浜は探題、宗氏、大内氏など支配が点々とし、息浜は大友氏に一貫して支配された。
宗教施設として、博多の総鎮守としての櫛田神社の他、聖福寺、承天寺のような禅宗寺院も重要である。特にこの地の禅宗は鎌倉禅、京都禅と並び、博多禅として、日本の禅宗信仰に大きな役割を果たした。また、禅宗僧侶が通訳の他、直接間接に貿易に関わり、その円滑化に重要な役割を果たしたことが確認された。
また、当時の海外の窓口である故、11世紀後半以降、博多に数多くの外国人が居住していたことが、考古学史料の発掘(中国人の名前を記した墨書陶磁器の出土)から分かる。13世紀、日本に帰化した宋人としては、承天寺に寄進をした謝国明が有名である。帰化人は婚姻や、寺院への寄進を通じて、現地社会にとけ込んでいった。
質疑に於いては、博多浜、息浜の違い、徴税などの公権力との関わり合いなどの質問が出された。また、現在、唐人町とよばれる地域は慶長・文永の役の際に連れてきた朝鮮人を住まわせた町であることが明らかになった。
佐伯氏の発表では、「現地」の強みを強く感じた。文献史料のみならず、考古学的な成果も可能な限り取り込まれており、それが、見事に相互補完しているのである。
また、個人的には博多が博多浜・息浜という二つの部分から構成されており、それぞれが別の勢力に支配されているのに大変興味を持った。そのことがどれだけ、それぞれの浜の発展に関係したか、「浜意識」のようなものがあったのか?興味が尽きない。この「浜」の下にまたそれぞれ「流」という街区、さらには唐人街のような外国人居住地域も存在するわけであるから、余計に複雑である。これらの「まち」と公権力との関係を明らかにするのは史料の欠如から、難しい面を伴うというが、是非、今以上の具体的な事例を提示していただきたい。
(文責:阿部 尚史)
フランスの4大港町(ルアン,ナント,ボルドー,マルセイユ)の成長過程と空間構造をテーマにした深沢報告では、まず、以下の3つの観点から問題設定がされた。①都市と港湾の関係性②市壁の拡大過程から見た都市成長と市街構造の関係性 ③都市成長と商業発展からみた港町の固有性。
まず、中世から近世にかけての都市形成が市壁の拡張を特徴とするという視点から、四都市の市壁の拡張過程が示された。また、市壁の構造から開放型と閉鎖型の2つの類型が提示された。マルセイユは開放型、それ以外は閉鎖型である。閉鎖型とは市壁により都市と港湾が分離されてしまう型である。港と都市は市門で結ばれ、市庁舎はやや内陸側の都市機能の中心部に位置し、河口内港に一般的な形態である。一方の開放型は市壁が港まで包摂するため,港湾部に障壁がなく,都市と港湾の一体化が見られる。この場合、市庁舎は港湾に直面,または近接して立地する。沿岸岸港に一般的な形態である。
近世都市から近代都市への変容は、都市改造と市壁撤去に象徴される。従来、近代的都市形成は国家主導によりおこなわれ、市政体・市民は都市改造に保守的であると言われてきた。これに対し、深沢報告は港町における商人層と市政府の役割は如何なるものであったかを再考証する必要性を唱え、都市改造のイニシャティヴにおける市政体,市民の複合的な貢献という視点が提示された。例えばナントの場合、商人たちが多く居住していた城外区の港町とその後背地が都市改造の中心地であったことから分かるように、最も整備された新市街(“beaux quartiers ”)は貿易商人の居住地である港湾地区の周辺であった。つまり,港町の発展に際しては商人層が決定的役割を担っており,従来重視されてきた国家・官僚・貴族の役割はかなり相対化するのではないだろうかという指摘がされた。
港湾の機能分布と市街構造について河口内港の一般傾向として、古代市壁内には領域支配の拠点機能(司教座教会,司法機関,国王官僚府など),中世市壁内には自治都市のコミューンや市庁舎,取引所,市民生活の中心である市場など,近世市壁内には修道院,工業施設,そして城外区には救貧院などのその他の多様な施設、というように市壁と都市の機能分布の間に相関性が見られる。またsegregation (分離居住)の有無に関しては,一定の居住分離傾向として貴族,官僚,聖職者は内陸側に居住し,商人は港湾側に居住するという点は指摘できるが,「修正主義史観」の新エリート論的な、両者間での階級闘争的な面は無く,市街構造が両者の融合を表現しないことは明白であるという。
結論として17,18世紀の港町では、領域性としての面(国王官僚府,司法機関,司教座教会,修道院),局地性としての点(市政府,市広場)、拡散性としての線(商業,港湾)という都市空間構造の三次元の関係性において,線の優越性が高まった(=商人層の社会経済的台頭)時期であり,結果として面,点との関係構造を変革した。そしてこれがフランス革命期の市政革命であったのである。
氏の報告で他の2報告との違いが際立っていた点は、4つの港町のうちマルセイユを除く3港が河川港であった点である。特にルアンに至っては海から100キロ以上も遡る地点に存在した。深沢氏の訳された『ヨーロッパと海』(ミシェル・モラ・デュ・ジュルダン著,深沢克巳訳 叢書ヨーロッパ,平凡社 1993)でも指摘されているように、ヨーロッパ世界の1つの特徴は幾つもの大河川が沿海と内陸との交通を容易にしているという点である。これら河川港は、氏が報告の中で指摘しているように、海,川,陸の3つの要素が共生するポイントとして,港そのものについて考える際に非常に興味深いものである。報告の中で、ボルドーなどは港湾機能を下流方向に移転したということが言及されたが、インドのグジャラートにある港町スーラトは17世紀にイギリス東インド会社の拠点として大変に栄えたが、現在では泥土の堆積のために船が航行することはまず不可能である。河川港の場合は川幅の問題もあるだろうが、泥土の堆積などのように自然地理環境が変化してしまった場合、どのようにして港としての生き残りを図るのであろうか。また,河川を利用することで商品が海外から内陸地へ流通する際,そしてその逆の際のネットワークはどのように変化するのであろうか。沿海部に港が位置した場合の状況との比較という点で非常に興味深い問題である。
(文責:鈴木 英明)
今回で5回目となる当研究会では、黒木英充氏の司会進行のもと、羽田正氏がイスラムの港の事例としてバンダレ=アッバースを、佐伯弘次氏が日本の港の事例として博多を、深沢克己氏がヨーロッパの事例としてマルセイユ、ルアン、ナント、ボルドーをそれぞれ取りあげて発表した。今回の共通テーマは「港町のトポグラフィー -港湾施設と市街構造の比較史的研究」であり、それぞれの発表では、各港市の港湾施設および市街構造が歴史的推移に従ってどのように変遷していったのかという点が特に意識された。(それぞれの発表内容に関しては上記の報告を参照。)その後、各発表の相互比較を通じて浮き彫りにされた問題点について出席者を交えて質疑応答および討論がおこなわれた。
まず、港における文化の異なる者どうしの紛争や諍いの調停・仲裁はどのようにおこなわれたのか、公権力はどの程度介入できたのかという問題が提起され、イスラム、フランス、インド、中国などの事例が紹介された。さらに、イスラム世界でシャー=バンダルと呼ばれる港湾管理者の問題、軍事施設や検疫・税関など交易管理施設の問題にも論及された。これらはいずれも港社会の公権力支配に関わる問題であり、最終的には、港市社会と公権力がいかなる関係にあったのかという問題に行き着く。
また、深沢報告ではフランスにおいて公的施設と並んで司教座教会が古くから市街の中心地(古代市壁内)に位置していたこと、佐伯報告では博多において博多浜の市街形成が寺社を中核とするものであり、新興の息浜(おきのはま)の発展も同様であったことが指摘されたが、質疑応答では、これらを受けて、インド洋世界におけるヒズル廟、中国における馬祖廟などの例が提示され、港市における宗教施設、いわば港社会の「信仰の場」「祈りの場」が都市形成上どのように機能したのかという問題が提起された。
つまるところ、これらの議論は、港湾都市の市街構造のうえで中心部に位置した公的施設、宗教施設の問題に収斂される。言うまでもなく、港市社会は多種多様な人々が集散する共生の場であり、公的施設、宗教施設は港社会内の秩序維持や外部権力との権益調整をおこなう役割を果たした。これらの施設が都市形成上、常に中核に位置していたのは、港市社会の存続の如何が公的施設、宗教施設に直接左右されたからであろう。ただし、時間の都合上、港市社会と公権力の支配力のバランスがどの程度のものであったのかという点にまで踏み込んでの議論はなされなかった。さらに、ひとくちに「公権力」といっても在地権力や中央権力など様々で、時には港社会を維持する商人集団までもその範疇に含まれうる。それらが互いにいかなる関係にあったのかという「公権力の多重性・多層性」の問題については議論の余地を残したままである。また、港市の市街構造の段階的発展において商人層がその原動力となったことは、いずれの報告においても異なるところはなかったが、惜しむらくは、総合討論において商業施設と港市社会・公権力・宗教教団の関係に関する議論がなされなかったことであろう。
総合討論の最後には、「港市とはいかなる形態をもったものなのか?」という、一言では言い尽くしがたい報告者泣かせの疑問が呈されたが、ある意味、この質問は今回の研究会では欠落していた重要な問題に直結するものであった。すなわち、港市の性質と機能は、むしろ内部構造よりも、自然環境、政治的パワーバランス、後背地やルートとの繋がりなど、取り巻く外部環境によって定められる部分が大きく、港市のトポグラフィー(港市の市街構造)といっても、その港が積出港collecting portか、中継港transit portか、国際貿易港emporiumかによって、大きく異なってくる。したがって、港市の市街構造と都市形成の比較をおこなうにあたっては、外部環境をも含めた港市の性質・役割の特定と比較が前提として無ければならない。その意味では、上記の質問は、今回の議論のメタ・テーゼとも言える重要な問題意識を含んでいるといえよう。
なお、研究会の後におこなわれた懇親会、翌日おこなわれた中世博多市街の巡見においても、適宜、研究会での議論を補足する貴重なご意見を伺ったので、この場を借りて報告したい。例えば、城塞と防護壁の問題。研究会においては、フランスにおける英仏海峡周辺と大西洋沿岸では軍事的緊張度が異なるため、軍事施設の配置状況に違いがあることが指摘されたが、日本の港市でも後期倭寇発生以前と以後では、海に対する防護意識が全く異なることを神戸女学院大学の真栄平房昭氏から伺った。この点、インド洋世界の港市においても同様であり、ヨーロッパの進出以前は、港市の防護壁(あるいは同様の役割を果たす自然要害)のベクトルは内陸に向いていたが、ヨーロッパ進出以後、各都市で海に対峙する形で要塞が建設されるようになる。空間軸・時間軸における海域の政治・社会状況の変化が港市の防護意識に直接反映している点で興味深い。また、巡見では聖福寺や承天寺などの禅寺が「綱首」と呼ばれる在日宋商の寄進によって建立されたとのご解説をいただいた。その場合、寺院は商人にとっての「信仰の場」であり、同時に当地での商業活動の後ろ盾となる存在、ある意味、交易活動の拠点とも言えた。(禅寺が対外交易を営んでいたことを示す有名な例として、「板渡し墨跡」や「新安沈没船の木簡」などが挙げられる。)他方、中央や在地の公権力は禅寺を外交活動の実務機関として利用し、一方で対外交易の拠点ともした。そういう意味では、聖福寺や承天寺などの博多の禅寺は単に宗教施設として片づけられるものではなく、公的施設、商業施設としての面も合わせ持つ多面的な機能を有していたことがわかり、公的施設、宗教施設、商業施設という単純な分類に基づく検討がどこまで有効であるのかということを痛感させられた。また、宗教教団と商人と公権力の関係という問題は、イスラム世界における商人のワクフ設定と公権力、中国における寺院・道観と商人・公権力の関係など、日本史だけにとどまらない問題であり、地域間交流とも少なからず関係してくる。今後、各分野の成果を持ち寄り、討議されるべきテーマのひとつであろう。
(文責:四日市 康博)
「地域間交流史の諸相」研究会 博多巡見報告
・巡見日 2001年7月1日
・巡見地域 博多
・参加者(敬称略) 阿部尚史(東京大学大学院修士課程)、荒木和憲(九州大学大学院修士課程)、伊藤幸司(日本学術振興会特別研究員)、大石高志(東京大学東洋文化研究所非常勤研究員)、太田啓子(お茶の水女子大学大学院博士課程)、栗山保之(日本学術振興会特別研究員)、黒木英充(東京外国語大学)、西園寺彩子(イスラーム地域研究第5班事務局)、佐伯弘次(九州大学)、鈴木英明(慶応大学大学院修士課程)、高橋公明(名古屋大学)、長島弘(長崎県立大学)、羽田正(東京大学)、原口泉(鹿児島大学)、深沢克己(東京大学)、真栄平房昭(神戸女学院大学)、森平雅彦(日本学術振興会特別研究員)、四日市康博(早稲田大学大学院博士課程)
・巡見目的 今回の共通テーマである「港町のトポグラフィー -港湾施設と市街構造の比較史的研究」の一環として、中世博多の道・堀・浜跡や公的施設・宗教施設・商業施設跡などを実際に辿ることによって、佐伯報告に取りあげられた中世・近世博多の市街構造および港市機能の変遷を確認する。なお、随時、博多の都市形成に大きな影響を与えた歴史的遺構・遺物を実見する。
・報告
朝10時、盛夏を思わせるほど強い日差しさす晴天のもと博多駅に集合した一行は、まず、博多の町を北西に進み、万行寺の南にある小さな駐車場に着いた。そこでは、万行寺境内と駐車場の境として大きな段差が見られた。この段差は戦国時代に自治都市であった博多の南方の要害として築造された房州堀の遺構の一部であるという。この堀の存在は近世から明治期にかけての絵図・地図にも見ることができる。『筑前国続風土記』によれば、元龜天正のころに臼杵安房守鑑?が掘らせたとも、それ以前、大内家守護の時代からあったものを臼杵氏が補修したとも伝えられる。房州堀の名はこの臼杵安房守にちなみ、幅は二十間(約36メートル)で石堂川につづいていた。房州堀は明治時代までその景観を残していたが、明治二十二年(1889)の九州鉄道開通に伴う旧博多駅設置によって大きく景観を変え、その後の都市開発により我々の訪れた堀跡のみが地上で確認できる唯一の痕跡となってしまった。この堀は近世博多の南の外郭に該当し、現在の博多駅は中世・近世の博多市街の外である。この先、我々はいよいよ中世・近世の博多市街に足を踏み入れることになる。以下、巡見の報告をおこなう前に、博多の都市形成について大まかに説明しておく。
博多はもともと博多湾岸に形成された北部・中央部・南部の三列の砂丘から成っていたという。後に中央と南部砂丘が博多濱、北部砂丘が息濱(おきのはま)となる。街区と呼べるものが出現したのは8世紀であり、南側の砂丘、すなわち博多濱南部に東北・南北方向の溝ができた。これは官衙に関わる区画であると推測されている。博多濱では、13世紀までに区画に規制された溝・建物が造られたらしい。12世紀後半には博多濱に南北方向の溝が造られ、13世紀末にはこれに重複して基幹道路が造られた。聖福寺や承天寺など町屋の核ともいえる寺社の成立も12世紀末から13世紀前半にかけてである。さらに14世紀初には、この期間道路に並行・交差する支線道路が一斉に整備された。一方、息濱は「沖濱」「興濱」「澳濱」などとも見えるように、もともと沖に位置する砂州であった。その成立は12世紀初頭、北部砂丘と博多濱を隔てる低地の一部が陸橋状に埋め立てられ、博多濱と連絡したことに端を発する。この時点で息濱でも生活の営みが見られるが、溝や建物が営まれたのは14~16世紀になってからであった。ここに、伝統的な博多濱と新興の息濱という二重的な都市構造が生じることになった。以上が中世博多の形成過程である。この二重構造は、例えば、大友氏の追濱支配と大内氏の博多濱支配というように、中世末期の大内氏滅亡まで続いてゆく。
近世博多の形成の画期となったのが、16世紀末の豊臣秀吉の「太閤町割り」であった。天正八年(1580)の肥後龍造寺軍焼き討ち、天正十四年(1586)の薩摩島津軍焼き討ちなどによって、博多の市街は焦土と化し、ほとんど壊滅状態にあった。太閤町割りはこの戦乱被害からの都市復興計画であり、これによって、中世の道路は廃絶せられ、町屋も一律に短冊形地割りに塗り替えられた。(ただし、中世博多の町割りの構造が一部継承されているともいう。)また、博多濱と息濱の間の低湿地が完全に埋めたてられ、博多濱と息濱は一連の街路で区画された単一の町へと生まれ変わった。すなわち、太閤町割りによって、自然が町割りに優先した中世都市から為政者の意思が自然条件より優先した近世都市へと転換されたのである。
一行は近世博多市街の西境にあたる街路を通り、櫛田神社に向かった。当社は櫛田大明神を祭る櫛田社、天照大神を祭る天照大神宮、素盞鳴尊(すさのうのみこと)あるいは祇園大明神を祭る祇園社から成っている。社伝によれば天平宝字元年(757)に伊勢国櫛田社を勧請しての創建とするが、平安末期に平清盛、頼盛が九州に下向して着任し、博多を平氏の対宋貿易の窓口として整備した際に、父祖以来の対宋貿易の拠点であった肥前国神埼荘の櫛田神社を勧請したとも見られている。境内には、「博多べい」と呼ばれる土塀が置かれていた。「博多べい」とは、天正十五年(1587)の太閤町割りの際に、郷土再興の悲願をそのままに、焼け石、焼け瓦を土塀の中に厚く塗り込めたものをいう。ここに置かれているのは、博多三商傑のひとり島井宗室の屋敷跡に三百八十余年に渡って風雪に耐えた最後の博多べいを移築したものである。
櫛田神社は博多祇園山笠が奉納される最古の博多総鎮守でもある。博多祇園山笠の起源は、鎌倉時代、博多が悪疫に悩まされた際に承天寺の開山として有名な入宋僧 円爾弁円が町中に甘露水を撒いて清めたことに端を発するとも言われるが、本来は御霊信仰に基づく都市的な祭礼であった。いずれにせよ、文献上確認できるのは、14~15世紀に京都 八坂の祇園社が勧請され、16世紀までには総鎮守化したということである。我々が巡見をおこなった七月朔日は、折しも博多祇園山笠の初日であり、博多の町の随所では華美壮麗な「飾山(かざりやま)」や勇壮豪快な「舁山(かきやま)」が眼を惹き、袢纏姿の人たちが行き来していた。山笠は「流れ」と呼ばれる集団ごとに作られているが、それは豊臣秀吉が博多の町を七つの流れ(区画)に編成して以来のことであるという。
一行は櫛田神社を後にするにあたって、境内の「蒙古碇石」を見学した。「碇石(いかりいし)」とは、船舶の「碇」の部材として用いられた角柱状の石で、碇全体を重くして沈めやすくするとともに、海底面に碇の爪が安定して突き刺さりやすくするための機能を持ったものである。同様の碇石は承天寺境内、筥崎宮境内にもあり、いずれも従来から「蒙古碇石」「蒙古軍船碇石」と呼ばれていた。しかし、最近の研究では、元寇遺跡といわれる鷹島海底遺跡引き揚げの「鷹島型碇石」が二石分離型碇石であるのに対し、櫛田神社所蔵碇石は「博多湾型碇石」と呼ばれる一石型碇石(角柱形碇石)であり、時代的にはむしろ宋代に属するものではないかと言われている。同型の碇石は博多湾周辺のほか、奄美大島、沖縄、泉州、ルソン、ウラジオストクなどでも確認されており、東シナ海、南海の交易ルートを考える上で注目される資料である。
続いて、一行は大乗寺跡板碑を実見した。大乗寺は律宗に属する。(後に浄土宗、さらに真言宗に改宗。)櫛田神社に隣接していたが、移転後、戦災で焼失し、現存しない。亀山法皇の勅願寺であり、法皇山と号されたという。その碑石のひとつは、高さ180センチ、幅100センチ、厚さ22センチの玄武岩に地蔵菩薩の立像と両脇侍を陽刻しており、北朝の康永四年(1345)の造立である。隣の碑石は摩滅して肉眼では銘文を読めない状態であり、微かに梵字らしき三文字が確認できた。当碑は亀山法皇が元寇の際に「敵国降伏」祈祷をおこなわせた、「勅願石」として伝えられている。次いで、一行は12世紀初期の白磁ばかりが山積みに打ち捨てられた状態で出土したという冷泉公園のわき(第14次発掘調査地点)を過ぎた。ここは当時、徐々に形成されつつあった博多濱北西部の入江の入口に位置し、波打ち際であったという。また、この附近には宋の商館が多かったともいう。出土した白磁の山には国産遺物はまったく含まれておらず、貿易船から陸揚げされる際に、船中で破損した不良品を一括破棄したものと考えられている。このように大量の白磁が輸入されはじめるのは、11世紀後半ごろからで、この時期は鴻臚館を舞台としたいわゆる「波打際貿易」から博多濱での「住蕃貿易」への移行期であった。この量産品の白磁の大量輸入は12世紀前半まで続くが、その後、龍泉窯系や同安窯系の青磁が量的に白磁を凌駕するようになる。我々はさらに博多濱と息濱の境にあたる国道202号線を横断し、いよいよ中世は息濱であった地帯に入った。現在、博多座などのビルが建ち並び、地上を見る限りは普通のビル街にしか見えない息濱の石積み護岸跡遺跡(第96次発掘調査地点)に着いたところで、昼食を取ることにした。
午後の巡見は、博多小学校の石塁遺構展示室の見学から始まった。発掘時には、一直線に延びた全長53メートル、幅3.3~3.5メートルの石塁が見つかり、鎌倉時代に息濱に築かれた元寇防塁ではないかと考えられている。また、戦国時代から江戸時代初期の頃の屋敷跡、井戸、溝、ゴミ穴などの遺構も見つかり、この周辺にアジア各地と交易をしていた大商人の屋敷があったことも判明した。展示室は校庭の地下にあり、石塁の一部がそのままの形で保存されていた。一行はさらに豊臣秀吉の時代の豪商 島井宗室屋敷跡を通過した。彼は戦国時代の戦乱で焦土と化した博多の復興に尽力し、太閤町割りにおいて重要な役割を果たした人物である。また、茶の湯に親しむ文化人でもあった。一行は、再び博多濱方面に南下し、普賢通りと呼ばれる中世の街路を経て、聖福寺に入った。
聖福寺は初期禅宗を携えて宋より帰朝した栄西を開山として創設された我が国最古の禅寺である。広く閑静な境内には山門、仏殿、本堂、楼などがあり、特に鎌倉の古寺を思わせる伽藍造りと壮大な山門が印象的であった。ただし、度々戦火に遭って焼け落ちたため、現在の建物は江戸時代に建てられたものであるという。この山門の額には「扶桑最初禅窟(ふそうさいしょぜんくつ)」と書かれており、「日本最初の禅寺」という意味である。この額は後鳥羽上皇から贈られたものであるというが、疑問もある。聖福寺の創建は建久六年(1195)とも元久元年(1204)とも言われている。栄西は聖福寺を創建するにあたり源頼朝の袖判(承認)を得たといわれる。その申状が同寺に伝わっており、その内容は、仏地である宋人建立の学舎旧跡(宋人百堂跡)に堂舎を建立して本尊を安置し、鎮護国家を祈りたい、というものである。この申状自体は形式その他の点で検討を要すると言われるが、この地が宋人集住地であったことは確かなようであり、境内から越州窯の水注なども出土している。先にも述べたように聖福寺の開基檀越(創設寄進者)は源頼朝と伝えられているが、栄西の『興禅護国論』などの記述から、事実上の開基は張国安などの博多綱首(在日宋商)たちであったと考えられている。また、当寺は鎌倉末期以降、幻住派禅僧の対外交流活動の中心的禅院として機能していた。幻住派とは、入元して杭州天目山幻住庵の中峰明本の法系を嗣いで帰朝した禅僧たちの総称である。彼らの対外交流は民間的交流から国家的交渉にまでわたり、中国、朝鮮、琉球などに及ぶ広範な「幻住派ネットワーク」を形成していたと言われる。
続いて一行は承天寺に向かった。承天寺は、聖福寺に遅れること半世紀、円爾によって開創された。円爾は南宋禅界の大仏者 無準から法を嗣いで宋文化を移入した代表的禅僧で、後に京都 東福寺の開山となった。(その結果、東福寺は本寺、承天寺は末寺となる。)承天寺の開基檀越は博多綱首の謝国明であり、捨地檀越(土地寄進者)は鎌倉幕府の九州支配を代行する権限を持つ少弐氏(武藤資頼?)と伝えられる。檀越(寄進者)の両名はともに日宋貿易に深く関わる者たちであった。彼らが承天寺の対中国貿易において果たした役割は重く、円爾は、師 無準師範(ぶしゅんしばん)の居た径山(きんざん)万寿禅寺が罹災した際には、謝国明の勧めもあって径山復興に資した。このとき、謝国明は径山復興復興の材木として板1000枚を送っている。これに対して、無準師範らが書いた感謝状が有名な国宝の「板渡しの墨蹟」である。また、宝治二年(1248)に承天寺が火災に遭った時にも、謝国明は再建のための援助をしている。このように、承天寺の維持や対外活動は博多綱首たちによって支えられており、同寺は博多綱首の寺であるといっても過言ではない。
承天寺は本寺の京都 東福寺の出先機関として貿易実務の代行もしていた。例えば、有名な新安沈没船から「東福寺」、承天寺の塔頭(たっちゅう)である「鈞寂庵」などと書かれた木簡が発見され、荷主にこれらの寺社が含まれることが明らかになった。ここから、同沈没船の積み荷の一部は元応元年(1319)の東福寺罹災に際する再建に関わるものであると考えられており、さらには同船が寺社造営料唐船(大寺大社が造営復興等の費用を得るため中国に派遣した貿易船)である可能性も指摘されている。
あたかも一行が訪れた時、承天寺の庫裡、方丈、書院が公開されており、足を踏み入れることができた。庫裡から入って方丈へ抜けると、そこは、真夏を思わせる外の熱気が嘘であったかのように清涼とした空間であった。内には太宰少弐武藤資頼、聖一国師円爾、謝太郎国明の肖像画が掲げられており、聖一国師円爾の説法台なども置かれていた。なかでも、謝国明の肖像画は、商人というにはあまりに威厳ありかつ澄高な風体であった。この肖像画の成立に関する知識を持ち合わせない報告者には、それが肖似性あるものなのか、あるいは後代の「見立て」なのか判断はつかなかったが、いずれにせよ、そこには謝国明に対する博多の人々の心象が表れているように感じられた。方丈、書院の回廊を廻った後、重要文化財の「木造釈迦如来及両脇侍像」や「絹本著色禅家六祖像」などを見学した一行は、ここ承天寺で巡見の日程を終えた。なお、佐伯弘次先生のご厚意により、有志のみで謝国明の墓へ行くことができた。承天寺から10分ほど歩いたその場所には、樹齢を何百年も重ねたであろう神木の大楠があり、そのわきには謝国明の墓碑があった。ただし、この墓碑は江戸時代のものであり、元来、謝国明の墓は大楠のもとにあったという。死後、数百年を経てもなお博多の人々に崇められた謝国明は果たして単なる一介の商人に過ぎなかったのであろうか。そのような疑問がこの墓を訪れた報告者の脳裏によぎった。そのことについては、また後述することにしたい。
さて、我々の見た二寺の例に典型的なように、博多禅宗寺院は禅僧の対外交流の拠点となり、商人とは切り離しがたい関係にあった。寺院の資財管理や運営、対外交易など俗的な面は商人の力に拠るところが大きく、商人は経済的に寺院を外護して自らの「信仰の場」とするとともに、活動の拠点としたのである。また、科挙制に基づく士大夫官僚を有さない日本においては、教養集団を輩出する禅宗寺院が外交機関として機能した。主に中央政権は京鎌五山を、博多周辺の在地政権は博多禅宗寺院を外交機関として利用し、一方で博多禅宗寺院は五山との緊密な関係を維持しつつ五山の出先機関の役割を果たした。そのため、対外交流に携わった者の大半が何らかの形で博多の禅宗寺院に関わっていたといわれる。さらに附言するならば、対外派遣使節において、実際に船を手配して現地まで使節を導いたのは対外交易に携わる商人たちであった。(イスラム世界でも同様のことが言える。例えば、ティムール朝シャー=ロフの明朝派遣使節団では、使節の従者として多数の商人が参加していた。)ここに、対外交流における「政」「商」「僧」の複合的な関係が見て取れよう。
同様の構造は、博多だけに限られない。博多の交易相手でもあった元朝下江南においても見受けられる。例えば、元朝に仕えたウイグル人官僚 亦黒迷失(ユィグミシュ)は度々、寺院への喜捨活動をおこない、報恩万寿堂による大蔵経の出版事業に都大勧縁(総世話人)として名を連ね、江南の白蓮教団の有力者であったと見られている。また、彼は世祖フビライの命を受け、セイロン、インドなどに派遣されている。その目的はそれらの諸国と通交関係を結び、仏鉢舎利や国師を将来することにあったが、現地では交易活動もおこなっていた。彼がジャワ遠征に参加したのも、軍事的目的よりもむしろ東南アジア周辺の諸国を招撫して通商関係を結ぶためであった。亦黒迷失自身は元朝に仕えた官僚であるが、オルトクと呼ばれるウイグル・イスラーム系特権御用商人との関係も深く、彼自身も交易をおこなっていたのである。亦黒迷失のように官位を得ながら、自ら或いはその兄弟、一族が交易に携わる商人であった例はめずらしくない。彼らは漢語史料に「権豪」「権勢」(特に官位に就いている者は「官豪」)などと呼ばれ、しばしば「僧道」「斡脱(オルトク)」と並記される。「権豪」は大規模な資本を持ち、交易や土地経営をおこない、しばしば官位を得たり、寺院や教団に深く帰依して外護者となったりする有力都市民であった。元朝の海運を一族で専掌し、大規模な海外交易を営んだことで有名な朱清・張?の一族も、平江路の磧砂延聖院による磧砂版大蔵経出版の有力スポンサーであったことが近年の研究で指摘されている。
日本に在住していた宋商 謝国明も中国でいえば「権豪」に該当するのではないだろうか。謝国明は博多 櫛田に拠点をもつ在日宋商で、複数の寺院に帰属関係をもって経済的にそれらの寺院を支える基盤であったとともに、活動の保護を受けていた。また、宗像社領 筑前国小呂島(現福岡市西区)に地頭職を持ち社役を勤めていたことが知られる。彼は在日中国人商人の貿易船団の長を意味する「綱首」と呼ばれていたが、近年の研究によれば、「綱」の原義は政府の委派を受けて官物運送を管領する人であり(『唐律疏議』)、波及して封建政権の財政、軍需、貿易と密接に関係した商業活動もすべて「綱」と称されるようになった。あるいは謝国明も何らかの形で宋朝政府とも関係を有していたのかもしれない。謝国明はまた、円爾の師である無準師範とも直接面識を有していたともいい、禅参入していた可能性も高いという。このように見てみると、元朝の亦黒迷失といい、謝国明といい、単に「財務官僚」、「商人」としてだけでは片づけられず、「官」「商」「僧」のいずれの性格も有する存在であったといえよう。よって、謝国明をはじめとする博多綱首たちと博多の都市形成について考える場合、単に「商人」としてだけではなく、宗教や公権力との関わりという面からも捉える必要がある。それはイスラーム世界でも同様であり、特に「僧侶」という身分の存在しないイスラーム世界においては、日本や中国など東アジア世界に比べ、商人と宗教人の間に存在する「俗」「聖」という意識差が希薄であって、商人の有する多面性はより顕著なはずである。「商人」や「ウラマー」「スーフィー」などといっても、決して一元的視点だけから捉えられるものではないだろう。今回の巡見では、中世日本最大規模の国際貿易都市 博多の都市形成において商業・宗教・政治の三つが密接に関わりあっていたことを自分の眼で確かめることができ、極めて有意義であった。報告を終えるにあたって、炎天下のもとご案内をしてくださり、資料を準備してくださった佐伯弘次先生と随時解説を加えてくださった伊藤幸司氏に感謝の意を示して筆を置くこととしたい。どうもありがとうございました。
(文責:阿部 尚史、四日市 康博)
《参考文献》
伊藤幸司「大内氏の対外交流と筑前博多聖福寺」『佛教史學研究』39/1,1996
伊藤幸司「中世後期の臨済宗幻住派と対外交流」『史學雜誌』108/4,1999
上田純一「鎌倉・南北朝期における筑前博多聖福寺」『九州史学』79,1984
大庭康時「聖福寺一丁目2番地 -中世後期博多における街区の研究(1)」『法哈?』2,1993
大庭康時「発掘調査からみた博多聖福寺と町場」,中世都市研究会(編)『中世都市研究4 都市と宗教』新人物往来社,1997
小川光彦「鷹島町第7次潜水調査(神崎地区):1997年度調査」『NEWSLETTER(九州・沖縄水中考古学協会会報)』4/4,1998
小川光彦「東アジア海底引き揚げの碇石」東南アジア陶磁器の生産と流通研究会発表要旨,金沢大学,2001
川添昭二「鎌倉中期の対外関係と博多-承天寺の開創と博多綱首謝国明」『九州史学』88-90合併号,1987
川添昭二(編)『よみがえる中世(1) 東アジアの国際都市博多』平凡社,1988
川添昭二「鎌倉末期の対外関係と博多-新安沈没船木簡・東福寺・承天寺」,大隈和雄(編)『鎌倉時代文化伝播の研究』吉川弘文館,1993
川添昭二『承天寺の歴史』承天寺,2001
北村高「元朝色目人「亦黒迷失」の仏教活動」『木村武夫教授古希記念 僧伝の研究』永田文昌堂1981
北村高「元代白雲宗の寺院と僧侶」『小田義久博士還暦記念 東洋史論集』,龍谷大学東洋史研究会,1995
佐伯弘次「中世後期の博多と大内氏」『史淵』121,1984
佐伯弘次「大内氏の博多支配機構」『史淵』122,1985
佐伯弘次「中世都市博多の発展と息浜」,川添昭二先生還暦記念会(編)『日本中世史論攷』文献出版,1987
佐伯弘次「中世都市博多の総鎮守と筥崎宮」,中世都市研究会(編)『中世都市研究4 都市と宗教』新人物往来社,1997
佐伯弘次,小林茂「文献および絵図・地図からみた房州堀」『福岡平野の古環境と遺跡立地-環境としての遺跡との共存のために』九州大学出版会,1998
西尾賢隆「京都五山の外交的機能-外交官としての禅僧」荒野泰典ほか(編)『アジアのなかの日本史2外交と戦争』東京大学出版会,1992
廖大珂「略論宋元時期的綱首」『海交史研究』1993/2
(文責:深見 奈緒子)