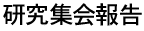
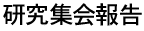
日時: 2001 年 3 月 13 日(火)〜14 日(水)
場所: 千葉県長生郡一宮町・ホテルシーサイドオーツカ
研究合宿はホテルシーサイドオーツカ付設の研修施設αプラザ(上総一ノ宮)で行わ れ、発表者3名の他、安藤潤一郎(東京大学大学院博士課程)、岸本美緒(東京大学大 学院教授)、黒岩高(東京大学大学院博士課程)、佐藤実(京都大学人文科学研究所非 常勤研究員)、東長靖(京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科助教授)中 西竜也(京都大学大学院修士課程)、仁子寿晴(日本学術振興会特別研究員)、松本光太 郎(東京経済大学助教授)、三浦徹(お茶の水女子大学教授)の計11名が参加した。
第一部: 13日 13:30〜18:30
『天方性理』図伝巻5 体一三品図説
翻訳・発表 青木隆(東京大学大学院博士課程 中国思想文化)
『天方性理』図伝巻5 三一通義図説
翻訳・発表 鈴木弘一郎(東京大学大学院博士課程 中国思想文化)
第二部: 14日 9:00〜12:00
『天方性理』図伝巻5 自然生化図説
翻訳・発表 小島毅(東京大学大学院助教授 中国思想文化)
【体一三品図説】
体一の三品は身体、心体、性体を指す。身、心、性の3分類は『図伝』巻四「聖功
実践図」「聖賢知愚図」「障碍層次図」などに見え、そこでは次のように説かれる。
「身」の条理(礼)を実践するものを愚者、「心」の条理(道)を実践するものを智者、
「性」の条理(真)を実践するものを賢者と呼び、さらにそれぞれのレベルで身体的欲
望や自意識などのために「本然」=真一との完全なる一体化が阻まれている賢者・智
者・愚者の人々をゴールに導くのが聖人であるという。
三一説は劉智に先立つ王岱輿の『正教真詮』『清真大学』に初出するが、王岱輿と
劉智の三一説に対する考え方は若干異なるのではないかとの意見が出た。
【三一通義図説】
『天方性理』巻五では、真一三品図説・数一三品図説・体一三品図説において中国
イスラーム思想の「三一説」が展開されてきたが、本節はそれらの総括をなすもので
ある。研究会では、本節中に散見される「三而一」の「一」とは何なのか、また「三
一」とは真一・数一・体一の三者のことだが、劉智はその三者を超越した「一」の存
在を考えていたのではないか、などといったことに関して、中東イスラーム思想の
タームとの対比をしつつ活発な議論が行われた。また、「三一説」に関しては、中国
社会科学院の金宜久氏の研究があるが、その研究に対して批判的な指摘がなされる一
幕もあった。
【自然生化図説】
本節では造物〔主〕による生成が理(不可視的なもの)と象(可視的なもの)の二
つに尽きるということが述べられる。この理と象とは自然にしてそうなるのであり、
生み出す者、変化させる者があって存在するのではない、とされる。
本節にいう「生化」の考え方は『列子』天瑞篇で説かれる「生成しないものは生成
する万物を生成させ、変化しないものは変化する万物を変化させる」と考え方と類似
する、との指摘があった。読解に関しては「理世等等不一之理、象世等等不一之象」
の意味を保留した。
なお今回の合宿で時間の都合上割愛せざるを得なかった青木隆氏の小論を掲載する。
(文責:佐藤 実)
明末の万物一体の思想における「無我・忘我」と「往来」について 青木 隆
回儒たちが彼らの思想をこなれた文語漢文で著した時の苦労は察するにあまりあ
る。スーフィズム的なイスラム思想はそれまで漢語で書き著されたためしがなかった
からである。彼らが同時代に流通していた中国思想の文献の漢語表現を参考にしつつ
作業をおこなったことは十分考えられることである。だから回儒たちの漢語表現を見
れば、彼らが中国の思想の中のどんなものに類似性を感じていたのか、そして自分た
ちの思想を中国の類似の思想からどのように差別化していたのかも理解できるかもし
れない。さらに、回儒たちの漢語による著作との対比によって中国思想の特徴が何か
新たに浮かび上がるかもしれない。
この「体一三品図」『天方性理図伝』巻五は、真有の顕現である修行者が真一に帰
一する体一について説明する章である。修行者が真一に一体化するする際に三段階あ
り、一体化の際の修行者の自己意識の消滅、つまり「無我・忘我」が話題の中心と
なっている。これに似たものを中国近世の宗教思想に求めれば、万物一体の思想があ
げられる。
中国近世の諸思想において、自分と自分以外との区別をしないこと、つまり「無
我」あるいは「忘我」という事態は、儒仏道の三教の別にかかわらず万物一体という
理想状態を示すメルクマールとして尊ばれた。たとえば、曹洞宗系の禅僧永覚元賢
(1578-1657)が「三教の聖人、教を設くること同じからずして必ず同じき所以は、
此の無我なり」と発言するように、「無我」は儒仏道三教に共通するものとして意識
されていた。多くの場合、万物一体の「無我」とは、自分と自分以外の二者関係の存
在を前提に、そのうえで自分と自分以外の二者を無我なる一体として見る視点を獲得
することを意味した。
自分と自分以外の区別がないから、自分と区別される自分以外のものがある。自
分と区別される自分以外のものがあるからいっそう自分と自分以外の区別がなくな
る。自分と自分以外の区別がないこと(無我)から出発して身体・心・他人・外物を
見てゆくと天地・宇宙の全体があまねく一つの巨大な無我の状態に到達する。(其の
無我に 因て所以に待つ有り、其の待つ有るに因て益々無我を見る。此に即して之
を推すときは、則ち身の若き心の若き人の若き物の若き以て天地の覆載虚空の寥廓に
及ぶ、総じて一無我の通光なり。)永覚元賢『げい(「うかんむり」に、左下が「爿」、右下の上側が「自」+下側が「木」)言』巻下元賢の発言からは、自分以
外のものの存在が自分と自分以外の物の区別をしない「無我」の前提であり、さらに
そのことがよりいっそう「無我」の状態へと事態を推進させる契機であることがうか
がえる。確かに、自分と自分以外のものを区別をしない「無我」という観念は、自分
と自分以外の両者の存在を論理的に要請するものであろう。元賢の考えでは、こうし
た「無我」を実現したとき、「必ずしも自分を滅却し自分が自分
以外のものを包容しなくても自分は自分以外のものになっているのだし、必ずしも自
分が自分以外のものと出会ってこれを自分に帰着させなくても自分以外のものは自分
になっているのである。(既に総じて一無我なるときは、則ち我れ必ずしも之を廓し
て以て物を容れずして己れ物に非ざる無し。物の必ずしも之を会して以て己に帰せず
して物己に非ざる無し。)」と自ら語るような万物一体の事態が現出しているはずな
のである。
自分と自分以外のものの存在が「無我」の前提であり、そのうえで自分と自分以外
を区別しない「無我」の状態とは結局、元賢の語るように、自分が自分でありながら
同時に自分でなく、自分以外のものが自分以外のものでありながら同時に自分である
という自己意識の問題に帰着しがちである。もともと、万物一体の思想の源泉たる
『荘子』の大宗師篇には、水の中を自由闊達に泳ぎ回る魚のイメージを借りて、自分
の内外の区別を忘れるのが万物一体であると説明する「両忘」という言葉がある。北
宋の程頤がこれを踏まえ、目標とすべき理想状態を『定性書』の中で「内外両忘」と
言ったように、「無我」なる万物一体は一方で「忘我」のことである。
理想状態としての「忘我」は、自己の内外を分かつような自分のことを忘れること
であるが、当然のことながらそこに自己言及的なパラドックスが生じる。つまり、自
分を忘れることを意識していたのでは、自分を忘れたことにはならないと考えられた
のである。三教一致論者の林兆恩(1517-1598)は、この問題について「之を忘じて
既に忘ずれば、忘を忘ずる所に忘じ、忘を忘ずる所無きに忘ず、是れ之を真忘と謂
う。」と発言しているように、彼も忘我とは単に忘れるだけでは不十分で、忘れるこ
とを忘れることが必要であると考えていた。林兆恩はさらに、「聖人知らざること無
くしてまた忘ぜざること無し。忘ぜざることなく忘ずることなし。斯れ之を真忘と謂
う」とたたみかけ、忘れることを忘れるという真の忘我は、知らないことがない、忘
れることがないといういわば全知の状態にほかならないことをわれわれに示唆してい
る(『無生篇』巻上)。 この真の忘我の状態の時、われわれは天地万物と一体なの
であるから、自分が天地万物であると意識してもならないし、反対に天地万物がこの
自分であると意識してもならない。林兆恩の万物一体についての発言は、自分と自分
以外の区別をしない「無我」
だけでなく、天地万物とこの自分の区別をしない、いわば「無天地万物」を説く点
で、明末の万物一体の思想の中で最も踏み込んだ表現かもしれない。
もし自分は天地万物であると言えば、自分の存在を意識してしまう。自分のある
ことを意識するということはまだ(自分以外と区別されるような)自分があるという
ことなのだ。もし天地万物は自分であると言えば、天地万物の存在を意識してしま
う。天地万物のあることを意識するということはまだ(自分と区別するような)天地
万物があるということなのだ。まだ自分があり、天地万物があるのならば、自分と天
地万物は一つになっていない。(若曰我即天地万物、則是知有我也。知有我、則尚有
我也。若曰天地万物即我、則是知有天地万物也。知有天地万物、則尚有天地万物也。
尚有我也、尚有天地万物也、而我與天地万物為非一矣。)林兆恩『心本虚篇』一五表
しかし、林兆恩の議論では、自分の存在を意識するのも、天地万物の存在を意識する
のも自分にすぎず、どこまでいっても自分の意識しか問題にされない。中国近世の万
物一体の思想の場合、自分と一体となる天地万物の範囲を自分の身近な範囲からしだ
いに大きくしていって最終的に天地宇宙大に至るという段階的方向性があり、万物一
体とはなによりも自分以外の他者との一体化の感覚を意味した。天地万物と人間の本
体は同じで
あるから、本来的に天地万物は一体であり、自分以外の万物の感覚が得られるのだと
考えられていたのである。したがって自分が万物一体を達成することは自分が自分及
び天地万物の本体へ立ち返ることでもあると考えられていた。しかし、人間の意識を
可能にしながら意識の対象にならないものという本体の定義上、人間が天地万物の根
源を意識することは不可能である。
それに対して、劉智の性体における真一との一体化についての議論では、修行者の
真一に対する意識だけでなく、修行者の帰一を受け入れる側の真一の意識までもが問
題にされているのにもかかわらず、いっこうに修行者の自分自身に対する意識のこと
は問題にされる気配がない。つまり、性体のレベルで帰一を成功させるためには、修
行者の側で真一を意識してもならないし、真一の側で修行者を意識してもならないと
いう厳しい条件が科せられているのに、修行者が自分を意識することについてはおか
まいないのである。少なくとも修行者が帰一して修行者=真一となるまでは。宗教者
は別にして、明末の儒者の中には「無我」を自己意識の問題に限定する王学左派系の
儒者も有力であったが、多くは自分の意志や行動が天理の自然にかなっていること
(私意でないこと)とオーソドックスに解釈するのが普通であった。自意識の問題に
還元することなく万物一体を説くために彼らが用いたのが「往来」である。「往来」
は、屈伸や感応などと同じく、気の運動のことである。天地万物の生成は気の運動で
ある。宋学では、しばしば人間の呼吸を例にあげて気の運動と生成を説明する。程伊
川
は、呼気と吸気の往来とは、身体に吸入された吸気がそのまま呼気となって身体の外
に排出されるものとは考えていなかった。「屈伸往来の義は、鼻息の間にあらわれて
いる。屈伸往来が理である。屈の気がまた伸の気となるとは限らない。生生の理は自
然であってやむことがない。」(『近思録』道体篇)という北宋の程伊川の発言があ
る。程伊川は、吸気とは別に身体の中で気が生成され、身体の外に排出されるのが呼
吸の際の吐く息だと考えているのである。人間の吸気に応じて発生する呼気は、屈伸
往来の局面で不断になされる気の生成の一例なのである。気の運動があるということ
は、多くの明代の儒者たちによって万物一体の徴候と考えられた。朱子学者で万物一
体論者の羅欽順(1465-1547)は、呼吸という気の往来を根拠に天地と人間が一体で
あることを例証している。「人間の呼吸の気が天地の気なのである。形体から見れ
ば、内外の区別があるかのようだが、実際には一気の往来である。
程子(明道)曰く、『天人はもともと二つに分かれていないのだし、合一しているな
どとというまでもない。』気こそが理なのである」『困知記』。人間は天地と形体の
うえで隔たっているが、ほんとうは人間と天地は一体なのだ。なぜならば人間の呼吸
の気が天地の気であるということは、人間と天地の間に一気の往来があるということ
であり、一気の往来があるということは、一体であるということなのだから。王陽明
(1472-1528)は、人間身体とその他の禽獣草木の身体は別々なのに同体というのは
何故かという質問する弟子に「感応の幾を見よ」と答えている。気の運動(感応)の
レベルで見れば、「心の霊明」と「天地鬼神万物」は「一気流通しているもの」で
あって、両者は互いに不可分の存在なのだ(『伝習録』巻下)。
劉智によれば結局の所、「無我」であり「往来」がある明末風の万物一体では、
「真一」への帰一、すなわち神との合一とは程遠いのだ。「真一」への帰一を劉智が
古典漢文で表現する際に、「真一」への帰一を語るのに不十分であるにもかかわらず
「無我」とか「往来」といったタームが使われるのは、劉智の議論に類似した明末の
万物一体の思想の語彙を使って、それとの差異を際立たせることによって表現せざる
を得なかったからであると考えることができよう。