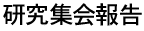
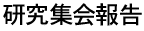
 ※PDFファイルを開くには、"Adobe Acrobat Reader" をインストールする必要があります。
※PDFファイルを開くには、"Adobe Acrobat Reader" をインストールする必要があります。
(右のボタンをクリックすると、無料ダウンロードのページにとびます。)
1-1 春日 直樹(大阪大学人間科学部、文化人類学/フィジー・オセアニア)
「フィジー社会における良き経済秩序」
報告要旨 PDF ファイル「Pf_kasuga.pdf」
レジュメ PDF ファイル「Pf_kasuga2.pdf」
1-2 林 文孝(山口大学人文学部、中国思想史)
「明清期中国の史論における公正」
報告要旨 PDF ファイル「Pf_hayashi.pdf」
レジュメ PDF ファイル「Pf_hayashi2.pdff」
1-3 長谷部 史彦(慶応義塾大学文学部、中東社会史)
「アドルと『神の価格』:マムルーク朝期カイロの市場社会と王権」
2-1 春日報告に関して
三浦徹:フィジーの当時の人口や、会社の出資対象について教えてほしい。
答:人口は、6万から7万台。一時インフルエンザで減ったが、1910年代から人口が増えている。出資対象について、帳簿は見たが、どう使われたのかはわからない。政府の命令で決算書を作ったが、会社の金とアポロシ個人の金が混同されている。取引の記録もない。ただ、「今、金がどこかにある」ということは信じられていた。
三浦:ココナツ石鹸工場の話が出てきたが。
答:ココナツ工場は結局できなかった。バナナを白人商人に売る契約を結んだが、守られない内にアポロシが逮捕され、白人業者が再び集荷を始めた。ビジネスの活動として確かに行われたのは、このバナナの専売と、店舗を3軒ほど経営したことである。店舗では、石鹸、ビスケット、キャラコなどが売られていた。学校は、3つばかりが1年あまりの間、開校されていた。
立本成文:manaとturanga の本物性という話があったが、本物でないmanaはmanaか。本物であることと「よい」ことは同じか。本物、よい、ということは、Viti(フィジー)がこれらを概括する概念になっているのではないか。
答:manaは本物でなければならない。authentic なもの。言った通りのものが現れなければおかしいということ。 ndinaとの関係でいうと、manaは「あるべき、ある筈の」もの。同時に、よいもの、祝福されるべきものでもある。Vitiだからよい、という自文化中心主義的なものはあるが、白人のmanaもあり得る。ただ、それをフィジーに関連あるものとして読み込んでいく、ということがある。
関本照夫:過去の伝統にもどる部分と、新しく来たものがよいものだという観念とがないまぜになっているところが面白い。その意味では、オセアニアには、カーゴカルトという西洋人のものが自分のものになるという運動があるが、新しいものに収斂していく面と、伝統的な面との関連が、他の地域とパターンが違うような気がする。
答:過去へ、というのはいいすぎかも知れない。昔の隠されたものを新しく発見するということである。
関本:カンパニーというのは面白いが、他の地域でもそういう例があるのか。
答:トンガなどであった。白人が主導して、実際の購買運動を行った。1900-10年代。土着運動として発展したわけではない。
関本:白人と接触して、会社のなかに秘密を見つけた、というような例は?
山本真鳥:カーゴカルトは宗教運動として有名になっているが、ニューギニアでは最近コープのようなものができている。出資金を集めたがそのままポシャってしまった。
三浦:会社は悪いものだと考えなかったのは不思議である。
答:何かがある、だまされている、隠している、という感じを会社に対してもつ。
柳橋博之:カンパニーという言葉は、国家、統治組織というふうに考えているのではないか。利潤を生む装置というよりは権力装置。
答:実質的にはそうだと思うが、会社が出発点にあった。
柳橋:東インド会社に近いのではないか。統治までふみこんだ会社。
答:最初は大チーフの方にお金を集めるが、立場が逆転してお金がアポロシの方に行ってしまう。
柳橋:富、利潤に対する伝統的な考え方はどのようなものか。
答:需給関係、つまり供給がへる価格が上がるといった関係について、彼らはよく知っていた。また、(福音となる)いい儲け、悪い儲けという考え方はもっていた。ウェーバー流の精神とは違うと思うが。
岸本美緒:一般に会社というものを考えるとき、会社内部の結合・秩序というものもあるが、会社は外部の市場社会のなかで競争することによって利益を得るので、そうした外部秩序のイメージもある筈だ。ヴィチ・カンパニの場合は、内部的結合をめざして盛り上がっているところはよくわかるが、外部秩序のイメージはどのようなものだったのか。また、会社というのは契約によって結ばれ、ダイナミックな運動体として広がっていくイメージがあるが、それと「古代の想起」という本来的過去への回帰とは抵触しないか。会社の中には、フィジー人以外も入れるのか。
答:外部イメージとしては、白人の会社などが競争相手として考えられている。ヴィチ・カンパニは本物なので、相手は必ず負けると思われているが、外部との競合は意識されている。運動体の無限の広がりという観念はある。初めフィジー人に限っていたが、白人でもインド人でも入ってよいということになった。入れば救われる。出資金は高いが、差異化して取り入れる。中心から外延へ、他者・異物を含み込んで広がってゆく。帝国的なイメージをもっているのかとも思う。運動の過程を通じてできたイメージである。
原洋之介:1910−30年代、フィジーの産物は何か。
答:コプラ・バナナ・サトウキビなどである。
原:家族数は1万位か。そのうち農家数は? カンパニは集荷組合のようなものか。
答:世帯数は1万5千位だと思う。90パーセント位は農村人口。農家のほか、都市に行って港で荷役をしたり、プランテーションで働く労働者もいる。
原:よき経済秩序がカンパニーという形で構想されたことの秘密は何か。一種の協同組合、地域主義のようなものと考えてよいか。都市型の製造業社会ではなくて。
答:トゥランガ(長)が上に座らないとだめで、ヘッドに預けると増えていくと考えている。
原:それは、ある意味では資本主義そのものじゃないか。
答:お金集めは好きである。
原:カンパニーとコーポラティブ運動との違いが意識されていたのだろうか。
答:白人が始めたのはコーポラティブな運動。
原:この時代は、恐慌がからんだりしているのではないか。
答:値動きが大きく、販路を握れば強かったと思う。しかし、ヴィチ・カンパニの運動は、見返りがなくても繰り返しやるところが特色。
木下鉄矢:カンパニーといえば、坂本竜馬の海援隊もそうだった。広域的人間関係を統括するシステムといえると思うが、首長をいただくシステムのほかに、フィジーのなかにそういう独自のシステムがあったのか。なかったとしたら、西洋人のもちこむカンパニーは、金を集めて富をつくり出してゆく、不思議なものと見えたかも知れない。
フィジーのなかに、家や村とは違う社会的結合形態はあったのか。アポロシの血筋はどうなのか。在来の社会のなかでは、長になる人は身分や家柄が限られていたのか。カンパニーの能力主義が新しいと思われたのか。
答:カンパニーに相当するようなシステムはもともとはない。トゥランガの地位は、家柄か能力か、どちらともいえない。植民地政府が入ってきたときに、一定の氏族でないと認められないと、家柄的に固定したため、不満が高まっていた。アポロシ自身も、「本当は首長になるべきもの」というアンビバレントであり、それを利用した。
木下:フィジーでは、法人的なものそれ自身が魔力をもつ秘密めいたものとして人格化された。ウェーバーの支配の諸類型に、カリスマ・官僚制などがあるが、国家的組織が大規模に公益性を保障する制度があったのか。それともカリスマによって常に動揺していたのか。
答:国家と訳せるかどうかわからないが、matanituという言葉がある。首長間の勢力の消長はあるが、カリスマ的人物が出てきて一遍に変わるということはない。
木下:市場に対し、国家が予測可能性を提供できないとすれば、フィジーの人々にとって、我々がいうような市場というシステムの観念がなかったのでは。
答:取引、計算は上手である。市場経済に対し積極的な態度で踏み込んでいったといえるのではないか。
木下:適正価格を考えていこうということがないと、そう言えないのではないか。
答:高すぎる安すぎるという感覚はある。経済学の教科書のような意味ではないかもしれないが。
原:カンパニーがlimited であるというような点は、フィジーの人々はその意味を理解しているのか。
答:実態はわからないが、そういう名前がついている。
原:株主という観念はわかっていたのか。
答:わかっていたとすれば、資本主義そのものだが。
三浦:フィジーのカンパニー運動は、ビジネスの成否とは必ずしもかかわらずに続いたということだが、日本のビジネスマンの意識も、実は同じようではないのか。フィジーの特殊例ではなくて、我々の経済行為についても考えさせられる。
2-2 林報告に関して
三浦:「おわりに」のところで、「(『公正』を)見いだすことは、主体自身が『公正』でないとできない。それゆえ、『公正』をめぐってさまざまな見解の広がりがあるのがむしろ常態であっただろう」とあるが、この「それゆえ」とはどういう意味か。
答:「公正」さそのものと「公正」を提示する主体の「公正」さとの2つのレベルが区別されていないということ。それが正しいという判断を提示するためには、万人に納得させる、誰もが承認する人格的能力がないといけない。普通の人が「これが大公至正だ」といっても、それに対する異論が出てくる。聖人であって始めて、誰もが納得する公正さを見いだせる。
岸本:王夫之は一方で「勢」を重視しつつ、他方では例えば夷狄が中国を支配する「勢」などに対しては決して承認することなく、定言命令的に華夷の分を言う。経済政策についても、一方では国家的規制を否定して放任を主張しつつ、他方では規制を主張する。そういうところが、王夫之の議論を「矛盾」の多いわかりにくいものとしているようにも思うが、統一的にとらえられるか。
答:経済政策に着目してみると、議論の型は一つに収斂し得るのではないか。土地所有に関しては事実的な展開にのって、国家の介入が負の効果を生むことを強調するが、塩の場合は米や土地とは異なってどこにもあるというものではなく、商人に独占され思うままにされやすいので、最低限の規制が必要だ、ということだと思う。こうしたバランス感覚はある程度一貫したものといえるのではないか。「勢」には諸条件があって、小人が勝手なことをして展開する勢もある。それを回復する場合、小人をいきなり排除することは反動を招くので、そうした方法はまずい。勢の反転を適切にとらえることが必要だ、というのであって、単なる状況追随ではない。
平田茂樹:経済政策論で矛盾と見られる点の一つとして、租庸調は均田制をもとに考えているが、その一方で土地所有の規制はいけないと言っているということがある。これは王夫之の議論の時代性であって、当時の「均」の観念が唐代等と違うのではないか。
答:一律均等ではなく、各々その所を得る。「分」という上下関係を機軸とした関係性があり、それに応じて得るべきものを得るのが「均」である。均田制については、戦乱の復興の政策として、租の負担が軽いところをとらえて高く評価している。
小島毅:(1)黄宗羲の場合の公議は、集団のなかで、という感じがあるが、王夫之の場合は名君待望論のようにも見える。「公正」の主体はどこにあるのか。(2)現実を踏まえ、結果を見通して適切であったかどうかが公正の基準となっている。判断する主体をどうとらえているのか。(3)中国語の元来の意味において、「公」と「正」との異同は何か。
答:(1)(2)名君待望論ではなく、官僚の方に大きな役割を期待していた。官僚が自ら判断して行う。事実上は特権的な治である。(3)この報告の依頼を受けたときは、「公正」という語を、フェアという意味、公認された手続きにのっとっており、不当な独占がない状態、という意味に受け取った。しかし、手続き的公正が中国で「公」と考えられるかというと、そうではない。現実にどうあるかという実質的問題。皆に共有の、独占されていないという状態である。「義」「是」「正」それぞれ、より個別的な場面に即して論ずる必要がある。
三浦:時間が残り少なくなったので、以下質問を続けて受付け、総合討論のときにまとめて答えていただくことにしたい。
青木敦:我々が考えるfairnessという意味の公正の概念を、近代の思想家はどのように受け入れたのか。
木下:「公」は名詞か形容詞か。「公と私」という場合、「公」は開かれているということが本義である。朱子によれば、「正」の感覚は「理」とは違い、「正−変」「正−邪」という対比。正、直、方、大は感覚的に似ている。公と私とは、道と径のトポス分けと重なるのではないか。王夫之らは政論家であって実際民政にたずさわっていない。それに対し、宋代の論者は実際に政治をしている。王夫之らの時代は議論がファナティックな傾向がある。
岡元司:「公」の問題は、public sphere という議論の場に関わっている。議論の場として黄宗羲の場合は学校があったが、王夫之の場合にはそうした場があるか。
2-3 長谷部報告に関して
三浦:ムフタスィブは市場価格の決定に力を持っていないと思うが、ムフタスィブの罷免要求は形式的なものなのか。
答:ムフタスィブは公定価格を提示し得る。
春日:神の価格を中世ヨーロッパのjust priceと比較できるだろうか。市場価格というのとは違うのではないか。
答:神の価格が従来 just price と訳を付けられていたので、その点をとらえて比較してみた。
柳橋:法学書には、価格に関する記述は少ないが、ハナフィー派の通説によれば,買い溜めの事実があっても,スルターンは,これを威嚇することはできるが,買い溜めの対象となっている物に手をつけることはできない。しかし人々の生命が危うくなった時には、買い溜めをしている商人から品物を没収することができる。ただし,買い溜め者はその意に反して商品を失ったので,後日それと同種の物が市場に出回るようになった時には,スルターンは没収した物と同種・同量を返還しなければならない(al-Kasani、11世紀)。マーリク派においては,食糧が払底した時点で、商人が原価で放出すべき(al-Baji、11世紀)とする説が唱えられている。これは、商人の行為自体に無効となる原因があるのではない。市場での契約とは関係のないマスラハ(公共利益)のための政策である。このような見解は,11世紀の中央アジアやアンダルスの学者が9世紀初めのメディナの学説を引用しているあたりが初期のものである。(注:ハナフィー派については,この時期の著作で学祖に帰せられた説は信憑性が計りにくいという問題がある)
三浦:買いだめ商人に放出させるというのは、買いだめ商人が人為的な操作をしているから、というのが理由なのか。
柳橋:食糧が存在するのに人々が飢えている、ということで取られる例外的な措置と解すべきである。
答:こうした政策は、その時々の政権の判断であり、明確な基準があったかどうかは明らかではない。
岸本:中国の場合、食糧が地域外に販出されるのを防ぐ、という一種の経済的地域主義が食糧暴動の大きな要因の一つだが、カイロの場合はどうか。
答:シリアに穀物を販出するときに抗議行動が起こる例がある。
山本:どの辺が just なのかについては、はっきりした基準がないようだが。全くの市場価格は just ではなく、商業活動が公共性を持っている、という考え方なのか。
原:経済学者に「公正価格とは何か」と聞けば、みな答に窮する。何が公正か、というときに、長期均衡価格を fair price という場合もあるし、必需品なのに高すぎるという議論が含まれる場合もある。ここでは、長期均衡価格をいうのではないか。つまり、買い占めるから長期均衡価格よりも高くなるという意味ではないか。アダム・スミスのいう natural priceである。
柳橋:イスラム法でザカート(公共福祉税、救貧税)というのがあるが、商品に対し一年未満で転売するとザカートをかけない。退蔵して値上がりを待っている場合にかけるもの。
三浦:乱高下している場合も神の価格というのか。
答:ズルム(不正、不公正)の要素を排除したあとの価格をいうのであろう。当時の人々は人為的要因についても気づいていた。神の価格という語が出てくるときは常にズルムの排除が一緒に出てくる。
三浦:これは法理論上の議論とは違うのか。
答:違う。
阿久津正幸:イブン・ハルドゥンが「市場に対する国家の介入が全体としてマイナス要因となる」といっている。当時の知識人はこうした「小さな政府」的な考え方をもっていたのか。
木下:神の価格は穀物についてのみ言われるのか。
答:肉についても言われるが、他には見たことがない。
木下:一般的商品価格として言われるのでないとすると、生存に関わる価格とみてよいのか。
答:今のところ、生存にかかわる価格といえる。
白川部達夫:日本の近世後期には、米穀安の諸貨高となる。マムルーク朝の場合、相対価格の動向はどうなっているのか。領主階級は、米で年貢をとって販売しているので、米の値段を上げようとするが、その力量がない。マムルーク朝が市場に介入して価格を上下できるその市場構造はどのようなものか。
原:サブタイトルに「市場社会」とあるが、どういう意味か。
答:加藤博氏が、法・貨幣・信用などの制度を取り上げて、市場社会の問題を論じているが、ここでは単に「貨幣による交換を媒介とした繋がり」の意味。
西尾寛治:マレー社会では食糧暴動はあり得ない。植民地以前にアドルという語が出てくるのは、統治階層の中でのみである。民衆の中ではアドルというような語はない。港市国家では王と外来商人が取引を行い、商人はカンポンに住んでいて、在地の人々は後背地に住んでいる。媒介するのは王である。植民地支配期になって始めて、商人と民衆とが接触する。その中で「彼らと私たち」という観念が出てきて、公正を回復する運動が起こる。公正と民族的なもの(移民や異民族という概念)との関連が生じる。
2-4 総合討論
立本:比較の枠組みに関していうと、秩序のレベルとして、(1)本当の秩序(神/天/真理)、(2)あるべき秩序(正しさや正義) (3)良き秩序あるいはとりあえずの秩序(公共)といった幾つかのレベルが考えられる。そのいずれを文化理念として取り上げるのか。この3つは、constitutionalに上から与えられるものといえようが、それとは別に、generativeな秩序、複雑系の秩序を語ることは可能か。法源ともいうべき(1)については、単数か複数か、秩序の根源はあるのか、などを考えるべきだろう。
原:今回は中国と西アジア、フィジーの報告だったが、インドを入れたらどうなるか。根本的な問題は、社会の秩序は放っておいたらできるのか、市場経済は放っておけば自然に秩序立つものなのか、買い占めをのぞけば公平な秩序は出来るのか−−これをどう考えるか、ということが社会をしわけするときの一つの基準となるだろう。中東はハイエクの世界であるように思われる。
三浦:中国の士大夫は民意について精密な議論をしているが、ウラマーの議論には、民意をどう掴むかという観点がないように思われる。ズルムも、神が除いてくれるのを待つべきだ、ということになる。
2-5 報告者による総括
春日:公正というテーマをもらったとき、人類学者の習性として、アングロサクソン的なfairか、民衆の観念としてのfairかといった翻訳の幅に敏感になってしまい、正面から取り上げられなかったが、フェアということについていずれ比較をしてみたいと思う。アダム・スミスがモラル・センチメントのなかで描いているフェアプレーから市場社会像を考えることもできる。
報告では、反復と差異を強調したかった。上位概念が、じつはブラックボックスであるということはよくあることだ。ある社会内部での反復の問題と、外部との差異の処理の問題があるだろう。日本のビジネスマンも、市場・資本に対して独自に解釈し接合して動いていて、全体を見通せているわけではなく、一人一人は小さなことをやっている。合理性・非合理性ということでは、必ずしも市場を説明できない。ただ、外部との接合と調整という点では、日本の方がうまくいっているとはいえるだろう。
林:近代の思想家と fairness の問題(青木氏の質問)については、よくわからない。中国語の「公」は、木下氏のご指摘の通り、「開かれている」という形容詞である。岡氏の質問の公共領域について、王夫之は、議論の場を積極的に位置づけてはいない。公論が上にあることが大事であって、下でわいわい言うことは望ましくない、という考え方である。争いに満ちた状態が却って議論の場を消してしまう、とする。経済秩序については自生的なものを考えているが。
長谷部:三浦氏の質問に対して。神意を受け取るのは誰かという問題だが、神意は個々人が受け取り実現するが、その先頭に君主と学者が立つということだろう。ウラマーと民衆とを峻別する必要はない。今回の研究会では「秩序」ということがテーマとなったが、なぜ「秩序」という語を使わなくてはならないのか、やや違和感がある。90年代に入って、ネットワーク論に対する批判に答える形で、秩序という語を盛んに使うようになったが、「秩序」という語を前提にして論ずることには問題があるのではないか。
※会場の準備と当日の運営については、岡山大学文学部青木敦氏と同学部東洋史専攻の学生諸君のお世話になりました。ありがとうございました。 (文責 岸本 美緒、三浦徹が一部修正)
今回のテーマは、日頃から関心を持っている問題であり、大変楽しく拝聴した。私は「秩序」「秩序」といつも騒いでいる人間なので、長谷部氏の指摘は耳が痛かったが、次のように考えている。凡そ人間が社会を作って暮らしている限り、そこには少なくとも、他人(敵やライバルを含めて)の行動に対するある程度の予測が共有されていると考えられる。これを広い意味での「秩序」と呼ぶことができる。必ずしも皆が整然と規則を守って行動するということではなく(例えば反則をする者もいるが)、人々の行動に対する何らかの常識的意味づけが存在する(あいつは反則をやった、として白い眼で見られる)ということである。むろん、その意味づけは人によって同じではなく、ある人間にとってルールであるものが他の人間にとっては反則だったりする。しかし、彼らが自分の正しさを主張しようとするとき、彼らはともに、その社会のなかの人々皆が共通に承認すべき基準−−一部の者がむりやり横車を押しているのではないという、人々の合意の基礎−−に言及するであろう。その観念を「公正」と名付けることができよう。公正の中身についての認識は無論、各社会によって異なり、またそれぞれの社会のなかでも異なる。しかし、公正の中身をめぐって対立する人々の間でも、公正さというものが存在する、という前提は共有されているといえるのではないだろうか。その公正さの中身や存立形態について比較することが可能だと考える。
公正な秩序に関する比較の軸としていくつかのものが考えられる。一つは、原氏が述べたように、秩序を自生的なものと考えるか否かということである〔自生的秩序( I )と設計的秩序( II )〕。個々人が全体秩序を念頭に置くことなくばらばらに行動していても、秩序が何となく自然に出来てくると考えれば、その秩序形成を人為的にかき乱さないということが「公正」さの内容となる。一方で、個々人のばらばらな行動の集合的結果について悲観的であれば、誰かが正しい秩序の枠組みを設計してそれを社会に与えなければならない。この場合「公正さ」とは、人々の行動に対して外から与えられる枠組みである。
この対比は、手続き的正義(a)と実質的正義(b)との対比とは必ずしも重なり合わない。人間が本来、利他的であり共同性を持つものと考えれば、放っておくことによって実質的に正しい秩序が形成される(I b)。放っておけば利己的な人間が争いあう禽獣のような世界になると考えれば、君主や聖人が正しい秩序を提示して人々を教化・強制しなければならないということになる( I b)。実質的な結果ではなくルールにのっとることのなかに「公正」さを認める立場においても、違反者を取り締まるだけの最小限ルールをよしとするのか( I a)、がんじがらめの競技規則を定めようとするのか( II a)という違いがあるだろう。
中国には、これらの型のいずれもがあり、せめぎあいつつ社会思想の枠組みを作ってきたといってよい。漢代の塩鉄論争や宋代の新法・旧法党争は、国家主導の設計主義的政策を推進しようとする人々と民間の自生的な秩序形成を強調する人々との対立といえる。また、一般に実質的正義が重視される傾向があったとはいえ、手続き的公正さの重要性も無視されていたわけではなかった(人治と法治)。ただ、全体として、中国の場合、穏健な一般の官僚はもとより、王夫之のような「ファナティック」な学者であっても、公正さのいずれかの型を原理として徹底的に主張するということなく、結局は「バランス感覚」に収斂していくような議論をするのである。これはどういうことかと考えると、公正さを主張するやり方として、まず社会の「全体」を念頭に置いて「全体」にとって最適な方策は何かを考えるという思考方式(甲)に基づくように思われる。それに対比して、個人であれ団体であれ、まず社会の個々の部分を念頭におき、それぞれの部分の固有の権利から発想する、という公正観念(乙)を考えることができる。
Bin Wong氏(9月の研究会で報告されたアメリカの研究者)にならって、前者(甲)をcommitment 型、後者(乙)を claim型、と名付けよう(ここで詳しく論ずることはできないが、寺田浩明氏の「権利と冤抑」をめぐる議論や「満員電車」論もこれと重なる)。ウォン氏によれば、近世西欧の国家形成においては、政府は、国家に対する身分団体や個人の対抗的な権利主張に直面しつつ、個々の要素の権限を法的に確定する形で秩序形成を進めてきた。それに対し、中国の場合、国家は、民間団体や個人を包含した普遍的利益の体現者として、全体社会のために最も適切な(介入しすぎず放任しすぎない)コミットメントを行うことが求められていたのである。18世紀の食糧暴動においても、西欧では、モラル・エコノミー的な「公正」の原理とポリティカル・エコノミー的な「公正」の原理とが鋭く対立する局面があったのに対し、中国の食糧暴動の論理は、適正なバランスのとれたコミットメントの要求にあった。そうしたコミットメントは無論、君主と政府が行うべきものであるが、いやしくも学問を学んだ君子たる者は、そうしたコミットメントの責任を分有するものである。
「公正」の内容が、「生存権」型の実質的権利であれ「自由権・平等権」型の形式的権利であれ、全体社会に対し対抗的に主張できるようなクレームとして提出される社会と全体社会の利益を増進しようとする立場そのものが「公正」とされる社会とでは、社会の手触りが相当違うように思われる。「公正」の観念が現実的に意味をもつためには、意見の異なる対立者を許容して秩序のなかに含み込む寛容さが「公正」観念のなかに埋め込まれていなければならないが、クレーム型では、それは意見の異なる者それぞれに固有の権利を与えるという形で与えられ、コミットメント型では、意見の異なる者がいるという現実を考慮しつつ最善の結果を模索するバランス感覚のなかに求められる。
「公正」に関わる比較の対比軸は、以上述べた I − II、a−b、甲−乙、のほかにも色々あるであろうが、とりあえず思いついたことを備忘録的に書かせていただきました。
論点を豊富化するために、参加者から研究会後にいただいたコメントを掲載します。
初参加で、岡山まで来てしまいました。文化相対主義に則っての時空間を越え
た大型比較研究は、最近あまり人類学でもしなくなってきているところなので、
大変頼もしい大胆な企画を歓迎します。
春日氏のフィジー会社の話は既に聞いたことのある話なのですが、本当の=あ
るべき経済秩序/本当でない=偽の経済秩序という対立がフィジー人の経済活動
に常につきまとう、というのは興味深い指摘です。これは、フィジー(だけでな
く、この地域の諸社会すべて)の経済活動に植民地主義の刻印が深く押されてい
るということなのでしょう。2つの異なるシステムが接合された結果として、先
住民であるフィジー人たちにとって偽の経済秩序が成立している。ただし、彼ら
が考える「あるべき経済秩序」というのを公正な経済秩序と考えていいかどうか
に、私は疑問をもちました。もしもこれが経済領域でのカーゴカルトだと考える
ならば、当然その理想とする経済秩序は、フィジー人と白人の関係において、現
在の状態が転倒した秩序でして、それはフィジー人にはあるべき経済秩序でしょ
うが、白人にとっての公正な経済秩序であるかどうか、わかりません。万人に
とっての公正さが想起されているかどうか。相対的でない公正な経済秩序という
ものに至るのに、大きな乗り越えが必要なのだと思います。とすれば、ポストコ
ロニアルの社会には、未だ「(絶対的な)公正さ」という概念が存在しているとは考
えにくい
のであって、それが実現されたらポストコロニアルの状況が乗り越えられたとい
うことになるのでしょうか。
趣意説明にもあるように、公正さという概念はやはり神(などの絶対的価値)
のいるところに成立するものなのでしょうか。林氏の議論中の公正さは、大変哲
学的で、中国思想に全く疎い私には大変難しかったのですが(しかし、公正さは
やはり絶対的な存在たる「天」にその根拠を辿るようです)、長谷部氏の議論は
もっと明瞭で、「公正さ」は「神の価格」のように、神に与えられたものとして
示されているわけです。しかし、そこまで図式的に考えるならば、結果は目に見
えていたはず、とちょっと反省。大変よいブレインストーミングでありました。
私は初めての参加であったが、西暦2000年、年末の一日、多分野からの充実し
た研究者の参集、報告、質疑によって、考察への刺激に満ちた時間を過ごすことが出
来た。
当日行われた三つの報告は、いずれも、細部のリアリティーを備えた、それぞれ異
なる地域、領域からの報告であった。細部のリアリティーとは、それぞれの事例に現
れる具体的な「振る舞い」への生々しい視線であり、また何よりもそこで発せられて
いた、あるいは資料にキーとして現れる「言葉」という振る舞いへの視線であった。
この点でいずれの報告も、他領域からの「比較」への取り付きにおのずから開かれた
ものとなっていたと私は観た。
報告、質疑、討論ともに「秩序」「規範」がキーテーマとなっており、これと関連
して「あるべき・・・」という言葉も出ていた。各報告の提出する「振る舞い」「言
葉」はもちろんこのキーテーマに向けて取り上げられていたのである。しかし、それ
らの「振る舞い」「言葉」のもつ生々しい具体性は、つまり人間の為しごととしての
そのリアリティーは、この「秩序」「規範」というタームの示す線型性・表層性に終
には収束し得ないのではないかという感を、漠然とではあるが、質疑、討論の発言を
聞くうちに抱かざるを得なかった。これは、これまでの議論に無知な、初参加者であ
るが故のことかもしれないが。
生々しい為しごとの絡み合う人間集団の生存、生活に「秩序」はそもそも「ある」
のだろうか。研究会での報告、質疑を思い返し、この辺りから自身のテーマとして詰
めてみようかと考えている。