

このページは、最近出版された歴史・人類学関係の本のうちから、研究分担者が興味を持ったものを選んで簡単な文章とともに紹介するものです。
|
|
|
|
|
|
イラン近代の原像 八尾師 誠(東京大学出版会、1998) |
東大出版会の「中東イスラム世界」シリーズ完結編。全体はI「場の表象」とII「革命の心性」の二部から成る。Iでは、西川長夫の提唱する「国民統合の諸条件」を下敷きにして、それらが今日の国民国家イランの形成にどのような役割を果たしてきたかが検討される。また、分断され、トルコ語が日常会話に使われるアゼルバイジャンという一地域が、いかに国民国家イランに統合されていったのかも論じられる。充実し、読み応えがある。それに比べると、本編であるはずのIIは、分量的にも、内容的にもややもの足りなく感じる。一般向けの書物なのだから、本の題名であるサッタール・ハーンの思想や行動、そして立憲革命の意味などをもっと詳しく、かつ、分かりやすく論じてもよかったのではないだろうか。(羽田 正) |
|
|
アブー・スィネータ村の醜聞 加藤 博(創文社、1997) |
「けたたましい本」という東京大学某教授の評もあるが、けたたましいだけではなく、優れた歴史記述の本だと思う。偶然見つけた百年以上前の文書に出てくるある村の村長職をめぐる争いが、今もなおその村の人々に記憶され、村社会に影を投げかけているということを知れば、誰でも興奮してある程度はけたたましくなるだろう。文書研究と現地調査を結び付けて歴史を考えようとする著者の熱い思いがひしひしと伝わってくる本である。(羽田 正) |
|
|
オスマン帝国の時代 林 佳世子(山川出版社、1997) |
加藤氏の本が荒れ狂う波涛を想起させるとすれば、この本はそれとは対照的に、静かな湖の鏡のような水面を思わせる。著者の思いは水面下に深く潜行し、叙述は淡々と進む。しかし、その内容は実はきわめて革新的で、随所でこれまでのオスマン朝史理解の見直しをさらりと提言している。記述が現在のトルコ地域に偏っているとか、文化についての記述が少ないとか、批判はありえようが、わずか原稿用紙百枚にこれだけの内容を盛り込んだ著者の力量に拍手。(羽田 正) |
|
|
イスラーム世界の興隆 佐藤 次高(中央公論社、1997) |
中央公論社『世界の歴史』シリーズ全30巻には、イスラーム関係として三巻が用意された。本書はそのトップ・バッターで、イスラムの勃興から15世紀までを扱う。30数年前の前回のシリーズでは、全16巻のうちに『西域とイスラム』(岩村忍)という巻があるだけ。463頁のこの本の中で本書の内容にあたる部分はわずか60頁ほどにすぎなかった。この間わが国におけるイスラーム世界史研究がいかに進んだかを知るために、本書と岩村氏の本を比べて読んでみるのも面白い。(羽田 正) |
|
|
ムガル美術の旅 山田 篤美(朝日新聞社、1997) |
ムガル美術と建築に関するわが国でほとんど初めての本格的な書物。一般向けだが、内容はきわめて濃い。著者は邦文、外国語の基本的な文献を丁寧に読み、チャハール・バーグの起源、ペルシア文化圏で青色が好まれた理由、ムガル朝初期に肖像画が量産された理由などについて、大胆な仮説を提唱している。イスラーム世界史研究は盛んになったけれども、美術史や建築史など文化史の研究はまだまだこれから。その意味でもこのような本格的な本の出版は喜ばしい。(羽田 正) |
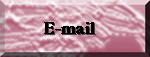
|
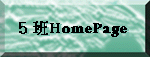
|

|