

杉田英明
昨九十八年の秋十月、文部省の科学研究費補助金を得て、十日間ほどイランを訪問する機会があった。渡航の直接の目的はイラン庭園文化に関する資料 集であったが、それとは別に、私は個人的な竊かな願いも抱いていた。百八十年前、日本人として初めてイラン(当時のペルシア)を訪れた「吉田正春使節団」の足跡を辿ってみたいという希望である。
この一行は、外務省御用掛であった吉田を団長に、参謀本部の古川宣誉(のぶよし)ほか商人5名、それにインド人通訳やペルシア人料理人など総勢十人で構成され、イランと日本の国交樹立の前提となる国情・商況調査のために日本から派遣された使節団だった。一八八〇年(明治13)七月、彼らは南部のペルシア湾岸の町プーシェフルを出発、騾馬の背に跨がってイラン高原を北上し、途中シーラーズやイスファハーン、ペルセポリス遺跡などを経たのち、四十二日間で主都テヘランに到着した。そこで当時の皇帝に拝謁し、一応の目的を果たしてから、カスピ海を渡ってイスタンブルへと抜けている。
その旅行記が、古川宣誉の『波斯紀行』(一八九一年)および吉田正春の『回彊探検・波斯之旅』(一八九四年)という形でまとめられ、日本人最初のイラン体験の記録として大きな歴史的評価を得ていることは改めて言うまでもないだろう。ここでの「波斯(はし)」とは、当時ペルシアを表記するさいに日本で一般的に用いられていた漢語、「回彊」とはイスラム世界といった意味である。とくに後者は、中公文庫に『ペルシアの旅』と題する普及版が収録されているので、誰でも簡単に読むことができる。彼らのイラン旅行の道程中、北側のシーラーズからテヘランまでは現在主要な観光コースに入っており、道路も整備されていて訪れる人も多い。しかし、シーラーズ以南はめぼしい観光遺跡もなく、日本ではほとんど具体的情報が得られないのが実情である。そこでこの区間について実地に赴いて、現状を確かめてみたいというのが私のささやかな願いであった。
十月初頭、秋の気配の漂うテヘランから飛行機で一時間半の距離にあるブーシェフルは、真夜中近くだと言うのに、空港に降り立った途端むっとするような熱暑であった。予約しておいた新しいホテルはさすがに冷房を入れていたが、外との温度差が余りに激しいため、持っていたカメラの内部に水滴がたまり、しばらくは使い物にならぬほどだった。翌日も早朝から大変な湿気と熱気である。町にクーラーが普及し始めたのはほぼ十年前からと言うが、それ以前は夏場、どんなにか過ごしにくかったことだろう。吉田正春らはじじで真夏に1ヶ月近く足止めを食い、「夜間の蚊群と昼間の蠅群」に悩まされつつ「喘息困睡の外なかりき」という無聊(ぶりょう)の日々を過ごしたのだった。
プーシェフルはかつてはイギリス東インド会社の拠点が置かれ、ペルシア湾の商業・軍事上の重要な港町だった。しかし現在では、繁栄を東側のバンダレ・アッバースに奪われ、眠ったような静かなたたずまいを見せている。海に突き出た岬に町の主要部は集中し、市街の外周を海岸沿いに一時間程も歩けば、その全貌はほぼつかめてしまう。ホテルの宿泊客の大半は、近くの石油・天然ガスの会社に勤める社員だということだ。
ここからシーラーズへ至るには、まず二千メートル級のザグロス山脈に取りつき、イラン高原に出ねばならない。吉田正春一行は、この区間の突兀魔天、犬牙錯綜の巨巌のあいだにからむ一条の隘路を、騾馬で懸命に命を預け、十日間かけて踏破している。「赭岩累積して奇怪なる組織を現はし、一望点緑なく石筍参差」という風景は昔と少しも変わらぬものの、戦後新しい舗装道路が作られたため、現在ではバスで五時間ほどの行程である。山あいの急カーブの道を辿ってぐんぐん高度を上げてゆくと、ブーシェフルの熱暑が嘘のように涼しくなった。ボラーズジャーン、ダーレキー、コナールタフテ、カーゼルーンと、吉田正春の旅行記で旧知の村々を過ぎ、シーラーズに近づく頃には、猛烈な雷鳴と稲妻を伴った豪雨である。運転手の音頭で、乗客が皆一斉に、雷除けのための聖句を唱え始めたのも珍しい光景だった。
たまたまバスで隣り合わせた青年は、プーシェフル出身のシーラーズ大学の学生で、毎週一回、大学の寮と実家とのあいだをこのバスで往復しているのだという。吉田正春の時代の旅の苦労が夢のような話である。故郷を観光地化して、町おこしするのが将来の目標だと語っていたが、果たしてうまくゆくだろうか。
その後テヘランの書店を覗いていたら、旅行記の集められた棚に、何と吉田正春の『波斯之旅』のペルシア語訳が並んでいるのに気がついた。訳者は大阪外国語大学のハーシェム・ラジャブザーデ教授、一九九四年の刊行である。この訳書によって、現代のイラン人が百年以上前の日本人の希有の体験を少しでも知ることができるとすれば、それは現代のイラン・日本双方にとって大きな贈り物となるに違いない。
『教養学部報』(1999.2.3)より転載
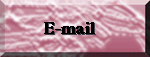 |
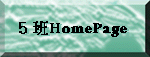 |
 |